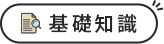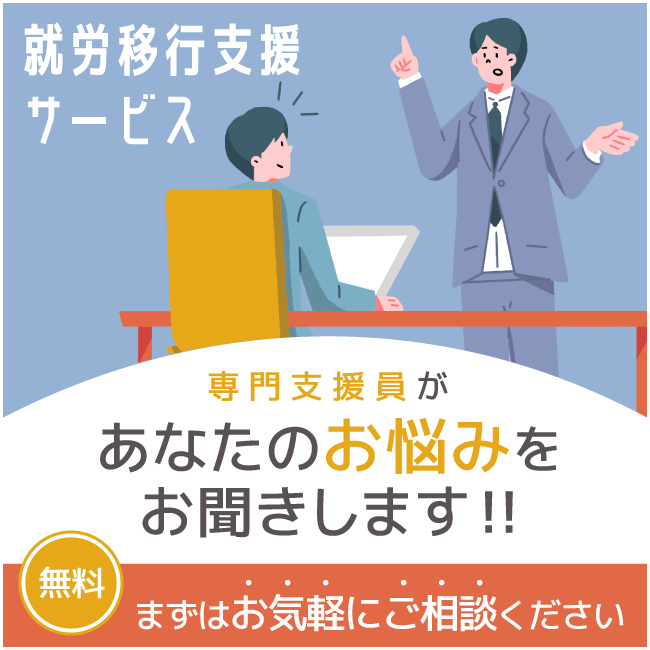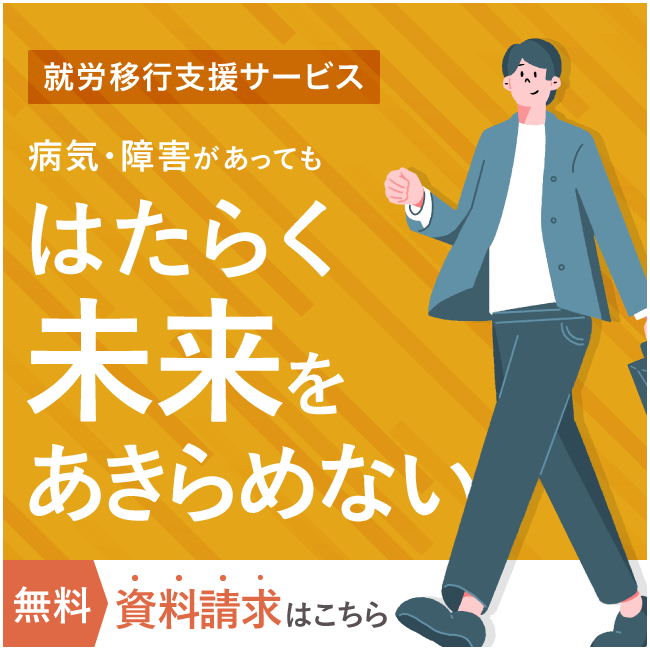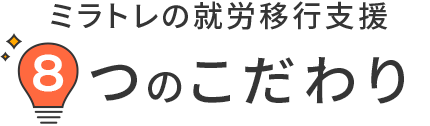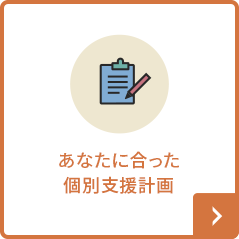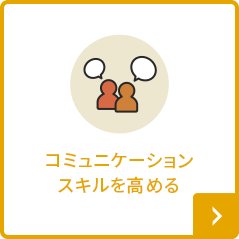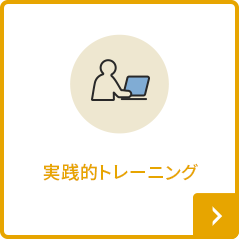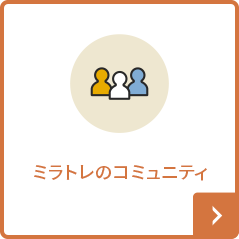ミラトレノート
就労移行支援の
 基礎
基礎 知識
知識



障害支援区分とは、障害のある人に必要な支援の程度を表す目安です。障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスを利用する際に必要となる場合があり、区分によって利用できるサービスや内容が異なります。そのため、障害福祉サービスを利用しようと検討中の人は、障害支援区分の認定が必要かどうか、事前に確認しておく必要があります。この記事では、障害支援区分の基礎知識と、認定手続きの流れや調査項目、利用できるサービスについて詳しく解説します。
障害支援区分とは
障害支援区分とは、「障害のある人に必要となる支援の度合い」を総合的に判断した区分のことです。障害の程度などによって、1~6段階に分けられており、数字が大きいほど支援の度合いも高くなります。障害支援区分の対象者は、障害のある18歳以上の人です。
障害支援区分は、障害者総合支援法にもとづく介護サービスなどを受ける際に必要となります。認定には、居住する市区町村の福祉課に申請して認定調査を受ける必要があり、主治医の意見書や調査員による調査によって区分が決定されます。
以前は「障害程度区分」と呼ばれていましたが、2014年4月から「障害支援区分」へと名称を変更しています。
障害支援区分は、障害者総合支援法にもとづく介護サービスなどを受ける際に必要となります。認定には、居住する市区町村の福祉課に申請して認定調査を受ける必要があり、主治医の意見書や調査員による調査によって区分が決定されます。
以前は「障害程度区分」と呼ばれていましたが、2014年4月から「障害支援区分」へと名称を変更しています。
障害者総合支援法とは?
障害者総合支援法とは、障害や難病のある人の支援について定めた法律です。2013年に「障害者自立支援法」が改正され、2013年4月から「障害者総合支援法」として施行されています。
障害者総合支援法の目的は、障害や難病の有無にかかわらずすべての人が尊厳をもって生活できる社会の実現を目指すことにあります。
障害者総合支援法の支援は「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つに大別されます。
障害者総合支援法の目的は、障害や難病の有無にかかわらずすべての人が尊厳をもって生活できる社会の実現を目指すことにあります。
障害者総合支援法の支援は「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つに大別されます。
障害者総合支援法の対象者は?
障害者総合支援法の対象者は、次の通りです。
- 障害者総合支援法の対象者
【1】以下の条件に当てはまる18歳以上の人
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者(発達障害者を含む)
【2】障害児
・身体・知的・精神に障害のある満18歳未満の児童。発達障害児も含む。
【3】難病患者
・障害者総合支援法で指定されている難病のある18歳以上の人。
※上記の難病の種類については、厚生労働省のサイトで確認できます。
厚生労働省:『障害者総合支援法の対象疾患(難病等)』
参照:厚生労働省『障害者総合支援法について』
障害支援区分の認定調査とは?手続きの流れと項目
障害支援区分の認定調査とは、障害のある人が必要とする支援の度合いを調査し、非該当もしくは1~6区分の7段階で判定する調査です。認定を受けるには、お住まいの市区町村の福祉窓口へ申請し、調査を受ける必要があります。
ここでは、障害支援区分の認定調査について、用いられる認定調査項目と手続きの流れについて解説します。
ここでは、障害支援区分の認定調査について、用いられる認定調査項目と手続きの流れについて解説します。
障害支援区分の認定手続きの流れ
障害支援区分の認定手続きから調査までの流れは次の通りです。
出典:厚生労働省『障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要』
1.市区町村の窓口へ申請
2.医師意見書の取得
3.認定調査員による認定調査
4.一次判定(コンピューター判定)
5.二次判定(市町村審査会)
6.市区町村による認定
7.申請者への通知
障害支援区分の認定手続きは、お住まいの市区町村の福祉窓口へ申請したのち調査を受ける流れです。認定調査員による認定調査では、調査員が自宅に訪問して認定調査項目(全80項目)の聞き取りを実施します。
一次判定では、認定調査員による調査内容と医師の意見書の一部をもとにコンピューターによって自動で判定されます。
その後、市区町村の審査会において、認定調査と医師の意見書の特記事項など複数の要素をもとに、総合的に判断し区分が決定されます。
区分が決定したら、「障害福祉サービス受給者証」が発行され、該当するサービスを利用できるようになります。
また、認定結果は申請から2カ月程度かかることがあるため、申請は余裕をもっておこないましょう。
なお、障害支援区分の有効期限は原則3年となっています。そのため、継続してサービスを利用したい場合は、再度認定調査を受けて更新手続きをおこなう必要があります。
1.市区町村の窓口へ申請
2.医師意見書の取得
3.認定調査員による認定調査
4.一次判定(コンピューター判定)
5.二次判定(市町村審査会)
6.市区町村による認定
7.申請者への通知
障害支援区分の認定手続きは、お住まいの市区町村の福祉窓口へ申請したのち調査を受ける流れです。認定調査員による認定調査では、調査員が自宅に訪問して認定調査項目(全80項目)の聞き取りを実施します。
一次判定では、認定調査員による調査内容と医師の意見書の一部をもとにコンピューターによって自動で判定されます。
その後、市区町村の審査会において、認定調査と医師の意見書の特記事項など複数の要素をもとに、総合的に判断し区分が決定されます。
区分が決定したら、「障害福祉サービス受給者証」が発行され、該当するサービスを利用できるようになります。
また、認定結果は申請から2カ月程度かかることがあるため、申請は余裕をもっておこないましょう。
なお、障害支援区分の有効期限は原則3年となっています。そのため、継続してサービスを利用したい場合は、再度認定調査を受けて更新手続きをおこなう必要があります。
障害支援区分の認定調査項目とは
障害支援区分でサービス内容が変わる自立支援給付とは?
自立支援給付とは、障害のある人を対象に障害福祉サービスの利用にかかる費用の負担を軽減する制度です。
対象となる障害福祉サービスは、次の5つです。
対象となる障害福祉サービスは、次の5つです。
- ・介護給付
・訓練等給付
・自立支援医療
・補装具費支給制度
・相談支援
上記サービスの中には、障害支援区分によって受けられるサービスや内容が異なるものがあります。
以下で、それぞれの内容や対象者について解説します。
以下で、それぞれの内容や対象者について解説します。
介護給付
介護給付は、障害のある人の身の回りの生活をサポートするサービスです。障害支援区分によって受けられるサービスと内容が異なります。
代表的な障害福祉サービスと、利用可能な区分を一覧にまとめました。
代表的な障害福祉サービスと、利用可能な区分を一覧にまとめました。
| サービス | 非該当 | 区分1 | 区分2 | 区分3 | 区分4 | 区分5 | 区分6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同行援護 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 短期入所 (ショートステイ) |
× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 居宅介護 | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 生活介護 | × | △ | △ | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 行動援護 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 施設入居支援 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 重度訪問介護 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 療養介護 | × | × | × | × | × | △ | 〇 |
| 重度障害者等包括支援 | × | × | × | × | × | × | 〇 |
※△は例外あり
各サービスの利用要件の詳細や例外、その他のサービスなどは、厚生労働省のサイトで確認しましょう。
出典:厚生労働省『障害福祉サービスについて』
訓練等給付
訓練等給付は、障害のある人が日常生活や社会生活において必要な訓練を受けられるサービスです。障害支援区分の認定を受けなくても利用できますが、唯一、共同生活援助(グループホーム)では、一定の条件下において障害支援区分の認定が必要となる場合があります。
訓練等給付は、主に次のようなサービスが挙げられます。
訓練等給付は、主に次のようなサービスが挙げられます。
| サービス | 内容 |
|---|---|
| 就労移行支援 | 一般企業への就労を希望している人に、就労に必要な知識と能力向上のための訓練をおこなう |
| 就労定着支援 | 就労後の職場や生活における課題について支援をおこなう |
| 就労継続支援A型・B型 | 一般企業での就労が困難な人に、就労機会を提供 |
| 自立生活援助 | 一人暮らしに必要な生活スキルを補う |
| 共同生活援助 | 共同生活を営む住居において、相談や日常生活での援助をおこなう ※ただし、入浴・排せつ・食事などの介護を伴う場合は障害支援区分の認定が必要 |
自立支援医療
自立支援医療は、心身の障害を軽減もしくは除去するために必要な医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。
自立支援医療の種類と対象者は以下の通りです。
自立支援医療の種類と対象者は以下の通りです。
| サービス | 対象者 |
|---|---|
| 精神通院医療 | うつ病や統合失調症などの精神疾患で、継続的な通院をする人 |
| 更生医療 | 身体障害者手帳を交付されている18歳以上の人で、手術や治療によって障害の除去・軽減が確実に見込める人 |
| 育成医療 | 更生医療を受ける対象が18歳未満の人 |
出典:厚生労働省『自立支援医療制度の概要』
補装具費支給制度
補装具費支給制度とは、障害のある人が身体機能を補う「補装具」を購入する際に、費用負担を軽くする制度です。
補装具費支給制度の適用となる補装具には、主に次のものが該当します。
補装具費支給制度の適用となる補装具には、主に次のものが該当します。
- 補装具費支給制度の適用例
・車椅子
・義肢
・義眼
・眼鏡
・補聴器
・人工内耳
・視覚障害者安全杖 など
相談支援
相談支援は、障害のある人やその家族を対象にしたサービスで、大きく分けて「計画相談支援」と「地域相談支援」の2種類があります。
計画相談支援では、障害福祉サービスの申請に必要な「サービス等利用計画案」を作成します。地域相談支援では、障害のある人が地域生活を送る際に必要なサポートや相談をおこなっています。
計画相談支援では、障害福祉サービスの申請に必要な「サービス等利用計画案」を作成します。地域相談支援では、障害のある人が地域生活を送る際に必要なサポートや相談をおこなっています。
障害支援区分の認定が必要ない福祉サービスも多い
障害支援区分の認定が必要なサービスを紹介しましたが、障害支援区分の認定が必要ない福祉サービスもあります。主なサービスとして、次のものが挙げられます。
- サービス例
・就労移行支援
・就労継続支援(A型・B型)
・就労定着支援
・自立訓練(生活訓練)
・自立生活援助
・共同生活援助(グループホーム)※ただし、入浴・排泄・食事等の介護を伴わないもの
・地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援) など
上記サービスは、障害福祉サービスの中の「訓練等給付」「相談支援給付」に当たります。このように、障害支援区分の認定を受けなくても利用できるサービスも多いため、まずは自分が利用したいサービスの利用条件を確認することが大切です。
障害支援区分を理解して必要な支援を受けよう
障害支援区分は、障害福祉サービスなどを利用する際に必要となる場合がある区分です。障害の種類や程度によって1~6段階に分けられており、数字が大きいほど支援の度合いも高くなります。そのため、自身が希望する福祉サービスの対象者かどうかは、障害支援区分によって異なる可能性があります。
まずは、自身に必要な障害福祉サービスを見つけて、障害支援区分の認定が必要な場合は申請をおこないましょう。障害支援区分の認定には、申請から2カ月程度かかることがあるため、申請は余裕をもっておこなうと安心です。
就労移行支援事業所「ミラトレ」では、障害のある人が就労に向けた一歩を安心して踏み出せるようサポートしています。利用者の障害特性を理解した上で一人ひとりの課題や能力に配慮しながら、就職までの準備はもちろん、職場への定着までを総合的に支援します。ミラトレの利用方法やサービスについて気になる方は、気軽にお問い合わせください。
※関連記事:『就労移行支援とは』
まずは、自身に必要な障害福祉サービスを見つけて、障害支援区分の認定が必要な場合は申請をおこないましょう。障害支援区分の認定には、申請から2カ月程度かかることがあるため、申請は余裕をもっておこなうと安心です。
就労移行支援事業所「ミラトレ」では、障害のある人が就労に向けた一歩を安心して踏み出せるようサポートしています。利用者の障害特性を理解した上で一人ひとりの課題や能力に配慮しながら、就職までの準備はもちろん、職場への定着までを総合的に支援します。ミラトレの利用方法やサービスについて気になる方は、気軽にお問い合わせください。
※関連記事:『就労移行支援とは』

執筆 : ミラトレノート編集部
パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業ミラトレが運営しています。専門家の方にご協力いただきながら、就労移行支援について役立つ内容を発信しています。
アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3

アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3