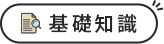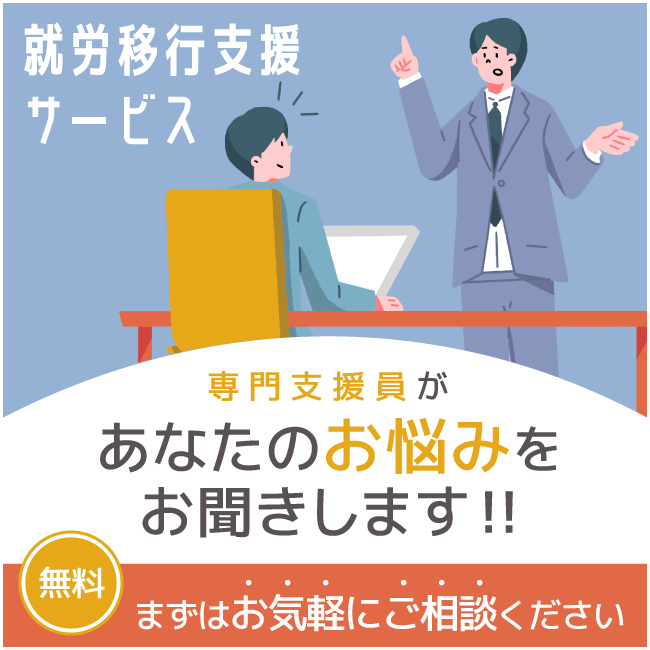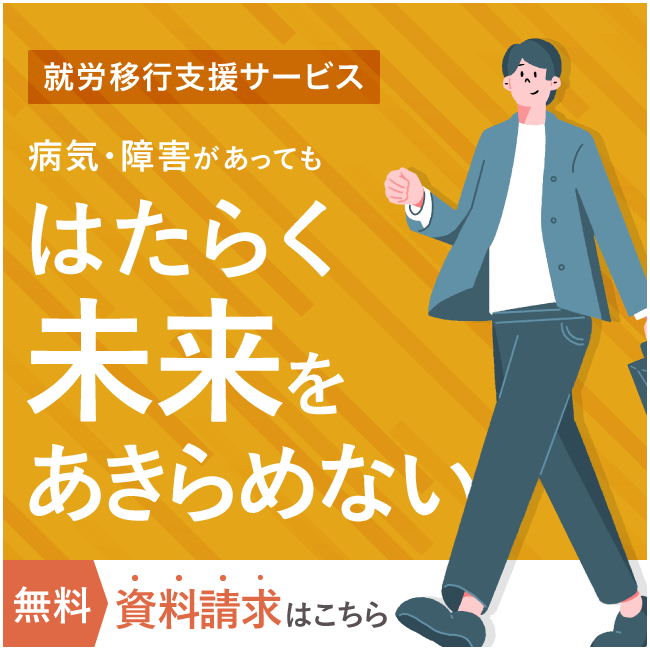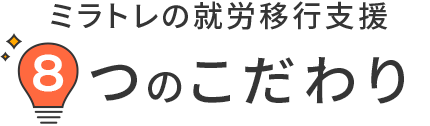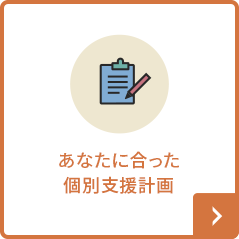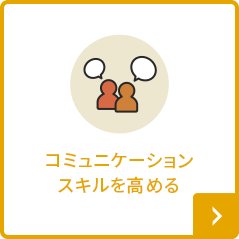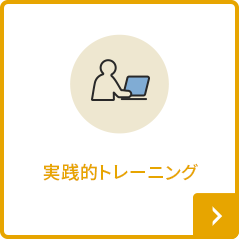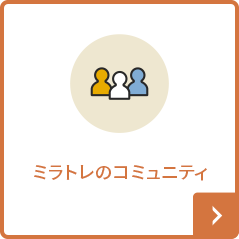ミラトレノート
就労移行支援の
 基礎
基礎 知識
知識



HSPとは、直訳すると「非常に繊細な人」です。生まれつき感受性が強く、外部からの刺激に敏感なことから「生活のしづらさ」を感じやすい傾向にあります。HSPの人の中には、「どのような仕事が自分に向いているのかわからない」「HSPでも就労移行支援を利用できるのか?」と悩んでいる人もいるかもしれません。
この記事では、HSPの特徴やHSPの人が長くはたらくためのポイント、就労移行支援事業所を利用する条件について併せて解説します。
HSPとは
HSPとは、Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)の頭文字を取った略称です。生まれつき感受性が強く、外部からの刺激に敏感な「非常に繊細な人」を指します。HSPは、生まれもった脳の性質によるものであり、障害や病気ではありません。
普通の人では気づかないような些細なことに影響を受けてしまうため、周囲の人から共感を得られにくく、それが「生きづらさ」につながってしまうケースも少なくありません。
HSPを提唱したアメリカの心理学者エレイン・アーロン博士は、HSPの特徴を以下のように掲げ、頭文字を取って「DOES(ダズ)」と名付けています。
アーロン博士は、下記4つの特徴すべてに当てはまる人をHSPと定義しています。
普通の人では気づかないような些細なことに影響を受けてしまうため、周囲の人から共感を得られにくく、それが「生きづらさ」につながってしまうケースも少なくありません。
HSPを提唱したアメリカの心理学者エレイン・アーロン博士は、HSPの特徴を以下のように掲げ、頭文字を取って「DOES(ダズ)」と名付けています。
アーロン博士は、下記4つの特徴すべてに当てはまる人をHSPと定義しています。
- HSPの特徴
・Depth of Processing:考え方が複雑、深く処理する
・Overstimulation:過剰に刺激を受けやすく、疲れやすい
・Emotional response and empathy:感情の反応が強く、共感力が強い
・Sensitivity to Subtleties:感受性が強く、些細な刺激も敏感に察知する
HSPの人が感じやすい「生きづらさ」や「はたらく上での困りごと」
HSPの人は、前述した特性により「生きづらさ」や「はたらく上での困りごと」を感じやすい傾向にあると言えます。
刺激を受けやすいHSPの人は、周囲の些細な刺激が強いストレスとなりやすいです。日常生活や職場などで、場の雰囲気を敏感に察知して気を揉んだり、人の声や物音が気になってストレスを感じやすかったり
、業務に集中しづらかったりします。特に、人とのコミュニケーションや責任が求められる職場では、緊張しやすいシーンが多く、人一倍気を遣って精神的に疲弊しやすいでしょう。
また、HSPが提唱されてから日が浅いため、HSPについて詳しく知らない人もいるでしょう。周囲の人たちからの理解が得られにくい点も、HSPの人たちの生きづらさに拍車をかけています。
特性や症状に対して理解が得られないと、力を発揮しにくいため成果につながらず、自己肯定感の低下や「頑張りすぎ」による疲弊を招いてしまいます。症状が悪化した場合、うつ病や適応障害などにつながる可能性があります。ストレスや疾患により日常生活や仕事に影響が出ると、長く安定してはたらくことが困難となり、休職や退職に至る場合もあるでしょう。
そのため、HSPの人が無理なくはたらき続けるためには、自身の特性に適した仕事や職場選びが必要です。
また、日常生活や仕事に支障がある場合、病院でカウンセリングや治療を受ける選択肢もあります。生活のしづらさやはたらく上での困りごとに悩んでいる人は、適切にケアすることが大切です。
刺激を受けやすいHSPの人は、周囲の些細な刺激が強いストレスとなりやすいです。日常生活や職場などで、場の雰囲気を敏感に察知して気を揉んだり、人の声や物音が気になってストレスを感じやすかったり
、業務に集中しづらかったりします。特に、人とのコミュニケーションや責任が求められる職場では、緊張しやすいシーンが多く、人一倍気を遣って精神的に疲弊しやすいでしょう。
また、HSPが提唱されてから日が浅いため、HSPについて詳しく知らない人もいるでしょう。周囲の人たちからの理解が得られにくい点も、HSPの人たちの生きづらさに拍車をかけています。
特性や症状に対して理解が得られないと、力を発揮しにくいため成果につながらず、自己肯定感の低下や「頑張りすぎ」による疲弊を招いてしまいます。症状が悪化した場合、うつ病や適応障害などにつながる可能性があります。ストレスや疾患により日常生活や仕事に影響が出ると、長く安定してはたらくことが困難となり、休職や退職に至る場合もあるでしょう。
そのため、HSPの人が無理なくはたらき続けるためには、自身の特性に適した仕事や職場選びが必要です。
また、日常生活や仕事に支障がある場合、病院でカウンセリングや治療を受ける選択肢もあります。生活のしづらさやはたらく上での困りごとに悩んでいる人は、適切にケアすることが大切です。
HSPの人が仕事をスムーズに進めるためには
繊細で過敏な特性をもつHSPの人たちが、仕事をスムーズに進めるためには以下の2点がポイントとなります。
- ポイント
1.「弱み」を「強み」として活かす
2.自分の特性に合った仕事を選ぶ
「弱み」を「強み」として活かす
一見、マイナスなイメージのあるHSPですが、見方を変えることにより特性が「強み」になり得ます。前述した「DOES(ダズ)」の4つの特性を例に解説します。
- DOES(ダズ)の4つの特性の例
●Depth of Processing:考え方が複雑、深く処理する
→物事を深く考えることにより、本質を捉えられる
●Overstimulation:過剰に刺激を受けやすく、疲れやすい
→五感が鋭く、繊細な感性により豊かな表現ができる
●Emotional response and empathy:感情の反応が強く、共感力が強い
→高い共感力により、人の感情の変化に気づき、寄り添える
●Sensitivity to Subtleties:感受性が強く、些細な刺激も敏感に察知する
→現状把握に優れており、主観にもとづく鋭い判断ができる
「考え方が複雑で周囲の刺激に過敏」という特性は、裏を返せば「思慮深く、周囲の状況や人の感情の変化に気付ける」という「強み」と捉えられます。そのため、職場内でのトラブルの芽にもいち早く気づき、速やかに対処行動ができたり、人の悩みや不安に共感して寄り添えたりと、職場での調整役ができる人も少なくありません。
また、繊細さは、芸術や創作の分野でも力を発揮しやすく、外部からの些細な刺激が強烈なインスピレーションとなり表現に活かせるケースもあります。
このように、自身の特性を強みと捉え、視点を変えることにより、ストレスや不安が軽減できる可能性があります。
また、繊細さは、芸術や創作の分野でも力を発揮しやすく、外部からの些細な刺激が強烈なインスピレーションとなり表現に活かせるケースもあります。
このように、自身の特性を強みと捉え、視点を変えることにより、ストレスや不安が軽減できる可能性があります。
自分の特性に合った仕事を選ぶ
自分の特性に合った仕事を選ぶのも、無理なくはたらくために重要なポイントです。
HSPの人に向いている仕事の一例として、下記のようなものがあります。
HSPの人に向いている仕事の一例として、下記のようなものがあります。
- 仕事の一例
・経理・事務
・データ入力
・Webコーダー
・エンジニア
・検査や検品などライン作業
・警備員
・研究員 など
在宅や自分のペースでできる仕事、人との関わりが少ない仕事などは、刺激が少なくストレスにつながりにくいため向いていると言えます。一方で、営業職やサービス業といった、マルチタスクで人との交流が盛んな仕事には向いていないかもしれません。
仕事を選ぶ際には、自分の特性を理解した上で、それを強みとして活かせる仕事を選ぶことが、仕事をスムーズにし、長くはたらき続けるための第一歩となるのではないでしょうか。
仕事を選ぶ際には、自分の特性を理解した上で、それを強みとして活かせる仕事を選ぶことが、仕事をスムーズにし、長くはたらき続けるための第一歩となるのではないでしょうか。
おすすめの就職支援サービス
「自分に合った仕事がわからない」「はたらくことに不安がある」など、自分一人での就職活動に限界を感じた場合、次のような就職支援サービスを利用するのも選択肢の一つです。
誰でも利用できるサービスと、条件を満たすことで利用できるサービスを以下で紹介します。利用を検討する際は、自分が対象かどうか事前に確認しましょう。
誰でも利用できるサービスと、条件を満たすことで利用できるサービスを以下で紹介します。利用を検討する際は、自分が対象かどうか事前に確認しましょう。
ハローワーク
ハローワーク(公共職業安定所)は、厚生労働省が運営する就職支援機関です。求人情報の提供や応募書類作成・面接の支援、セミナー開催など、就職活動に役立つさまざまな支援をおこなっています。
また、全国のハローワークには、正社員就職を目指すおおむね35歳未満の人を対象にさまざまな就職支援を無料でおこなう「わかものハローワーク(わかもの支援コーナー・わかもの支援窓口)」も設置されています。「自分に向いている仕事がわからない」「面接に自信がない」など、一人ひとりの状況に合わせたサポートをマンツーマンで実施しているのが特徴です。
※参照:厚生労働省『ハローワーク就職活動』
※参照:厚生労働省『わかものハローワーク』
また、全国のハローワークには、正社員就職を目指すおおむね35歳未満の人を対象にさまざまな就職支援を無料でおこなう「わかものハローワーク(わかもの支援コーナー・わかもの支援窓口)」も設置されています。「自分に向いている仕事がわからない」「面接に自信がない」など、一人ひとりの状況に合わせたサポートをマンツーマンで実施しているのが特徴です。
※参照:厚生労働省『ハローワーク就職活動』
※参照:厚生労働省『わかものハローワーク』
地域若者サポートステーション
地域若者サポートステーション(通称サポステ)は、はたらくことに悩みを抱える15~49歳までの人を対象に無料で就労支援をおこなっています。全国179カ所に拠点があり、就職活動から職場定着までをサポートしています。
※参照:厚生労働省『サポステ[地域若者サポートステーション]』
※参照:厚生労働省『サポステ[地域若者サポートステーション]』
障害者就業・生活支援センター
障害者就業・生活支援センターは、障害のある人の職業生活を支援しています。全国に339カ所設置されています(2025年6月時点)。対象者は障害者手帳を取得している人ですが、障害者手帳がなくても日常生活や社会生活を送る上で困りごとがあれば利用できる可能性があります。利用の可否については、最寄りの障害者就業・生活支援センターに問い合わせてみましょう。
※参照:厚生労働省『障害者就業・生活支援センターについて』
※参照:厚生労働省『障害者就業・生活支援センターについて』
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所では、障害や難病のある人が、一般企業への就職を目的としたスキル習得や、トレーニングといった就職活動におけるサポートを受けられます。ASD(自閉スペクトラム症/アスペルガー症候群)やうつ病など、特定の精神障害・発達障害・知的障害・身体障害・難病(障害者総合支援法の対象疾病)のある人で、一定の条件を満たした人が対象となります。
就労移行支援の概要や対象者、利用料金について知りたい人は、以下の記事もご覧ください。
※関連記事『就労移行支援とは』
※参照:厚生労働省『就労移行支援について』
HSPの人も就労移行支援を利用できるかどうかについては次の項目で解説します。
就労移行支援の概要や対象者、利用料金について知りたい人は、以下の記事もご覧ください。
※関連記事『就労移行支援とは』
※参照:厚生労働省『就労移行支援について』
HSPの人も就労移行支援を利用できるかどうかについては次の項目で解説します。
HSPの人は就労移行支援を利用できる?
就労移行支援の対象者は、障害や難病のある人です。HSPは、脳の性質による特性であって障害や病気ではないため、原則として就労移行支援の利用対象にはなりません。
しかし、主治医の診断書があれば就労移行支援を利用できる可能性があります。
HSPは、その過敏性ゆえに、職場や日常生活の中で非常に強いストレスを受ける傾向にあります。自分でも気づかないうちに精神が疲弊してしまい、「うつ病」や「適応障害」といった疾病を発症してしまうケースも考えられます。
このように、HSPの特性が原因で日常生活や仕事に支障をきたし、精神疾患や障害の診断を受けている人は、就労移行支援の利用対象となる可能性があります。
就労移行支援の利用にあたって、障害者手帳の所持(取得)は必須ではありません。「障害や病気などにより、就労が困難である」ことを医師によって証明してもらい、自治体からの許可が下りればHSPの人も就労移行支援を利用できます。
HSPの人で、かつ就労移行支援の対象となる障害や難病のある人は、まず医師に相談してみるとよいでしょう。
就労移行支援が受けられる障害・難病について以下の記事で詳しく解説しています。ご覧ください。
※関連記事『就労移行支援の対象者』
しかし、主治医の診断書があれば就労移行支援を利用できる可能性があります。
HSPは、その過敏性ゆえに、職場や日常生活の中で非常に強いストレスを受ける傾向にあります。自分でも気づかないうちに精神が疲弊してしまい、「うつ病」や「適応障害」といった疾病を発症してしまうケースも考えられます。
このように、HSPの特性が原因で日常生活や仕事に支障をきたし、精神疾患や障害の診断を受けている人は、就労移行支援の利用対象となる可能性があります。
就労移行支援の利用にあたって、障害者手帳の所持(取得)は必須ではありません。「障害や病気などにより、就労が困難である」ことを医師によって証明してもらい、自治体からの許可が下りればHSPの人も就労移行支援を利用できます。
HSPの人で、かつ就労移行支援の対象となる障害や難病のある人は、まず医師に相談してみるとよいでしょう。
就労移行支援が受けられる障害・難病について以下の記事で詳しく解説しています。ご覧ください。
※関連記事『就労移行支援の対象者』
HSPの特性を理解して自分に合ったはたらき方を探そう
HSPの特性やおすすめの就職支援サービスについて紹介しました。HSPは、障害や病気ではないがゆえに周囲からの理解が得にくく、生きづらさや困難さにつながりやすい傾向にあります。そのため、自身の特性に合った職種やはたらき方を選ぶのが、長くはたらき続けるための重要なポイントと言えます。しかし、自分一人で就職活動をおこなうことが難しい人もいるでしょう。その場合には、この記事で紹介した就職支援サービスの利用も検討してみてください。
就労移行支援事業所「ミラトレ」では、障害のある人が自分らしいはたらき方を見つけ、長くはたらき続けられるよう就労をサポートしています。利用者の障害特性を理解した上で一人ひとりの課題や能力に配慮しながら、就職までの準備はもちろん、職場への定着までを総合的に支援します。
就労移行支援を利用してみたいけれど自分が対象者かどうかわからない人や、ミラトレの利用方法やサービスについて気になる方は、お気軽にご相談ください。
就労移行支援事業所「ミラトレ」では、障害のある人が自分らしいはたらき方を見つけ、長くはたらき続けられるよう就労をサポートしています。利用者の障害特性を理解した上で一人ひとりの課題や能力に配慮しながら、就職までの準備はもちろん、職場への定着までを総合的に支援します。
就労移行支援を利用してみたいけれど自分が対象者かどうかわからない人や、ミラトレの利用方法やサービスについて気になる方は、お気軽にご相談ください。

執筆 : ミラトレノート編集部
パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業ミラトレが運営しています。専門家の方にご協力いただきながら、就労移行支援について役立つ内容を発信しています。
アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3

アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3