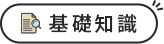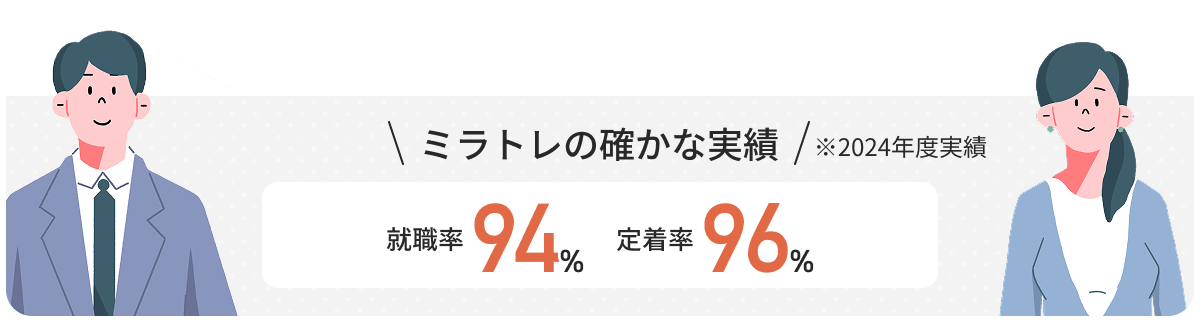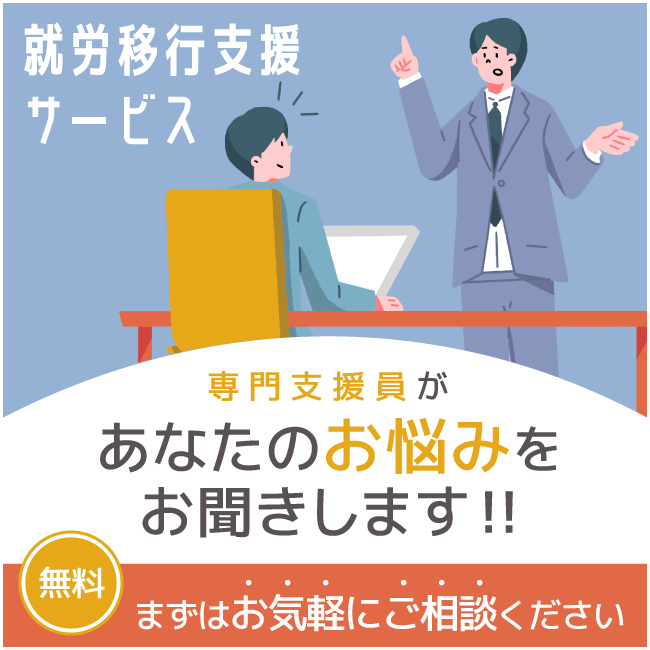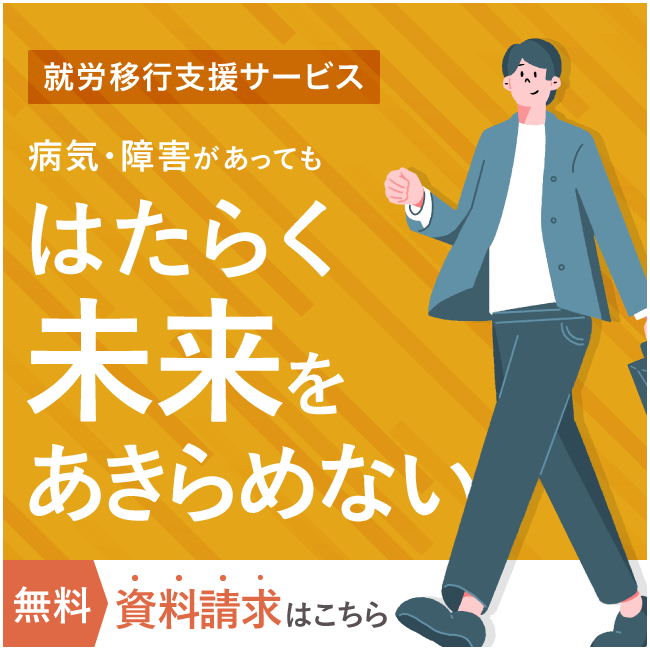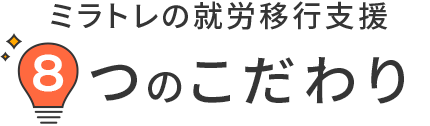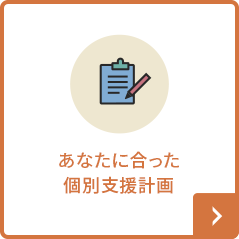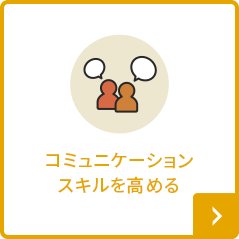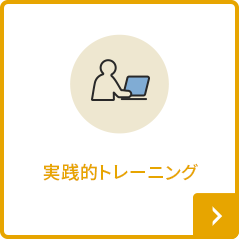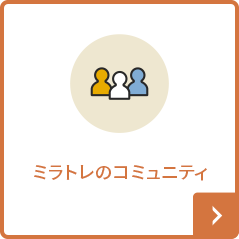ミラトレノート
就労移行支援の
 基礎
基礎 知識
知識



「非定型うつ病」とは、従来のうつ病には当てはまらない症状が出るタイプのうつ病です。比較的新しいうつ病のため「新型うつ病」とも呼ばれ、若年の女性に多くみられます。非定型うつ病の症状としては、過眠や過食が多い傾向にある点や、「楽しいこと」や「うれしいこと」など特定の物ごとに対してだけ意欲が湧く点など、定型うつ病とは異なる点が多くあります。この記事では、非定型うつ病の概要や判断基準、定型うつ病との違い、治療法について詳しく解説します。
非定型うつ病とは
「非定型うつ病」とは、従来のうつ病(以下、定型うつ病)とは異なる症状をもった「うつ病」です。病名の通り、定型うつ病の症状に当てはまらない症状をもったうつ病の一種です。男女比率は3:7と男性よりも女性に多くみられ、発症年齢の平均は定型うつ病が30代であるのに対して、非定型うつ病は20代と若年での発症が多い傾向にあります。
非定型うつ病は、国際的な診断基準であるアメリカ精神医学会の「DSM(精神障害の分類と統計マニュアル)」において、正式な病名として認められており、その診断基準が定義されています。定型うつ病よりも比較的新しいため、日本では「新型うつ病」と呼ばれることもあります。
※参照:昭和女子大学管理栄養学科、昭和女子大学女性健康科学研究所「〔報 文〕大学生における抑うつ症状および非定型うつ特徴とその関連要因の検討」)
非定型うつ病は、国際的な診断基準であるアメリカ精神医学会の「DSM(精神障害の分類と統計マニュアル)」において、正式な病名として認められており、その診断基準が定義されています。定型うつ病よりも比較的新しいため、日本では「新型うつ病」と呼ばれることもあります。
※参照:昭和女子大学管理栄養学科、昭和女子大学女性健康科学研究所「〔報 文〕大学生における抑うつ症状および非定型うつ特徴とその関連要因の検討」)
非定型うつ病の診断基準
アメリカ精神医学会の最新版DSM-5によると、非定型うつ病は以下2つの条件により診断されます。
- 条件
1.うつ病の診断基準を満たすこと
2.非定型うつ病の特徴を認めること
うつ病は、以下の症状のうち5項目以上が当てはまり、対人関係や社会的・職業的な領域において障害をきたしていることにより診断されます。
- 症状
・抑うつ気分
・興味・喜びの喪失
・体重減少・食欲減退または体重増加・食欲増加
・不眠または過眠
・精神運動の焦燥または制止
・疲労感または気力減退
・無価値感または罪責感
・思考力低下・集中力低下・決断力低下
・希死念慮・自殺企図
上記の診断基準のうち5つ以上が当てはまり、さらに以下のような特徴が認められた場合に、非定型うつ病と診断されます。
- 診断基準
1.気分の反応性がある(感情の波が激しい)
2.以下のうち2つ以上が当てはまる
・顕著な体重増加、または食欲増加
・過眠
・鉛様の麻痺(身体が鉛のように重く、起き上がれないほどの全身のだるさ)
・顕著な社会的、職業的障害をきたすほどの対人関係における拒絶過敏性
3.メランコリー型(定型うつ病や緊張性うつ病)の特徴を認めない
気分の反応性とは、「抑うつ」状態が続いている中でも、良い出来事があると反応して気分がもち上がる症状です。DSM-5では、この気分の反応性を非定型うつ病の必須症状としています。
うつ病と非定型うつ病との違い
定型うつ病と非定型うつ病の違いを、わかりやすく表にまとめました。
| うつ病 | 非定型うつ病 | |
|---|---|---|
| 気分の落ち込み | 常に落ち込んでいる | 気分がもち上がるときがある |
| 興味の喪失 | 何事に対しても興味が湧かない | 特定の事柄に対して興味がある |
| 睡眠 | 眠れない人が多い(不眠) | 常に眠い人が多い(過眠) |
| 食欲 | 普段より食欲がない人が多い(拒食) | 普段より食欲が増加する人が多い(過食) |
| ストレスの原因 | 自分自身を責めがち | 環境や他人の言動に緊張や不安を感じやすい |
| 治療方法 | 投薬治療 休養 環境を変えるだけでは改善しにくい |
投薬が効かないこともある 活動で改善することもある 環境を変えると改善することもある |
うつ病と非定型うつ病では、気分の落ち込み方に違いがあります。定型うつ病は何をするにも気分が落ち込む一方、非定型うつ病では自分が好きなことに対しては気分がもち上がり、元気になるのが特徴です。 また、うつ病では拒食や不眠となることが多いのに対して、非定型うつ病では過食や過眠が多いほか、ストレスの原因や治療方法などさまざまな違いがあります。
非定型うつ病の特徴
非定型うつ病にみられる特徴として、以下のようなものがあります。
- 特徴
・特定の事柄に対して興味・意欲が湧く
・重度の倦怠感がみられる(鉛様麻痺)
・対人関係で拒絶への過敏さがみられる(拒絶過敏性)
・不眠・拒食よりも、過眠・過食が多い
・慢性化しやすい・再発しやすい
・若年の女性に発症しやすい
非定型うつ病の一番の特徴は、普段は落ち込んでいる気持ちが続いていても、楽しいことや好きなことに対しては意欲が湧く点です。具体的には、学校や会社のある平日は気分が落ち込んでいるけれど、自分が好きなことができる休日には気分がもち上がるなど、気分に変動がある状態を指します。
また、手足に鉛が入っているかのように身体が重くてだるいといった、重度の倦怠感(鉛様麻痺)がみられるのも非定型うつ病の特徴的な症状です。定型うつ病でも倦怠感は症状として認められますが、非定型うつ病の場合は起き上がることもできないほど全身がだるくなる場合があります。
このほか、他人から否定されるような言動に対して過敏になる、慢性化・再発しやすい、若年の女性に発症しやすいのも非定型うつ病の特徴として挙げられます。
気分に変動があることから、周囲からは「仮病」や「甘え」と誤解されやすいです。しかし、抑うつ気分や倦怠感などの症状は重く、慢性化したり合併症を引き起こしたりすることもあるため、早めの治療が大切です。
また、手足に鉛が入っているかのように身体が重くてだるいといった、重度の倦怠感(鉛様麻痺)がみられるのも非定型うつ病の特徴的な症状です。定型うつ病でも倦怠感は症状として認められますが、非定型うつ病の場合は起き上がることもできないほど全身がだるくなる場合があります。
このほか、他人から否定されるような言動に対して過敏になる、慢性化・再発しやすい、若年の女性に発症しやすいのも非定型うつ病の特徴として挙げられます。
気分に変動があることから、周囲からは「仮病」や「甘え」と誤解されやすいです。しかし、抑うつ気分や倦怠感などの症状は重く、慢性化したり合併症を引き起こしたりすることもあるため、早めの治療が大切です。
非定型うつ病だと感じたら
ここまで解説した特徴や症状をみて、自身が「非定型うつ病かもしれない」と感じた場合は、すぐに心療内科や精神科など専門機関を受診しましょう。
うつ病は、定型であれ非定型であれ、適切な治療の必要な精神疾患です。気分が落ち込んでいる、気力や意欲が湧かない、身体が重くて動きづらい、食欲や睡眠に異常があるなど、日常生活に支障がある場合はうつ病の可能性があります。
非定型うつ病の治療方法は、定型うつ病と基本的に同じで以下のようなものが挙げられます。
うつ病は、定型であれ非定型であれ、適切な治療の必要な精神疾患です。気分が落ち込んでいる、気力や意欲が湧かない、身体が重くて動きづらい、食欲や睡眠に異常があるなど、日常生活に支障がある場合はうつ病の可能性があります。
非定型うつ病の治療方法は、定型うつ病と基本的に同じで以下のようなものが挙げられます。
- 治療方法
・休養・環境調整
・薬物療法
・精神療法・心理療法
・磁気刺激治療 など
ただし、うつ病の治療法が非定型うつ病に効かないケースもあります。十分な休養と投薬により効果が期待できるうつ病と違い、非定型うつ病では、休養や投薬よりも、心理療法や認知行動療法などが効果的なケースもあります。
また、非定型うつ病は再発しやすい特徴もあるため、治療が終わったあとも規則正しい生活を保ち、適度に運動したり食生活を整えたりと注意が必要です。
また、非定型うつ病は再発しやすい特徴もあるため、治療が終わったあとも規則正しい生活を保ち、適度に運動したり食生活を整えたりと注意が必要です。
うつ病の人が活用できる制度や支援
定型・非定型うつ病の人が、生活する上で活用できる制度や支援を紹介します。ただし、支援制度の利用対象かどうかは個人の状況によって異なります。自身が対象かどうかは、お住まいの自治体や制度の相談窓口で確認してください。
- 相談窓口
医療費
・自立支援医療(精神通院医療)
・心身障害者医療費助成制度 など
└東京都福祉局
暮らしと社会生活
・精神障害者保健福祉手帳 など
生活費
・障害年金
・失業保険(失業手当、雇用保険給付)
・傷病手当金 など
就労支援
・就労移行支援事業所
・ハローワーク
・地域障害者職業センター
・障害者就業・生活支援センター(なかぽつ)
・地域若者サポートステーション(サポステ)
・リワーク
・ジョブコーチ(職場適応援助者) など
さまざまな相談窓口
・基幹相談支援センター
・保健所
└都道府県別の保健所一覧
・精神保健福祉センター
└全国精神保健福祉センター一覧
・病院の患者会や家族会
└みんなねっと
・ピアサポート団体 など
└全国ピアグループ一覧
安心してうつ病の治療に専念できるよう、困りごとがある場合には支援制度の利用を検討しましょう。
就労移行支援事業所「ミラトレ」は、うつ病がある人の就職を支援します
非定型うつ病は、好きなことに対して意欲が湧くなど気分に変動があることから、周囲から理解を得にくい障害です。過食や過眠、抑うつなどの症状により日常生活に支障がある人は、早めに医療機関を受診することが大切です。
また、定型・非定型に関係なく、うつ病のある人が再就職して障害と向き合いながら長くはたらき続けたい場合、自分の特性を理解した上で自分に合ったはたらき方を見つけることが大切です。自分一人でこれらを身につけることが困難な場合は、専門の支援機関を利用しましょう。
就労移行支援事業所「ミラトレ」では、うつ病や障害のある方を対象に就労トレーニングや就職活動支援、就職後の定着支援をおこなっています。就労移行支援についての疑問や、「ミラトレ」についてのご質問、うつ病や障害に関するご相談など、お気軽にお問い合わせください。
また、定型・非定型に関係なく、うつ病のある人が再就職して障害と向き合いながら長くはたらき続けたい場合、自分の特性を理解した上で自分に合ったはたらき方を見つけることが大切です。自分一人でこれらを身につけることが困難な場合は、専門の支援機関を利用しましょう。
就労移行支援事業所「ミラトレ」では、うつ病や障害のある方を対象に就労トレーニングや就職活動支援、就職後の定着支援をおこなっています。就労移行支援についての疑問や、「ミラトレ」についてのご質問、うつ病や障害に関するご相談など、お気軽にお問い合わせください。

執筆 : ミラトレノート編集部
パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業ミラトレが運営しています。専門家の方にご協力いただきながら、就労移行支援について役立つ内容を発信しています。
アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3

アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3