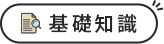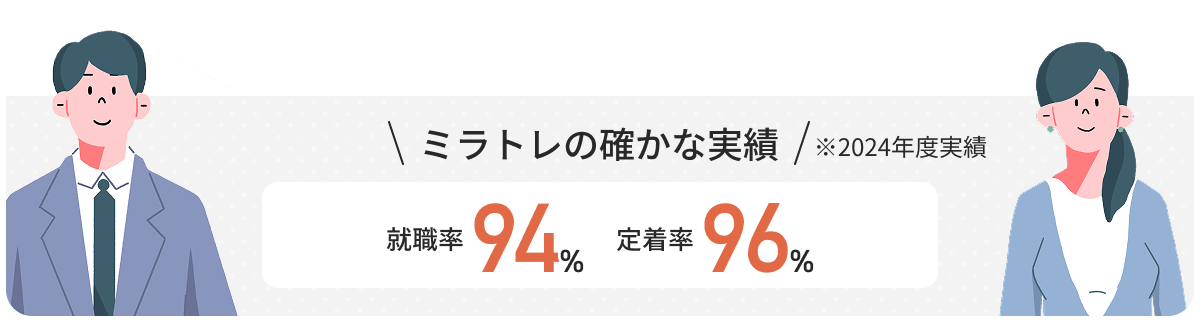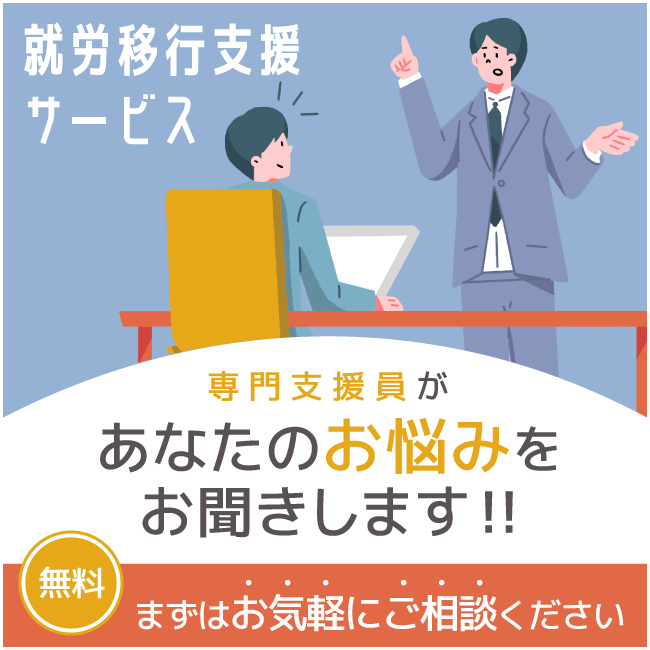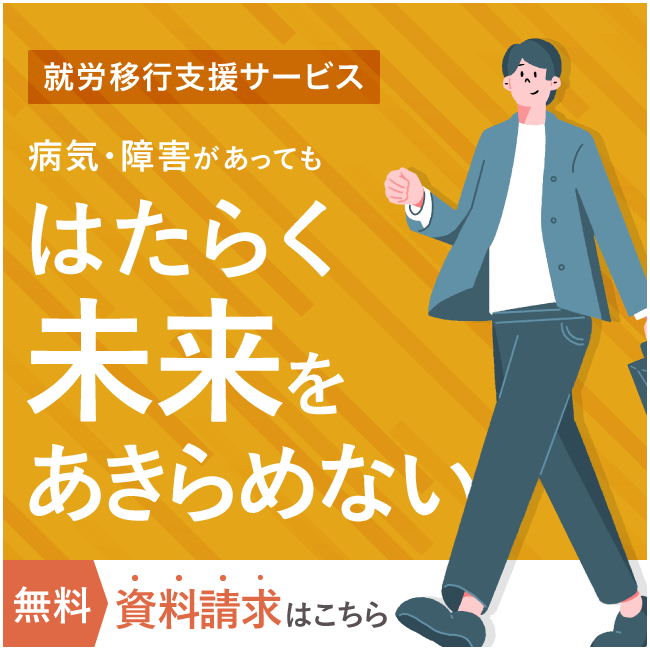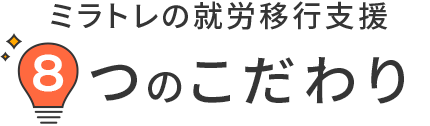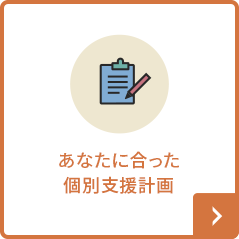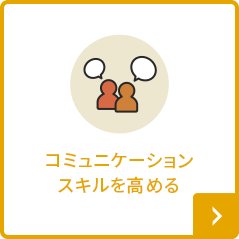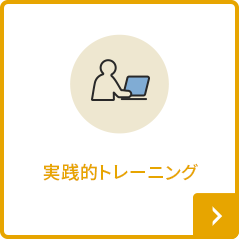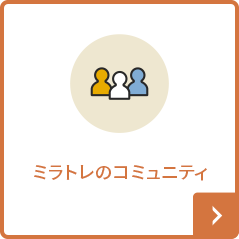ミラトレノート
就労移行支援の
 基礎
基礎 知識
知識


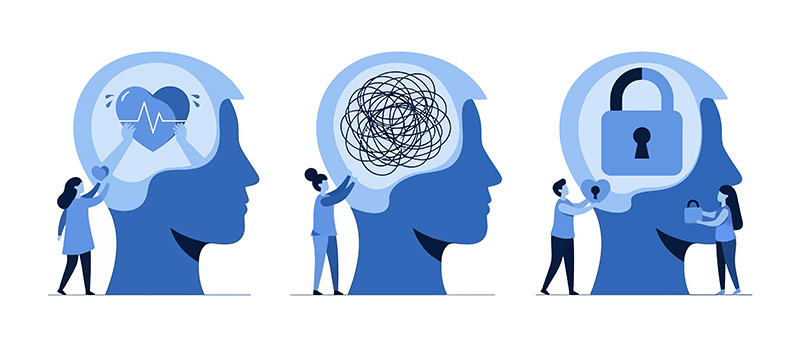
認知行動療法(CBT)とは、物事に対する思考(認知)の偏りや歪みを整え、行動を変えていくことでストレスの軽減を図る心理療法です。認知に偏りがあると、些細な出来事でも大きなストレスを感じてしまい、気持ちが落ち込んだり不安になったりと行動にも影響が出てしまいます。認知行動療法では、医師やカウンセラーとの対話を通じて、自分の認知の癖に気づき整えるトレーニングをおこないます。うつ病などの精神疾患のほか、発達障害や睡眠障害などにも効果があるとされ、広く用いられています。今回は、認知行動療法の基礎知識と技法に加えて、認知行動療法を自分で取り組む方法についても紹介します。
認知行動療法(CBT)とは
認知行動療法とは、物事に対する思考(認知)や行動にはたらきかけることで、気持ちを楽にしてストレスを軽減する治療法の一つです。「Cognitive Behavior Therapy」の頭文字を取って「CBT」とも呼ばれています。
「認知」と「行動」とは、具体的には以下のようなものです。
「認知」と「行動」とは、具体的には以下のようなものです。
| 認知 | 行動 |
|---|---|
| 思考、捉え方、記憶、イメージ、信念 | 振る舞い、習慣、活動 |
「認知」に偏りや歪みがあると、何気ない日常でもストレスを受けやすく、行動にも影響を及ぼします。
よく用いられる例えが「コップの水の話」です。
コップに水が半分入っている状態を見たときに、「半分も入っている」「半分しか入っていない」と異なる捉え方ができます。「半分しかない」と捉えた場合、残量に不安を感じて少しずつ飲もうとするかもしれません。一方で、「半分もある」と捉えると安心できるものの、楽観視するあまり一気に飲み干してしまい、後で足りなくなる可能性もあります。
このように、どちらかが良くてどちらかが悪い、という偏った捉え方をするのではなく、バランスの取れた捉え方をできるようになるのが理想です。
認知行動療法では、物事に対して「どのように思考(認知)し」「どう行動しているのか」という、自身の思考の癖や行動パターンを理解し、バランスの取り方を学びながら調整していきます。
認知行動療法は、うつ病や統合失調症、パニック障害といった精神疾患の治療に効果があることが実証され、広く用いられています。
よく用いられる例えが「コップの水の話」です。
コップに水が半分入っている状態を見たときに、「半分も入っている」「半分しか入っていない」と異なる捉え方ができます。「半分しかない」と捉えた場合、残量に不安を感じて少しずつ飲もうとするかもしれません。一方で、「半分もある」と捉えると安心できるものの、楽観視するあまり一気に飲み干してしまい、後で足りなくなる可能性もあります。
このように、どちらかが良くてどちらかが悪い、という偏った捉え方をするのではなく、バランスの取れた捉え方をできるようになるのが理想です。
認知行動療法では、物事に対して「どのように思考(認知)し」「どう行動しているのか」という、自身の思考の癖や行動パターンを理解し、バランスの取り方を学びながら調整していきます。
認知行動療法は、うつ病や統合失調症、パニック障害といった精神疾患の治療に効果があることが実証され、広く用いられています。
認知行動療法の種類
認知行動療法には、さまざまな種類の技法があります。ここでは、4つの技法について解説します。
リラクセーション法
リラクセーション法は、緊張やストレス、心配、不安などを軽減するための技法です。全般的な不安や緊張の緩和だけでなく、特定の場面における不安や緊張の緩和にも効果的です。漸進的筋弛緩法や呼吸法、イメージ技法などさまざまな技法があります。
認知再構成法
認知再構成法は、ある出来事や状況に直面した際に、無意識的・反射的に浮かぶネガティブなイメージや感情を客観的に捉え、バランスを整えて改善していく認知的技法です。認知を再構成するための方法として、「コラム法(思考記録表)」がよく使われます。コラム法は、全部で7つのステップ(コラム)に沿って、ネガティブな思考を客観的に見つめ直す訓練です。繰り返し実践することにより、より柔軟で建設的な考えを身につけていきます。
段階的暴露療法(エクスポージャー法)
不安や恐怖を感じている状況や対象に対して、段階的に慣れて克服することを目指す行動療法が段階的暴露療法(エクスポージャー法)です。不安や恐怖の対象を洗い出し、不安の程度が低いものから意図的に接していきます。繰り返しおこなうことで、徐々に慣れていく方法です。心的外傷後ストレス障害(PTSD)や強迫性障害などの治療に用いられます。
SST(ソーシャルスキルトレーニング)
SST(ソーシャルスキルトレーニング)は、日常生活や対人関係を円滑にするために必要な社会生活技能(ソーシャルスキル)を、習得・向上させるための技法です。認知行動療法の一つとして位置づけられており、社会生活技能訓練とも呼ばれています。
SSTでは、職場や実生活で起こった困りごとを想定してロールプレイをおこなったり、ディスカッションや共同作業などを通じてコミュニケーションスキルの向上を図ったりします。心療内科のほか、リワークや就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所などでも実施している場合があります。
SSTでは、職場や実生活で起こった困りごとを想定してロールプレイをおこなったり、ディスカッションや共同作業などを通じてコミュニケーションスキルの向上を図ったりします。心療内科のほか、リワークや就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所などでも実施している場合があります。
認知行動療法が有効な疾患
認知行動療法は、うつ病の治療法として開発されたものですが、うつ病以外にも以下のような精神疾患やそのほかの病態にも効果があるといわれています。
- 認知行動療法が有効な疾患
うつ病
双極性障害(躁うつ病)
統合失調症
強迫性障害
パニック障害
社交不安障害
発達障害
摂食障害
パーソナリティ障害
PTSD(心的外傷後ストレス障害)
不眠症 など
認知行動療法のやり方
認知行動療法は、一般的に医師やカウンセラーなどによって時間をかけて実施されます。週に一度、30分~50分程度の面談を、3カ月程度を目安におこなうのが一般的です。
治療は以下のような流れで進めていきます。自動思考とは、ネガティブな出来事に直面したときに、瞬間的に浮かぶ思考やイメージのことです。
・自分のストレスや問題を把握し、整理する
・問題がどのような状況で生じやすいか、どのような感情を引き起こしているのかを整理する
・自動思考を明確にし、自身の感情や行動のパターンを把握する
・自動思考における偏りやずれに自分で気づけるホームワークをおこなう
・問題解決に向けたホームワークをおこない、変えられるところから認知を修正していく
・面談でホームワークを振り返る、効果が見られない場合は治療目標やホームワークを見直す
・必要に応じて再発防止のフォローアップ面談をおこなう
認知行動療法では、対話によるカウンセリングだけでなく、ホームワークを設けて日常生活で検証をおこないます。日常生活の中で対処法を練習することで、認知の癖やずれを修正していきます。
治療は以下のような流れで進めていきます。自動思考とは、ネガティブな出来事に直面したときに、瞬間的に浮かぶ思考やイメージのことです。
・自分のストレスや問題を把握し、整理する
・問題がどのような状況で生じやすいか、どのような感情を引き起こしているのかを整理する
・自動思考を明確にし、自身の感情や行動のパターンを把握する
・自動思考における偏りやずれに自分で気づけるホームワークをおこなう
・問題解決に向けたホームワークをおこない、変えられるところから認知を修正していく
・面談でホームワークを振り返る、効果が見られない場合は治療目標やホームワークを見直す
・必要に応じて再発防止のフォローアップ面談をおこなう
認知行動療法では、対話によるカウンセリングだけでなく、ホームワークを設けて日常生活で検証をおこないます。日常生活の中で対処法を練習することで、認知の癖やずれを修正していきます。
自分でおこなう認知行動療法のやり方
認知行動療法は、基本的に医師やカウンセラーといった専門家と一緒におこなうものですが、自分自身で取り組むこともできます。
ここでは、自分でも取り組みやすい認知行動療法の一つ「セルフモニタリング」について紹介します。
ここでは、自分でも取り組みやすい認知行動療法の一つ「セルフモニタリング」について紹介します。
セルフモニタリング
セルフモニタリングは、自身の認知や行動を客観視できるようになることで、心の状態を整える心理療法です。自身の行動が社会的に適切かどうかを観察し、コントロールできるよう訓練していきます。一連のプロセスを習慣化することで、ストレスの軽減や望ましい行動変容が期待できます。
セルフモニタリングに活用できる技法には、以下のようなものが挙げられます。
セルフモニタリングに活用できる技法には、以下のようなものが挙げられます。
- セルフモニタリングに活用できる技法
週間活動記録表
コラム法(思考記録表)
週間活動記録表は、就寝・起床時間、食事の時間など一日の活動内容を記録していく行動療法です。1週間・1カ月など一定期間記録し振り返ることで、日々の行動が気分や体調に与える影響を客観視できます。自己理解ができることで対策が打てるようになり、体調・精神の安定につながっていきます。手帳やアプリなどでもできるため、比較的個人でも取り組みやすいものです。
コラム法(思考記録表)では、ネガティブな出来事に対して反射的に浮かんだ感情や考えを記録し、客観視することで偏った認知を整えていく心理療法です。自分を落ち込ませている出来事に関して、7個の項目で「感情」と「考え」を書き出して整理することで、出来事を多角的に捉え柔軟な思考を養います。
ただし、やり方や本人の心身の状態によっては症状が悪化する場合があります。自身で取り組む際には、主治医や専門家へ相談してからおこなうと安心です。
コラム法(思考記録表)では、ネガティブな出来事に対して反射的に浮かんだ感情や考えを記録し、客観視することで偏った認知を整えていく心理療法です。自分を落ち込ませている出来事に関して、7個の項目で「感情」と「考え」を書き出して整理することで、出来事を多角的に捉え柔軟な思考を養います。
ただし、やり方や本人の心身の状態によっては症状が悪化する場合があります。自身で取り組む際には、主治医や専門家へ相談してからおこなうと安心です。
就労移行支援事業所「ミラトレ」でも認知行動療法を採り入れています
認知行動療法は、もともとうつ病の治療法として発展してきましたが、そのほかの精神疾患や発達障害、睡眠障害などにも効果があることがわかり、広く用いられています。自分の認知(思考)の癖に気づき、バランスの取れた柔軟な考え方と行動ができるよう整えていくことで、ストレスの軽減や問題解決が期待できる心理療法です。
就労移行支援事業所「ミラトレ」では、認知行動療法の一つ「ソーシャルスキルトレーニング(SST)」を擬似就労という形で採り入れています。擬似就労では、ミラトレの事業所を一つの会社に見立て、総務部・広報部などいくつかの部署に分かれて実務に近い内容のトレーニングをおこなっています。グループワークを通じて対人関係におけるソーシャルスキルを高め、長くはたらくためのスキルを養います。
発達障害や難病の方で、就労における困りごとや不安のある場合は、お気軽に「ミラトレ」にご相談ください。
就労移行支援事業所「ミラトレ」では、認知行動療法の一つ「ソーシャルスキルトレーニング(SST)」を擬似就労という形で採り入れています。擬似就労では、ミラトレの事業所を一つの会社に見立て、総務部・広報部などいくつかの部署に分かれて実務に近い内容のトレーニングをおこなっています。グループワークを通じて対人関係におけるソーシャルスキルを高め、長くはたらくためのスキルを養います。
発達障害や難病の方で、就労における困りごとや不安のある場合は、お気軽に「ミラトレ」にご相談ください。

執筆 : ミラトレノート編集部
パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業ミラトレが運営しています。専門家の方にご協力いただきながら、就労移行支援について役立つ内容を発信しています。
アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3

アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3