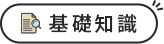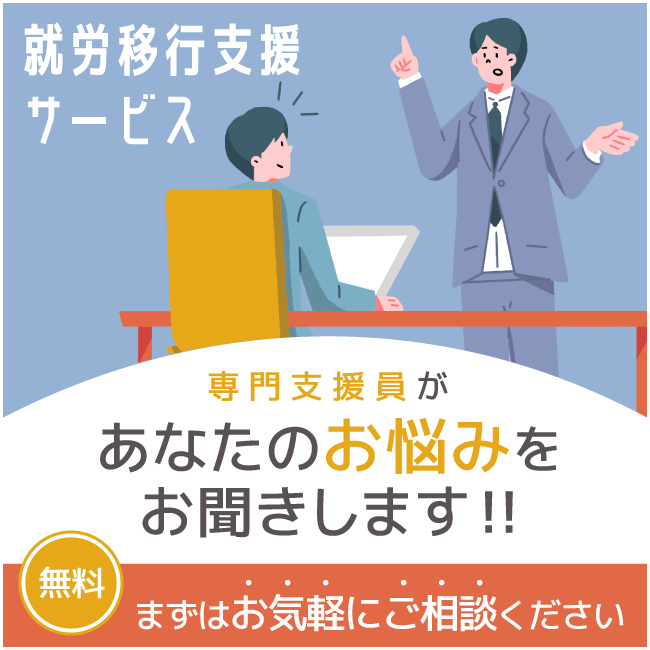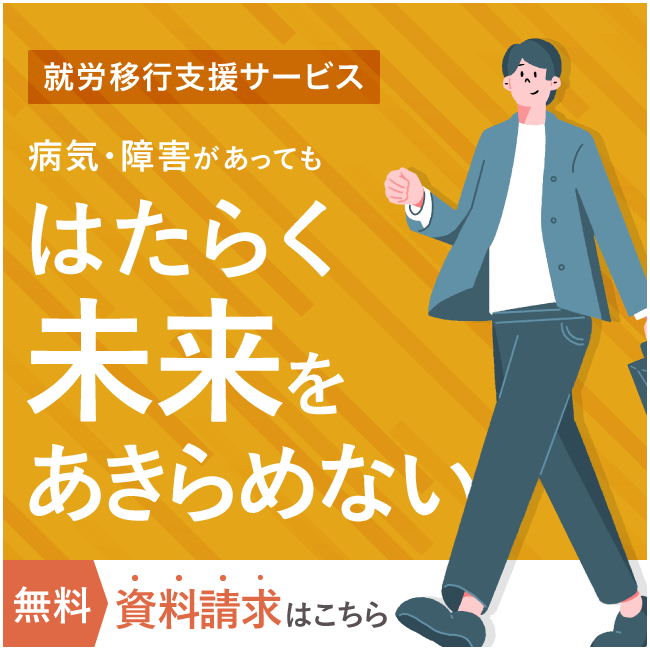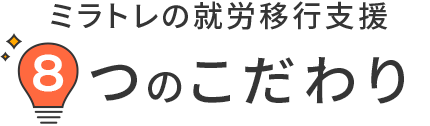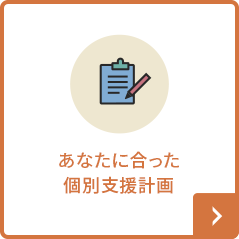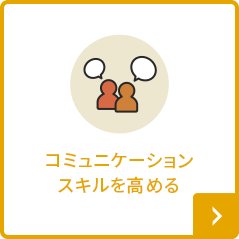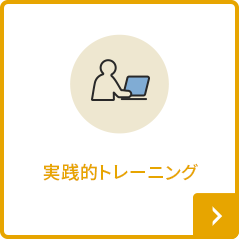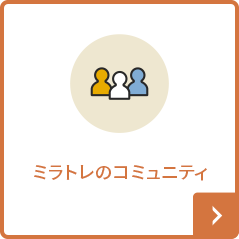ミラトレノート
就労移行支援の
 基礎
基礎 知識
知識


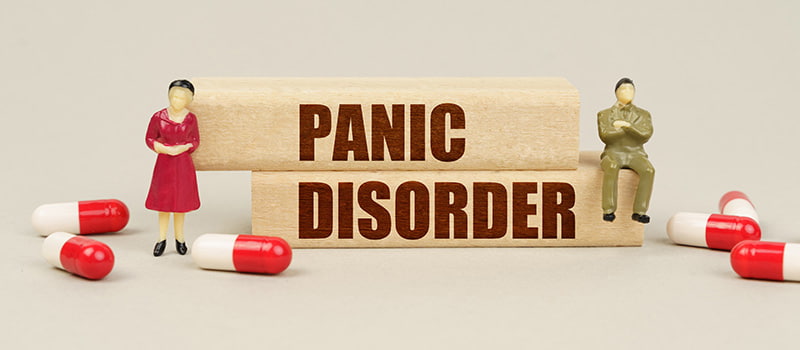
パニック障害である場合に、仕事をしていて「迷惑がかかっているのではないか」「クビになるのではないか」と不安を抱える声もよく聞かれます。今回は産業医科大学教授江口尚先生の解説のもと、パニック障害の基礎知識や仕事選びのポイント、長くはたらき続けるためのコツを紹介します。
目次
-
1.パニック障害の基礎知識
-
1-1.パニック障害の主な症状
-
1-2.パニック障害の要因
-
1-3.パニック障害の主な治療方法
-
2.生活するために活用したいサポート
-
3.パニック障害のある人へ周りの人が理解するべきこと
-
3-1.家族や周りの人ができるサポートについて教えてください
-
3-2.パニック障害の方に接する際の注意点や接し方のポイントはありますか?
-
4.パニック障害のある人が仕事を選ぶポイント
-
4-1.パニック障害の人が就職活動で大切にすべきことは何ですか?
-
4-2.パニック障害の人が比較的はたらきやすいのはどのような環境ですか?
-
4-3.パニック障害の人にとって注意が必要な仕事はありますか?
-
5.パニック障害のある人のはたらく形、仕事を続けるコツなどを解説
-
5-1.パニック障害の人が、長くはたらき続けるためのコツはありますか?
-
5-2.パニック障害の人が、はたらけなくなる状態を避けるためにはどうすればよいでしょう?
-
6.パニック障害のある人のはたらき方を考える
-
6-1.勤務時間に融通が効くか
-
6-2.作業場所を選択できるか
-
7.パニック障害のある人が実際に就職した事例
-
7-1.50代女性Lさんの場合
-
7-2.40代男性Mさんの場合
-
8.パニック障害の人もはたらきやすい環境を見つけよう
パニック障害の基礎知識
パニック障害とは、身体症状を伴った極めて強い不安や恐怖・不安などの精神症状が、発作的に生じる障害です。ある日突然、呼吸困難などの症状とともに、強い不安と恐怖が襲いかかります。「このまま死んでしまうのではないか」という恐怖感を抱くのも特徴です。
パニック障害は、体に病気のない健康な人が、動悸や呼吸困難、めまいなどの発作を突然起こしてしまう「不安障害」の一種です。「不安障害」は、過度に不安が生じることにより心と体にさまざまな不快な変化が起こるもので、社会生活に影響のある状態を指します。慢性的に不安な状態が続く場合や、特定の状況で発作的に不安が生じる場合など、不安障害にもいくつかの種類があります。
パニック障害は、体に病気のない健康な人が、動悸や呼吸困難、めまいなどの発作を突然起こしてしまう「不安障害」の一種です。「不安障害」は、過度に不安が生じることにより心と体にさまざまな不快な変化が起こるもので、社会生活に影響のある状態を指します。慢性的に不安な状態が続く場合や、特定の状況で発作的に不安が生じる場合など、不安障害にもいくつかの種類があります。
パニック障害の主な症状
パニック障害の症状は、以下のように人によってさまざまです。
- 動悸
- 発汗
- 息切れ
- 胸の痛み
- 吐き気
- めまい
- 寒気
- ほてり
- 何かが手を這うように感じるなどの異常感覚
- 自分が自分ではないように感じ
- 自分をコントロールできない感覚
- 死んでしまうのではないかという感覚・恐怖
上記の症状が突発的に起こり、数分以内にピークに達し、多くの場合は数分でおさまるのが特徴です。パニック障害の症状を「パニック発作」と呼びますが、これらのパニック発作を繰り返すと「パニック障害」と診断されます。
また、多くの人は「発作が起きたらどうしよう」と心配になりがちです。パニック発作を繰り返すうちに、発作を起こしていない時にも次の発作を恐れるようになります。これらは「予期不安」といい、パニック障害に多く見られる症状の一つです。不安のあまり家から出られない、仕事に行けないなどの社会生活に影響を及ぼすこともあります。
その他、その場で発作が起きたら逃げられないのではないか、助けが得られないのではないかと思える苦手な場所ができ、その場所や状況を避けるようになります。これを「広場恐怖」といいます。広場恐怖を伴わないパニック障害もありますが、多くの場合、広場恐怖がみられます。
また、多くの人は「発作が起きたらどうしよう」と心配になりがちです。パニック発作を繰り返すうちに、発作を起こしていない時にも次の発作を恐れるようになります。これらは「予期不安」といい、パニック障害に多く見られる症状の一つです。不安のあまり家から出られない、仕事に行けないなどの社会生活に影響を及ぼすこともあります。
その他、その場で発作が起きたら逃げられないのではないか、助けが得られないのではないかと思える苦手な場所ができ、その場所や状況を避けるようになります。これを「広場恐怖」といいます。広場恐怖を伴わないパニック障害もありますが、多くの場合、広場恐怖がみられます。
パニック障害の要因
パニック障害の要因は、いまだはっきりとわかっていません。強いストレスや幼少期の分離不安などによる親子関係、脳の伝達物質の動きなどが関係しているのではないかといわれています。
また、不安を感じやすい人がパニック障害になりやすいとも言われています。原因は人によってさまざまな場合が多いため、治療を進める上でも原因を取り除くという発想にはなりにくいようです。
また、不安を感じやすい人がパニック障害になりやすいとも言われています。原因は人によってさまざまな場合が多いため、治療を進める上でも原因を取り除くという発想にはなりにくいようです。
パニック障害の主な治療方法
パニック障害は、数分で症状が静まることから、発作が起きている状態を医師が確認するのは難しいでしょう。まず、身体的な病気がないか確認し、それらを除外した上で診断します。医師は、本人に寄り添いながら話を聞き、本人の気持ちを思い起こせるように話をなぞります。
パニック障害の主な治療方法は、患者教育、精神療法、薬物療法の3つです。患者教育は、患者自身が自分のことを理解するためにおこなう治療です。パニック障害とはどういうものなのか、自分に起こりうる症状や自身に障害があること、死ぬことはないということなどの認知を促します。薬を服用することへの不安がある場合は、薬による効果と副作用について把握してもらうことで、不安の軽減につなげます。家族や周りの方への理解を促し、身近な人に受け入れてもらうことも大切です。
精神療法では、主に認知行動療法や、ばく露療法が用いられます。認知行動療法を通して、自分の思考に偏りがあることに気づき、考え方を修正します。ばく露療法は、段階的に不安なものや苦手なものに少しずつ慣れていく方法です。不安を感じやすく、パニックに陥りやすい可能性のある状況に身を置き、少しずつ心と体を慣らしていきます。
薬物療法は、脳に作用する薬を服用する療法です。発作を起こしにくくする薬を継続的に服用する場合や、発作時にその症状を静めるために服用する場合があります。主治医の指導の下、自分に合った薬を選択しましょう。また、薬物療法に加えて、精神療法を併用することも重要です。薬によって発作が起こらなくなってきたら、少しずつ不安や苦手なものに挑戦していきます。
パニック障害の主な治療方法は、患者教育、精神療法、薬物療法の3つです。患者教育は、患者自身が自分のことを理解するためにおこなう治療です。パニック障害とはどういうものなのか、自分に起こりうる症状や自身に障害があること、死ぬことはないということなどの認知を促します。薬を服用することへの不安がある場合は、薬による効果と副作用について把握してもらうことで、不安の軽減につなげます。家族や周りの方への理解を促し、身近な人に受け入れてもらうことも大切です。
精神療法では、主に認知行動療法や、ばく露療法が用いられます。認知行動療法を通して、自分の思考に偏りがあることに気づき、考え方を修正します。ばく露療法は、段階的に不安なものや苦手なものに少しずつ慣れていく方法です。不安を感じやすく、パニックに陥りやすい可能性のある状況に身を置き、少しずつ心と体を慣らしていきます。
薬物療法は、脳に作用する薬を服用する療法です。発作を起こしにくくする薬を継続的に服用する場合や、発作時にその症状を静めるために服用する場合があります。主治医の指導の下、自分に合った薬を選択しましょう。また、薬物療法に加えて、精神療法を併用することも重要です。薬によって発作が起こらなくなってきたら、少しずつ不安や苦手なものに挑戦していきます。
生活するために活用したいサポート
パニック障害の方の生活を支えるためには、さまざまなサポートがあります。これらを上手に活用し、生活基盤を整えましょう。
職場の産業医や学校の精神科医、スクールカウンセラーに相談できます。勤務先が産業医を選任していない場合は、都道府県に設置されている産業保健総合支援センター(さんぽセンター)に相談するとよいでしょう。
職場の産業医や学校の精神科医、スクールカウンセラーに相談できます。勤務先が産業医を選任していない場合は、都道府県に設置されている産業保健総合支援センター(さんぽセンター)に相談するとよいでしょう。
- 医療費のサポート
・自立支援医療
精神科の治療のため、定期的・継続的に通院している場合、かかった医療費を補助してもらえる制度です - 暮らしと社会生活のサポート
・精神障害者保健福祉手帳
税金の優遇制度や交通機関の割引、公営住宅への優先入居など経済的・福祉的なサービスを利用することができます - 就労のサポート
・就労移行支援事業所
・ハローワーク
・地域障害者職業センター
・障害者就業・生活支援センター(なかぽつ) - さまざまな相談ごとのサポート
・保健所
└都道府県別の保健所一覧
・精神保健福祉センター
└全国精神保健福祉センター一覧
・病院の患者会や家族会
└みんなねっと
パニック障害のある人へ周りの人が理解するべきこと
パニック障害の方を支える家族や周りの人は、どのように本人に接するとよいのでしょうか。家族ができるサポートや職場の方に理解してほしいことについて、産業医科大学教授 江口尚先生に解説いただきます。

【監修者】
産業医科大学 産業生態科学研究所
産業精神保健学研究室 教授
江口 尚氏
【専門分野】
職場の心理社会的要因、治療と仕事の両立支援、障害者や中小企業の産業保健
家族や周りの人ができるサポートについて教えてください
家族や周りの方は、パニック障害であることを否定したり、簡単に「大変だね」と言わないようにしていただきたいです。本人の辛さは、周りの方であろうとも理解できないこともあるでしょう。基本的には、寄り添う姿勢でサポートいただければと考えます。決して本人の辛さやパニック障害の症状を軽んじないでいただきたいです。
しかし、常に本人と一緒にいるのは現実的ではありません。適度な距離感も必要です。適度な距離で見守ってくれていて、自分のことをわかってくれる存在がいることは安心につながります。パニック発作を起こしたときに、薬を飲むよう伝えたり、落ち着くために安心させるスキンシップができる関係性であれば、そのようなコミュニケーションも有効でしょう。そのためにも、家族は受診に同行し、主治医からの説明を受けることも大切です。
しかし、常に本人と一緒にいるのは現実的ではありません。適度な距離感も必要です。適度な距離で見守ってくれていて、自分のことをわかってくれる存在がいることは安心につながります。パニック発作を起こしたときに、薬を飲むよう伝えたり、落ち着くために安心させるスキンシップができる関係性であれば、そのようなコミュニケーションも有効でしょう。そのためにも、家族は受診に同行し、主治医からの説明を受けることも大切です。
パニック障害の方に接する際の注意点や接し方のポイントはありますか?
パニック障害の症状の辛さは、本人にしかわからない点が多いです。実際、話を聞いているだけでは理解できないこともありますが、決して本人の主張を大げさだと軽んじないことです。本人の状況や辛さを十分に聞き取り、本人の話を信じてあげましょう。その上で、発作が出ていないときには通常通り接してあげてください。
パニック障害のある人が仕事を選らぶポイント
パニック障害の方が就職する際、仕事を選ぶときのポイントはあるのでしょうか。就職活動をする上で大切にすべきことなど、江口先生に解説いただきます。
パニック障害の人が就職活動で大切にすべきことは何ですか?
パニック障害の方が就職を目指す場合、患者教育や精神療法を通して、発作時のコントロールができるようになっていることが望ましいです。もし、発作時のコントロールが不十分なまま就職し、就労中に発作を起こした場合、本人も企業も戸惑いが大きいでしょう。まずはコントロールが可能になってから就職活動を進めた方がよいと考えます。
発作時のコントロールができている場合、安心して障害を伝えられる環境が望ましいと思います。パニック障害であることを理解してもらい、発作が起きても慌てずに本人の対応を見守ってくれる環境があれば安心です。一時的に休憩することを理解し認めてくれたり、一人になれる場所があり薬を飲んだり落ち着く時間が取れたりすることが、安心してはたらくことにもつながるでしょう。
発作時のコントロールができている場合、安心して障害を伝えられる環境が望ましいと思います。パニック障害であることを理解してもらい、発作が起きても慌てずに本人の対応を見守ってくれる環境があれば安心です。一時的に休憩することを理解し認めてくれたり、一人になれる場所があり薬を飲んだり落ち着く時間が取れたりすることが、安心してはたらくことにもつながるでしょう。
パニック障害の人が比較的はたらきやすいのはどのような環境ですか?
パニック障害は、加齢とともに症状は少しずつ落ち着くことが多いといわれています。
しばらく症状が落ち着いているけれど、季節や天気によって発作が起きやすくなる方や、過重労働や睡眠不足が続くと発作が起こりやすい方などもいます。
本人が安心してはたらけ、心身にストレスがかからない環境がはたらきやすいといえそうです。発作を誘発する原因は一人ひとり違うため一概には言えませんが、疲れからコントロールがしにくくなり、発作を起こすこともあります。発作とどのように付き合っていくか、工夫しながら向き合える環境が望ましいでしょう。自分のペースで仕事ができ、いつ発作が出てもこの環境なら大丈夫と思えれば、予期不安にもつながりにくいといえます。
しばらく症状が落ち着いているけれど、季節や天気によって発作が起きやすくなる方や、過重労働や睡眠不足が続くと発作が起こりやすい方などもいます。
本人が安心してはたらけ、心身にストレスがかからない環境がはたらきやすいといえそうです。発作を誘発する原因は一人ひとり違うため一概には言えませんが、疲れからコントロールがしにくくなり、発作を起こすこともあります。発作とどのように付き合っていくか、工夫しながら向き合える環境が望ましいでしょう。自分のペースで仕事ができ、いつ発作が出てもこの環境なら大丈夫と思えれば、予期不安にもつながりにくいといえます。
パニック障害の人にとって注意が必要な仕事はありますか?
発作が起こったときに離席することが難しい環境や、仕事のスケジュールをコントロールしにくい環境は注意が必要です。そういった環境調整が難しいほど、発作がいつ起こるかわからないパニック障害の方は辛さを感じるでしょう。「この環境で発作を起こしたらどうしよう」「逃げ場がない」などの予期不安にもつながりかねません。
また、車の運転を伴う仕事も注意が必要です。発作を抑える薬を服用していても、安心とは言い切れないところがあります。車を運転できるかどうかは、個人差があるので、必ず主治医に相談しましょう。
また、車の運転を伴う仕事も注意が必要です。発作を抑える薬を服用していても、安心とは言い切れないところがあります。車を運転できるかどうかは、個人差があるので、必ず主治医に相談しましょう。
パニック障害のある人のはたらく形、仕事を続けるコツなどを解説
就職自体がゴールではありません。本当に重要なのは、就職後に長くはたらき続けることです。パニック障害の方が仕事を続けるコツについて、江口先生に解説いただきます。
パニック障害の人が、長くはたらき続けるためのコツはありますか?
長期就労を目指すパニック障害の方は、まずはしっかりと通院することが大切です。通院しながら、主治医から体調に応じたアドバイスをもらいましょう。。休職が必要な場合には、復職のタイミングは主治医と十分に相談することが重要です。
職場においては、自分には通院が必要であることをあらかじめ伝えましょう。そして、安心して仕事ができる環境を自ら作る努力もしていただきたいです。自分でも工夫できることを見つけたり、仕事のスケジュールの立て方、避けてほしい業務などを、上司へ相談しておくとよいでしょう。また、発作が起こった際に上司や同僚にはどうしてほしいかも伝えるとよいと思います。救急車は呼ばなくてよいことや、薬を飲んで休憩すれば落ち着くことなどをあらかじめ伝えておけば、双方が安心でき長期就労にもつながるでしょう。
職場においては、自分には通院が必要であることをあらかじめ伝えましょう。そして、安心して仕事ができる環境を自ら作る努力もしていただきたいです。自分でも工夫できることを見つけたり、仕事のスケジュールの立て方、避けてほしい業務などを、上司へ相談しておくとよいでしょう。また、発作が起こった際に上司や同僚にはどうしてほしいかも伝えるとよいと思います。救急車は呼ばなくてよいことや、薬を飲んで休憩すれば落ち着くことなどをあらかじめ伝えておけば、双方が安心でき長期就労にもつながるでしょう。
パニック障害の人が、はたらけなくなる状態を避けるためにはどうすればよいでしょう?
予期不安が強くなりすぎて、薬を服用しても不安が改善しにくく、外出もままならないような状態になってしまうことも考えられます。そのような場合は、無理せず休職を選択しましょう。発作の頻度が増えたり、頻繁に勤怠が乱れたりしたら要注意です。迷わず主治医に相談してください。
パニック障害は、基本的には服薬すれば安定すると考えられているため、仕事の能力が落ちることはありません。休職して一度症状を安定させてから、改めて仕事を再開してもよいと考えます。
はたらけなくなる状態を避けるためには、体調に違和感を覚えたら誰かに相談することです。また、不安への対処方法を身につけることも有効でしょう。セルフケアのスキルが身につけられると、不安にどう対処したらよいかがわかってきます。呼吸を整えるリラクゼーション法なども有効でしょう。
そして、頑張りすぎないことも大切です。仕事においてはどこまで頑張ってよいかの判断が難しい場面もありますが、トライ・アンド・エラーを繰り返しながら、職場と一緒に探っていけるとよいと思います。
パニック障害は、基本的には服薬すれば安定すると考えられているため、仕事の能力が落ちることはありません。休職して一度症状を安定させてから、改めて仕事を再開してもよいと考えます。
はたらけなくなる状態を避けるためには、体調に違和感を覚えたら誰かに相談することです。また、不安への対処方法を身につけることも有効でしょう。セルフケアのスキルが身につけられると、不安にどう対処したらよいかがわかってきます。呼吸を整えるリラクゼーション法なども有効でしょう。
そして、頑張りすぎないことも大切です。仕事においてはどこまで頑張ってよいかの判断が難しい場面もありますが、トライ・アンド・エラーを繰り返しながら、職場と一緒に探っていけるとよいと思います。
パニック障害のある人のはたらき方を考える
パニック障害のある人が仕事を探すとき、どのようなことを考慮するとよいのでしょうか。転職サイトや求人サイトなどを見るときの参考にしたいポイントを2つ紹介します。
通勤時間に融通が効くか
通勤時間を調整できるかも確認したいポイントです。人混みで発作を起こしやすい場合は、「満員電車を避けた時間帯に通勤できる」「電車ではなく、徒歩で通勤できる場所を選ぶ」など、通勤手段も考えるとよいでしょう。
作業場所を選択できるか
パニック障害の場合、人に囲まれた環境や、すぐにその場から離れられない環境で不安を感じやすい人もいるでしょう。席を端にしてもらったり、扉の近くにしてもらったりして、要因となりやすい環境を避けることも大切です。
パニック障害のある人が実際に就職した事例
パニック障害の人が、実際にミラトレの就労移行支援を通して就職した事例を2つご紹介します。
50代女性Lさんの場合
50代女性Lさんは、神経性疲労疼痛症候群を発症したことで仕事を続けることが難しくなり、退職した経緯がありました。また、精神面の不調としてパニック障害とうつ病があるとも診断されていました。
職歴に10年ほどの空白期間があったLさんでしたが、ミラトレの就労移行支援をインターネットで見つけ、通所を開始。途中、自身の健康状態に合わせて活動時間を変更しながら、無理のないように通所を続けました。
トレーニングを繰り返す中で課題が見つかったときには、支援員の声掛けや自身の気持ち・体調の記録を通して、徐々に行動を起こしたり、納得できたりするようになりました。
週5日のフルタイム通所が安定してきた頃に初めて「障害者雇用枠」で就職活動を開始し、通所から1年11カ月が経過した頃に金融関係の企業から内定を受けました。現在は体調も整って正規雇用に切り替わり、フルタイムではたらいているそうです。
職歴に10年ほどの空白期間があったLさんでしたが、ミラトレの就労移行支援をインターネットで見つけ、通所を開始。途中、自身の健康状態に合わせて活動時間を変更しながら、無理のないように通所を続けました。
トレーニングを繰り返す中で課題が見つかったときには、支援員の声掛けや自身の気持ち・体調の記録を通して、徐々に行動を起こしたり、納得できたりするようになりました。
週5日のフルタイム通所が安定してきた頃に初めて「障害者雇用枠」で就職活動を開始し、通所から1年11カ月が経過した頃に金融関係の企業から内定を受けました。現在は体調も整って正規雇用に切り替わり、フルタイムではたらいているそうです。
40代男性Mさんの場合
40代男性Mさんは、前職の業務量増加によるストレスから、パニック障害とうつ病を発症しました。退職後の数年間はひきこもっていましたが、症状が落ち着いてきた頃にミラトレの就労移行支援と出会いました。
前職の経験を生かすため、パソコン関連のプログラムに重点をおきつつも、興味の幅を広げられるようさまざまなプログラムに挑戦しました。Mさんにはこだわりが強く完璧主義な一面が見受けられましたが、声掛けや利用者同士でのグループワークを通して、コミュニケーション面が大きく変化していったといいます。
週5日の安定した通所ができ、就職へのスキルも備わっていたことから、通所開始から10カ月後に、特例子会社の事務職として内定を得ることができました。採用後は「あらかじめ業務量を伝えてほしい」との配慮を求めながら、体調も勤務も安定して過ごせているそうです。
前職の経験を生かすため、パソコン関連のプログラムに重点をおきつつも、興味の幅を広げられるようさまざまなプログラムに挑戦しました。Mさんにはこだわりが強く完璧主義な一面が見受けられましたが、声掛けや利用者同士でのグループワークを通して、コミュニケーション面が大きく変化していったといいます。
週5日の安定した通所ができ、就職へのスキルも備わっていたことから、通所開始から10カ月後に、特例子会社の事務職として内定を得ることができました。採用後は「あらかじめ業務量を伝えてほしい」との配慮を求めながら、体調も勤務も安定して過ごせているそうです。
パニック障害の人もはたらきやすい環境を見つけよう
パニック障害の方が就職し、長くはたらくためのコツを紹介しました。パニック障害の人のなかには、「迷惑がかかるのではないか」「クビになってしまったらどうしよう」と悩む人もいるでしょう。長くはたらくためには、自己理解や障害受容など、まずは自分を知ることが大切です。一人ではどうしたらよいかわからないときは、精神科や心療内科といった医療機関、就労移行支援事業所などの外部サービスを利用し、サポートを受けるとよいでしょう。

執筆 : ミラトレノート編集部
パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業ミラトレが運営しています。専門家の方にご協力いただきながら、就労移行支援について役立つ内容を発信しています。
アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3

アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3