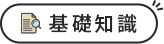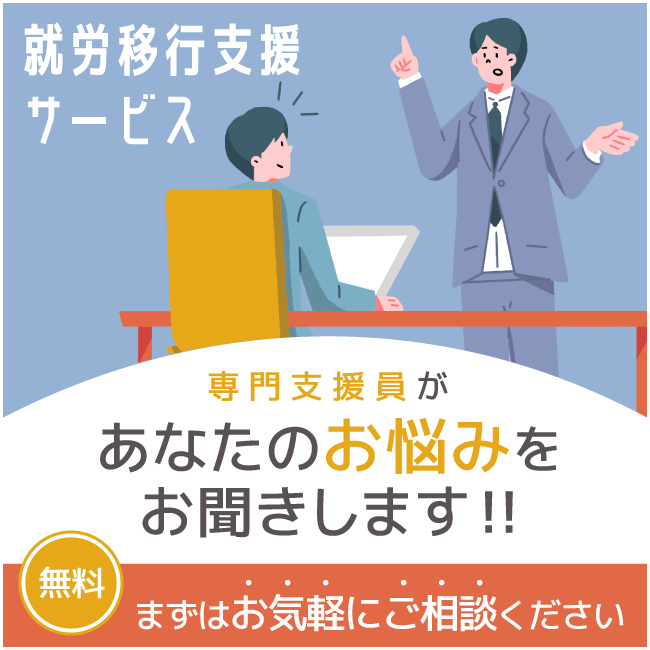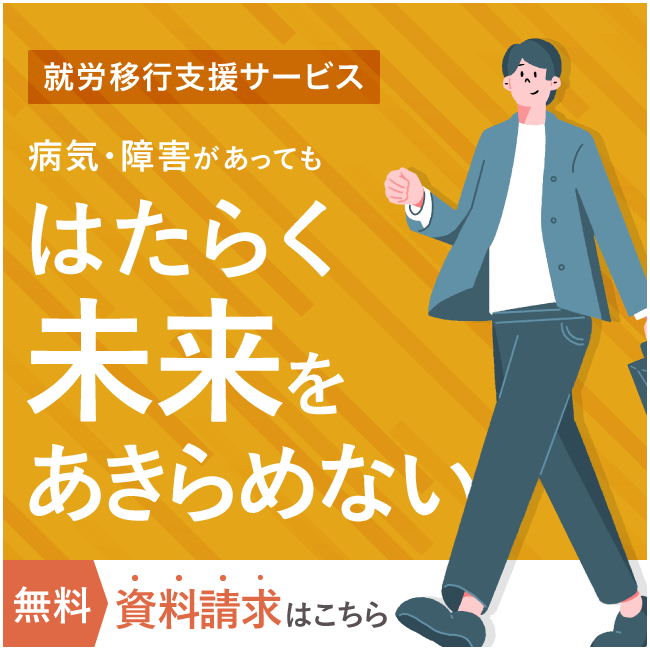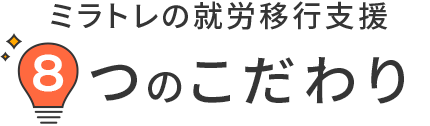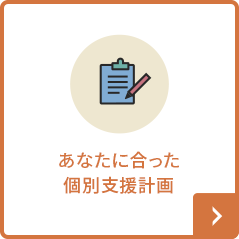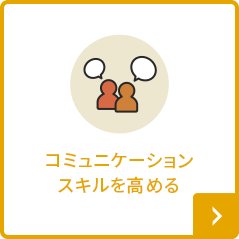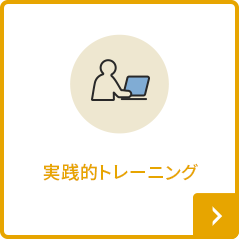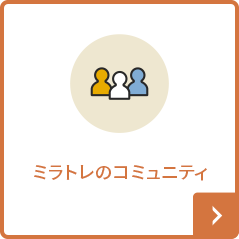ミラトレノート
就労移行支援の
 基礎
基礎 知識
知識



障害のある人のなかには、「企業に勤めることは難しいけれど、はたらく喜びを実感しながら生活したい」「社会の一員として生産活動に参加したい」という人もいるでしょう。そのような思いに寄り添い、はたらく場を提供する福祉サービスが就労継続支援B型です。今回は、就労継続支援B型の利用方法や事業所の選び方などを具体的に紹介します。就労継続支援A型や就労移行支援との違いなど、利用前に知っておきたい基礎知識についても解説します。
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型とは、障害や難病のある人にはたらく場を提供する福祉サービスの一つです。障害や体力などの理由で一般就労が難しい人も、事業所で軽作業などの生産活動をおこない、その対価として工賃を受け取れます。
障害の特性や体調に応じたサポートを受けながら、無理のないペースではたらけることが大きなメリットです。スタッフから、はたらくための知識やスキル、マナーを学べるほか、社会生活の支援も受けられます。就労継続支援にはB型のほかにA型もありますが、その違いは後ほど解説します。
障害の特性や体調に応じたサポートを受けながら、無理のないペースではたらけることが大きなメリットです。スタッフから、はたらくための知識やスキル、マナーを学べるほか、社会生活の支援も受けられます。就労継続支援にはB型のほかにA型もありますが、その違いは後ほど解説します。
就労継続支援B型の利用方法
ここからは、就労継続支援B型の利用方法やサービス内容について紹介します。
就労継続支援B型の利用対象者
就労継続支援B型を利用できるのは、障害や難病があり、かつ下記のいずれかに当てはまる人です。ただし利用条件は自治体によって異なるため、お住いの市区町村で確認してください。
- (1)就労経験はあるが、年齢や体力の面で、企業などではたらくことが難しくなった人
- (2)50歳以上の人、または障害基礎年金1級の受給者
- (3) (1)や(2)には当てはまらないが、就労アセスメント(※)によって就労面の課題があるとされた人
- (4)事業所ではたらいているが、その事業所での就労に必要な知識や能力を向上するために、一時的な支援が必要な人
(※)就労アセスメントとは、「障害と折り合いながらはたらきたい」という人の能力やニーズを把握し、その人が適切な福祉サービスを利用できるようサポートする制度です。主に就労移行支援事業所などでおこなわれており、2025年10月から「就労選択支援制度」がスタートすると、就労継続支援B型の利用希望者は原則的にアセスメントを受けられます。
※参考:厚生労働省『就労系障害福祉サービスの概要』
※参考:厚生労働省『就労系障害福祉サービスの概要』
就労継続支援B型の利用料金
就労継続支援B型は、9割以上の人が無料で利用しています。しかし、前年度の世帯収入などによって料金が発生するため、以下の表を参照してください。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 ※1 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯 (所得割16万円 ※2 未満)※3 |
9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 3万7,200円 |
(※1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象
(※2)収入がおおむね670万円以下の世帯(18歳以上の場合は、障害のある当事者とその配偶者)が対象
(※3)20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、一般2となります
※出典:厚生労働省『障害者の利用者負担』
(※2)収入がおおむね670万円以下の世帯(18歳以上の場合は、障害のある当事者とその配偶者)が対象
(※3)20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、一般2となります
※出典:厚生労働省『障害者の利用者負担』
就労継続支援B型の仕事内容
就労継続支援B型の事業所では、どのような仕事をおこなえるのでしょうか。利用者を対象とした2022年のアンケート結果から、上位の回答を紹介します。
- 就労継続支援B型の仕事
1位 その他の軽作業(14.1%)
2位 内職(10.5%)
3位 その他(6.4%)
4位 検査・検品(6.1%)
5位 建物のなかのそうじ(5.4%)
6位 その他 ものづくり(5.2%)
7位 草取り・雪かき・配達(5.1%)
8位 部品・機械組立(4.5%)
9位 施設外就労(4.3%)
10位 梱包・箱詰め(4.2%)
シール貼付や値札付けなどの軽作業、パソコンを使った設計・プログラミング、農業など、作業内容は事業所によりさまざまです。そのため、どのような作業なら無理なく続けられそうか、事前に検討しておくと良いでしょう。
※出典:厚生労働省『就労系障害福祉サービスの利用者の支援ニーズ等の実態把握等に関する調査』
※出典:厚生労働省『就労系障害福祉サービスの利用者の支援ニーズ等の実態把握等に関する調査』
就労継続支援B型の利用期間・日数
就労継続支援B型の利用期間に制限はありません。他の就労福祉サービスに切り替えたり、企業ではたらいたりするために利用を中断した後も再開できます。
はたらく日数や時間は事業所によって異なります。公益財団法人が2018年に公表したレポートによると、就労継続支援B型における一週間の平均就労時間は22時間という結果でした。この数字はあくまでも平均値であり、「利用は週2日から」を原則としている事業所もあれば、「週1日、短時間からの利用も可」という事業所もあります。ほとんどの場合、一人ひとりの希望に応じて就労の日数や時間を調整してもらえるため、無理のないペースではたらけるでしょう。
※出典:日本財団『就労継続支援B型事業所調査報告書追加資料 工賃に関するレポート』
はたらく日数や時間は事業所によって異なります。公益財団法人が2018年に公表したレポートによると、就労継続支援B型における一週間の平均就労時間は22時間という結果でした。この数字はあくまでも平均値であり、「利用は週2日から」を原則としている事業所もあれば、「週1日、短時間からの利用も可」という事業所もあります。ほとんどの場合、一人ひとりの希望に応じて就労の日数や時間を調整してもらえるため、無理のないペースではたらけるでしょう。
※出典:日本財団『就労継続支援B型事業所調査報告書追加資料 工賃に関するレポート』
就労継続支援B型の工賃
就労継続支援B型は雇用契約を結ばない労働のため最低賃金は保障されていませんが、工賃は上昇傾向にあります。2022年度、ひと月あたりの平均工賃は1万7,031円、1時間あたり243円でした。事業所や仕事内容によって工賃が異なるため、事業所選びの際に確認しましょう。
※出典:厚生労働省『障害者の就労支援対策の状況』
※出典:厚生労働省『障害者の就労支援対策の状況』
自分に合った事業所の探し方と選び方
就労継続支援B型の事業所を探すには、主に以下のような方法があります。
- 自分に合った就労継続支援B型を見つけるための5つの探し方
●市区町村の福祉窓口に相談する
●相談支援事業所に相談する
●インターネットで検索する
●ハローワークに相談する
●障害者向けの求人検索サイト・求人情報誌で探す
また、事業所を選ぶ際は、主に以下のポイントをチェックしましょう。
- 事業所を選ぶ際の8つのチェックポイント
▢自分の障害が支援対象になっているか
▢定員に空きがあるか
▢作業内容が自分の障害特性や希望に合っているか
▢利用の日数や時間、工賃はどのように定められているか
▢雰囲気は自分に合いそうか
▢自宅から通いやすいか
▢設備に不便を感じないか
▢支援の考え方が自分に合っているか
さまざまな障害の人を幅広く受け入れている事業所もあれば、特定の障害に特化している事業所もあります。事業所選びの際は、自分の障害が支援対象となっているか確認しましょう。就労場所は事業所内に限らず、他の企業におもむく施設外就労や在宅勤務、屋外作業などさまざまです。活動内容や雰囲気も異なるため、「屋外で他の利用者と一緒に体を動かしたい」「屋内で黙々と手仕事に取り組みたい」など、自分の希望に合った事業所を選びましょう。
通所までの流れ
就労継続支援B型を利用するには、次のステップを踏む必要があります。
- 通所までの6つのステップ
●主治医への相談
▼
●事業所への問い合わせ・資料請求
▼
●事業所の見学・体験利用
▼
●障害福祉サービス受給者証(受給者証)の申請
▼
●事業所との利用契約
▼
●利用開始
就労継続支援B型を利用しても問題ないか主治医の判断を仰いだ上で、事業所を探します。利用したい事業所が見つかったら、問い合わせや資料請求をおこなって、自分の障害特性や希望に合っているかを確認しましょう。多くの事業所では見学や体験利用を実施しているので、自宅からの交通アクセスや作業内容、雰囲気を知るためにも、直接訪問してみることをおすすめします。
利用には受給者証の申請と発行が必要です。申請にあたり、障害者手帳は必ずしも必要ではありません。医師の診断書や自立支援医療受給者証など、障害があることを証明する書類を用意して、市区町村の福祉窓口で受給者証を申請します。
申請後、「サービス等利用計画書」を提出する必要があります。自分で作成することが難しい場合は、家族や相談支援事業者に依頼しましょう。受給者証が発行され、事業所で契約を結ぶと、通所を開始できます。
利用には受給者証の申請と発行が必要です。申請にあたり、障害者手帳は必ずしも必要ではありません。医師の診断書や自立支援医療受給者証など、障害があることを証明する書類を用意して、市区町村の福祉窓口で受給者証を申請します。
申請後、「サービス等利用計画書」を提出する必要があります。自分で作成することが難しい場合は、家族や相談支援事業者に依頼しましょう。受給者証が発行され、事業所で契約を結ぶと、通所を開始できます。
就労継続支援A型や就労移行支援との違いは?
就労系の障害福祉サービスには、就労継続支援B型だけでなく、就労継続支援A型や就労移行支援などがあります。それぞれの違いを表にまとめました。
| サービス | 就労継続支援B型 | 就労継続支援A型 | 就労移行支援 |
|---|---|---|---|
| 対象 | 雇用契約の下ではたらくことが難しい人 | 一般企業ではたらくことは難しいが、一定の支援があれば雇用契約の下ではたらける人 | 一般企業ではたらきたい人 |
| 対象者の年齢 | 制限なし | 原則として18歳以上65歳未満 | 原則として18歳以上65歳未満 |
| 書類選考・面接選考 | なし | あり | なし |
| (事業所との)雇用契約 | なし | あり | なし |
| 報酬 | 工賃が支払われるが、最低賃金の保障なし | 最低賃金以上の給料が保障される | 報酬なし |
| 利用期間 | 制限なし | 制限なし | 原則として最長2年間 |
就労継続支援が「はたらく機会を提供する」サービスであるのに対し、就労移行支援は「企業などではたらくための準備をサポートする」サービスです。就労移行支援事業所は就労ではなく訓練の場なので、報酬は発生しません。
就労継続支援A型は、B型と違い雇用契約下の就労です。人によっては就労条件や仕事内容に負担を感じる可能性があるでしょう。その場合、A型からB型へ切り替えるという選択肢もあります。
※関連記事:『就労継続支援A型とは?利用方法や他サービスとの違いについて』
就労継続支援A型は、B型と違い雇用契約下の就労です。人によっては就労条件や仕事内容に負担を感じる可能性があるでしょう。その場合、A型からB型へ切り替えるという選択肢もあります。
※関連記事:『就労継続支援A型とは?利用方法や他サービスとの違いについて』
就労継続支援B型を有効的に活用するには
就労系の障害福祉サービスを選ぶ前に、「自分に合うはたらき方」について考えてみることをおすすめします。障害の特性や体力に考慮しながら、無理なくはたらける仕事内容や日数を具体的にイメージしてみましょう。その上で医師や障害福祉専門家、家族に相談すると、適切な障害福祉サービスを選びやすくなります。
事業所選びも大切です。「得意なことを活かしたい」「仲間と楽しく過ごしたい」「パソコンスキルを身につけたい」など、利用の目的は人それぞれでしょう。見学や体験利用を通して、自分の障害特性や希望に合った事業所を見つけてください。
事業所選びも大切です。「得意なことを活かしたい」「仲間と楽しく過ごしたい」「パソコンスキルを身につけたい」など、利用の目的は人それぞれでしょう。見学や体験利用を通して、自分の障害特性や希望に合った事業所を見つけてください。

執筆 : ミラトレノート編集部
パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業ミラトレが運営しています。専門家の方にご協力いただきながら、就労移行支援について役立つ内容を発信しています。
アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3

アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3