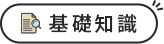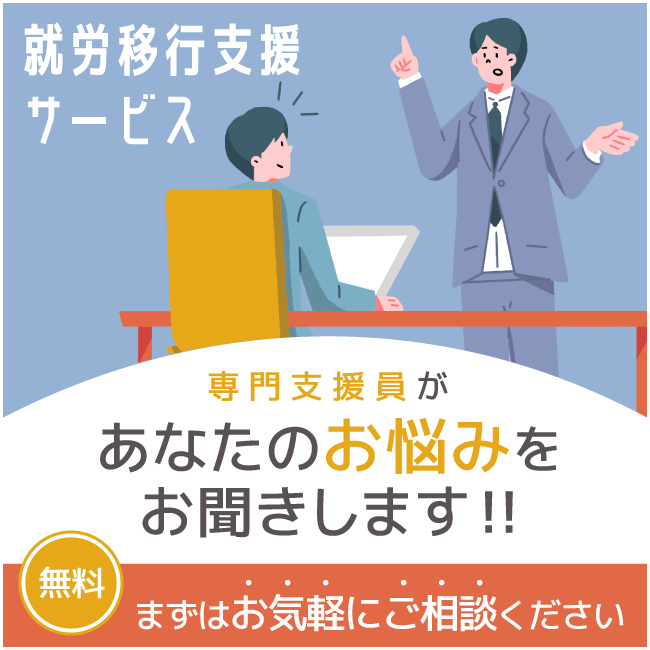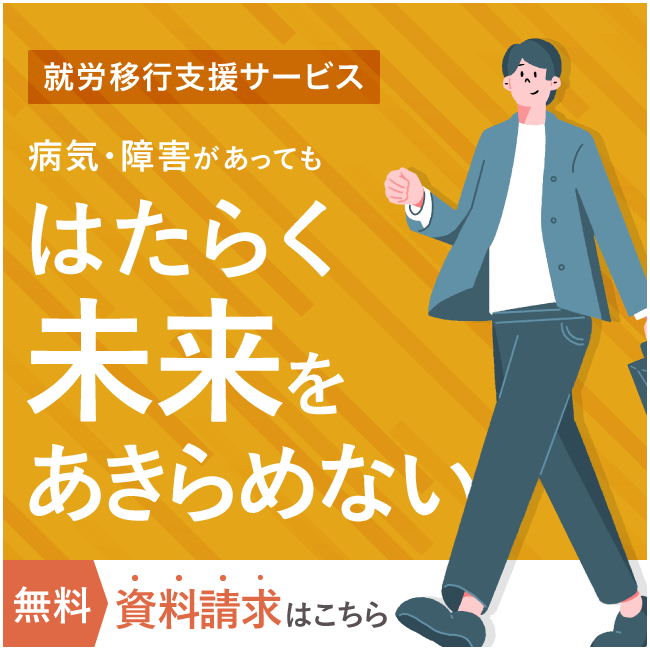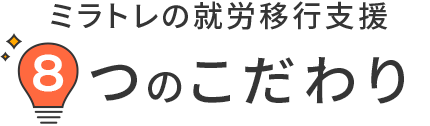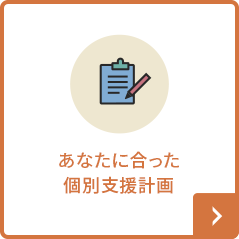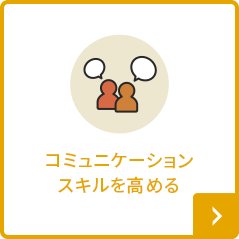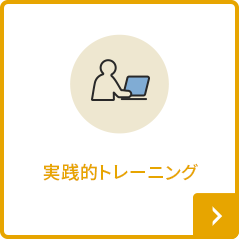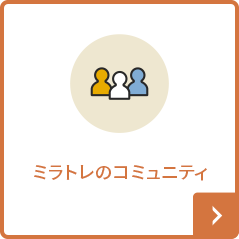ミラトレノート
就労移行支援の
 基礎
基礎 知識
知識



就労移行支援を利用することは、人によって向き不向きがあります。就労移行支援の利用を検討している人のなかには、「自分は就労移行支援に向いているのだろうか?」と悩んでいる人もいるのではないでしょうか。就労移行支援は、一般企業への就職を希望する障害や難病のある人を対象に、就労に必要な知識・スキルの習得をサポートする障害福祉サービスです。就職を保証するサービスではなく、利用者にも心構えが求められます。就労移行支援を利用する目的をしっかりと理解した上で、自分に向いているか向いていないかを判断して利用を検討しましょう。この記事では、就労移行支援についての基礎知識と、就労移行支援の利用に向いている人・向いていない人の特徴について詳しく解説します。
目次
-
1.就労移行支援とは
-
2.就労移行支援の対象者・料金・期間
-
2-1.就労移行支援の対象者
-
2-2.就労移行支援の利用料金
-
2-3.就労移行支援の利用期間
-
3.就労移行支援で取り組めること
-
4.就労移行支援に向いている人向いていない人
-
4-1.就労移行支援の利用に向いている人の特徴
-
4-1-1.障害や難病があり、就職活動に不安がある人
-
4-1-2.就職活動に苦戦している人
-
4-1-3.就職に意欲があり、主体性をもった人
-
4-1-4.一般雇用・障害者雇用の形態にこだわりがない人
-
4-2.就労移行支援に向いていない人の特徴
-
5.就労移行支援事業所の探し方
-
6.就労移行支援「ミラトレ」で自分に向いている仕事を見つけよう
就労移行支援とは
就労移行支援とは、障害者総合支援法が定める障害福祉サービスのひとつです。一般企業への就職を希望する障害や難病のある人が、就労に必要な知識・スキルの習得や就職活動のサポートを受けられます。
最長2年間の利用期間のなかで、就労移行支援事業所に通いながら一般企業への就労を目指します。就職後も、職場への定着を目的にカウンセリングなどの支援を継続して受けられるのが特徴です。
※関連記事:『就労移行支援とは』
最長2年間の利用期間のなかで、就労移行支援事業所に通いながら一般企業への就労を目指します。就職後も、職場への定着を目的にカウンセリングなどの支援を継続して受けられるのが特徴です。
※関連記事:『就労移行支援とは』
就労移行支援の対象者・料金・期間
就労移行支援を利用できる対象者や利用料金、期間について以下で紹介します。
就労移行支援の対象者
就労移行支援は誰でも利用できるわけではありません。利用できる対象者は、下記の条件をすべて満たしている人です。
- 条件
・精神障害・発達障害・知的障害・身体障害・難病(障害者総合支援法の対象疾病)のある人
・サービス利用開始時点で65歳未満の人
・一般企業への就職を希望する人
就労移行支援を利用するためには、上記の条件を満たした上で、市区町村から障害福祉サービス受給者証の交付を受ける必要があります。
障害者手帳がなくても医師の診断・定期的な通院があれば申請可能な場合や、例外的に対象となるケースもあるため、希望する事業所の対象者を確認しましょう。就労移行支援の対象者について詳しく知りたい人は、以下の記事もご覧ください。
※関連記事:『就労移行支援の対象者』
障害者手帳がなくても医師の診断・定期的な通院があれば申請可能な場合や、例外的に対象となるケースもあるため、希望する事業所の対象者を確認しましょう。就労移行支援の対象者について詳しく知りたい人は、以下の記事もご覧ください。
※関連記事:『就労移行支援の対象者』
就労移行支援の利用料金
就労移行支援の利用料金は厚生労働省によって定められており、前年の収入によって負担額の上限が決められています。収入は、18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得となります。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(※1) | 0円 |
| 一般1 |
市町村民税課税世帯 (所得割16万円未満:※2) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム等利用者を除きます。(※3) |
9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 3万7,200円 |
※1 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入がおおむね300万円以下の世帯が対象となります。 ※2 収入がおおむね600万円以下の世帯が対象になります。 ※3 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、「一般2」となります。 ※関連記事:『就労移行支援の利用料金』
「考え方が複雑で周囲の刺激に過敏」という特性は、裏を返せば「思慮深く、周囲の状況や人の感情の変化に気付ける」という「強み」と捉えられます。そのため、職場内でのトラブルの芽にもいち早く気づき、速やかに対処行動ができたり、人の悩みや不安に共感して寄り添えたりと、職場での調整役ができる人も少なくありません。
また、繊細さは、芸術や創作の分野でも力を発揮しやすく、外部からの些細な刺激が強烈なインスピレーションとなり表現に活かせるケースもあります。
このように、自身の特性を強みと捉え、視点を変えることにより、ストレスや不安が軽減できる可能性があります。
また、繊細さは、芸術や創作の分野でも力を発揮しやすく、外部からの些細な刺激が強烈なインスピレーションとなり表現に活かせるケースもあります。
このように、自身の特性を強みと捉え、視点を変えることにより、ストレスや不安が軽減できる可能性があります。
就労移行支援の利用期間
就労移行支援事業所に通所する期間は、原則「最長2年間」です。利用者はこの2年間を有効に使って、一般就労のために必要なスキルや技能、知識などを身につける必要があります。
ただし、あくまで「2年以内の一般就労」が目標のため、2年間在籍しなければならないわけではありません。個人差はありますが、半年~1年程度で就労を実現している人もいます。
就労移行支援はトータルの利用期間が2年を超えていなければ、2回目、3回目と再利用もできます。詳しくは以下の記事をご覧ください。
※関連記事:『就労移行支援の利用期間』
ただし、あくまで「2年以内の一般就労」が目標のため、2年間在籍しなければならないわけではありません。個人差はありますが、半年~1年程度で就労を実現している人もいます。
就労移行支援はトータルの利用期間が2年を超えていなければ、2回目、3回目と再利用もできます。詳しくは以下の記事をご覧ください。
※関連記事:『就労移行支援の利用期間』
就労移行支援で取り組めること
就労移行支援のサポートやトレーニング内容は、各事業所によって異なりますが、一般的には下記のようなサポートを受けることができます。
- サポート一覧
体調や就職活動に関する相談
各種スキルの習得
就職活動のサポート
就職前の就労体験
職場定着支援
体調管理の支援、日常生活管理の支援 など
就労移行支援では、実際に業務に役立つビジネススキルだけでなく、対人スキルや体調管理の支援、日常生活管理の支援などのサポートも受けられます。障害や難病などの特性を理解した上で、その人に合った支援計画にもとづき無理なく就職活動に取り組める点も、就労移行支援の魅力のひとつです。
※関連記事:『就労移行支援のサポート内容』
※関連記事:『就労移行支援のサポート内容』
就労移行支援の利用に向いている人向いていない人
就労移行支援の利用には、人によって向き・不向きがあります。以下の表は、就労移行支援に向いている人と向いていない人の状況を比較した表です。
| 向いている人 | 向いていない人 | |
|---|---|---|
| 体調 | 安定している | 安定していない |
| 就職時期 | 今すぐ就職する自信がない | 今すぐ就職したい |
| 就労経験 | 経験がない・少ない | 経験に対するこだわりが強い |
| スキルレベル | 実務レベルに満たない、自信がない | 実務レベルを満たしている |
| 金銭面 | 生活費がある | 当面の生活費の確保に不安がある |
就労移行支援は、一般企業での就労を目指しているため、通所期間中は週3日~5日の通所が推奨されています。そのため、就労移行支援を利用する上では、体調の安定が前提となります。
また、就労移行支援の利用にあたって、賃金の支払いは発生しません。就労移行支援に通っている間は、家族の生活支援を受けるか貯金などによって生活費を補う必要があります。
上記を踏まえた上で、就労移行支援の利用に向いている人と向いていない人の特徴について以下で詳しく解説します。
また、就労移行支援の利用にあたって、賃金の支払いは発生しません。就労移行支援に通っている間は、家族の生活支援を受けるか貯金などによって生活費を補う必要があります。
上記を踏まえた上で、就労移行支援の利用に向いている人と向いていない人の特徴について以下で詳しく解説します。
就労移行支援の利用に向いている人の特徴
次のような特徴の人は、就労移行支援の利用が向いていると言えます。
- 特徴
障害や難病があり、就職活動に不安がある人
就職活動に苦戦している人
就職に意欲があり、主体性をもった人
一般雇用・障害者雇用の形態にこだわりがない人 など
それぞれ詳しく解説していきます。
障害や難病があり、就職活動に不安がある人
就労移行支援では、支援員との面談などを通じて、障害特性や職業適性への理解を深められます。自分を客観視し、強みや弱み、望ましい配慮などを整理することで不安を払拭できるだけでなく、専門知識をもった人からの助言やアドバイスを受けられるため、安心して就職活動に取り組めるでしょう。
就職活動に苦戦している人
就職活動に取り組んでいるものの、うまくいかない人にも就労移行支援をおすすめします。
就職活動がうまくいかない理由はさまざまありますが、主な原因として以下のようなものが考えられます。
就職活動がうまくいかない理由はさまざまありますが、主な原因として以下のようなものが考えられます。
- 主な要因
・障害や病気に対する自己理解ができていない
・自分に合った仕事を理解していない
・コミュニケーション能力が不足している
・基礎的なビジネススキルや知識が不足している
・計画的に進められない
・一人でおこなう就職活動に孤独を感じている など
就労移行支援事業所では、利用者一人ひとりの特性や希望に応じた個別支援計画書を作成します。そのため、自分に不足しているスキルを計画的に学べるでしょう。ビジネススキルに限らず、ビジネスマナーやコミュニケーションスキルなど、総合的な「はたらく力」を身につけられるのも特徴です。
また、就労移行支援では、年齢や経験は異なっても、障害や困りごとをもつ人に出会えます。一緒に頑張っていける仲間ができることで、生活やトレーニングに意欲が生まれることも期待できます。
また、就労移行支援では、年齢や経験は異なっても、障害や困りごとをもつ人に出会えます。一緒に頑張っていける仲間ができることで、生活やトレーニングに意欲が生まれることも期待できます。
就職に意欲があり、主体性をもった人
本人が就職したいと思っていない場合、モチベーションを保つのが難しくなります。就労移行支援に通う意味がわからなくなり、最悪の場合、利用を中止する可能性が高まるでしょう。
就労移行支援は2年間利用したら、特別な理由がない限り再び利用することはできません。自身が本当に必要と感じた際の利用をおすすめします。
就労移行支援は2年間利用したら、特別な理由がない限り再び利用することはできません。自身が本当に必要と感じた際の利用をおすすめします。
一般雇用・障害者雇用の形態にこだわりがない人
就労移行支援は、一般雇用・障害者雇用の形態にこだわらず、就労意欲がある人に向いています。障害者雇用とは、障害のある人が障害のない人と同様にはたらく機会を得られるよう、自治体や企業が特別な採用枠で雇用することです。障害があることを前提としているため、障害者手帳を取得している人が対象で、一般雇用とは異なる採用基準での就職となります。
就労移行支援では、自己理解・障害理解に基づく合理的配慮の整理や、障害者手帳の取得に関する相談など、障害者雇用ではたらくためのサポートもおこなっています。そのため、雇用形態を一般雇用に限定せず、障害者雇用も視野に入れた就職活動により、安定した長期就労を目指したい人におすすめです。
※関連記事:『障害者雇用ではたらくとは?一般雇用との違いや障害者手帳の種類についてまとめました』
就労移行支援では、自己理解・障害理解に基づく合理的配慮の整理や、障害者手帳の取得に関する相談など、障害者雇用ではたらくためのサポートもおこなっています。そのため、雇用形態を一般雇用に限定せず、障害者雇用も視野に入れた就職活動により、安定した長期就労を目指したい人におすすめです。
※関連記事:『障害者雇用ではたらくとは?一般雇用との違いや障害者手帳の種類についてまとめました』
向いていない人の特徴
反対に、就労移行支援に向いていないのは、以下のような特徴の人です。
- 向いていない人の特徴
・就労に必要なスキルや知識が身についている人
・就職先を紹介してもらいたいだけの人
・専門的なスキルを身につけたいだけの人
・就職への意欲や主体性に欠ける人 など
就労移行支援事業所は、障害や難病による不安や困りごとのある人が、一般企業への就職を目指してトレーニングをおこなう場です。そのため、日常生活に問題がなく、基本的労働習慣がすでに身についており、就労に対して不安や困りごとがない人には、就労移行支援は向いていないと言えるでしょう。
また、「専門的なスキルを身につけたいだけ」「就職先を紹介してもらいたいだけ」と考えている場合も、その分野に特化した他のサービスを選んだ方が効率的なため就労移行支援はおすすめしません。
就労移行支援の利用を検討している人は、自分の目的や状況が適しているかどうかを見極める必要があります。
また、「専門的なスキルを身につけたいだけ」「就職先を紹介してもらいたいだけ」と考えている場合も、その分野に特化した他のサービスを選んだ方が効率的なため就労移行支援はおすすめしません。
就労移行支援の利用を検討している人は、自分の目的や状況が適しているかどうかを見極める必要があります。
就労移行支援事業所の探し方
就労移行支援が自分に向いていると判断したら、実際に通える範囲にある就労移行支援事業所を探してみましょう。おすすめの探し方は以下の3つです。
- 探し方
・市区町村に相談する
・専門機関に相談する
・検索サイトで調べる
市区町村の障害福祉窓口に相談すると、近隣の就労移行支援事業所をまとめた一覧表やパンフレットがもらえるので、事業所探しに役立つでしょう。
障害や難病で通院している場合は、通院先に相談する方法もあります。障害者就業・生活支援センターや、就労支援センター、相談支援事業所、ハローワークなど専門的な知識をもつ福祉関係機関への相談もおすすめです。
インターネットで検索する際には、「就労移行支援事業所 ○○市」と住んでいる地域を入れると最寄りの事業所が見つかりやすいでしょう。
就労移行支援事業所をいくつか見つけたら、見学や体験を通して事業所の雰囲気やトレーニング内容、支援員の人柄などを確かめましょう。事業所選びのポイントや判断ポイントを紹介した記事もあります。参考にしてください。
※関連記事:『就労移行支援事業所って何?利用を検討する際のメリットと8つの判断チェックポイントを紹介』
※関連記事:『就労移行支援の利用前に知っておきたい、事業所選びのポイント』
障害や難病で通院している場合は、通院先に相談する方法もあります。障害者就業・生活支援センターや、就労支援センター、相談支援事業所、ハローワークなど専門的な知識をもつ福祉関係機関への相談もおすすめです。
インターネットで検索する際には、「就労移行支援事業所 ○○市」と住んでいる地域を入れると最寄りの事業所が見つかりやすいでしょう。
就労移行支援事業所をいくつか見つけたら、見学や体験を通して事業所の雰囲気やトレーニング内容、支援員の人柄などを確かめましょう。事業所選びのポイントや判断ポイントを紹介した記事もあります。参考にしてください。
※関連記事:『就労移行支援事業所って何?利用を検討する際のメリットと8つの判断チェックポイントを紹介』
※関連記事:『就労移行支援の利用前に知っておきたい、事業所選びのポイント』
就労移行支援「ミラトレ」で自分に向いている仕事を見つけよう
今回は、就労移行支援に向いている人と向いていない人の状況や特徴について解説しました。就労移行支援は、一般企業ではたらきたいと考えている障害のある人や難病の人を対象にした支援サービスです。就職に際して不安や悩みがない人や、はたらくための知識やスキルが十分に身についている人には向いていないと言えます。
就労移行支援事業所「ミラトレ」では、障害のある人が自分らしいはたらき方を見つけられるよう、就職準備はもちろん職場への定着まで総合的な支援をおこなっています。ビジネススキルやメンタルケアなど各分野の専門家が連携しあい、一人ひとりの能力や課題に配慮しながら、スキル向上をサポート。実際の職場をイメージした疑似就労プログラムにも力を入れています。
就労移行支援が向いているかどうかお悩みの方や、ミラトレのサービスについて知りたい方は、気軽にお問い合わせください。
就労移行支援事業所「ミラトレ」では、障害のある人が自分らしいはたらき方を見つけられるよう、就職準備はもちろん職場への定着まで総合的な支援をおこなっています。ビジネススキルやメンタルケアなど各分野の専門家が連携しあい、一人ひとりの能力や課題に配慮しながら、スキル向上をサポート。実際の職場をイメージした疑似就労プログラムにも力を入れています。
就労移行支援が向いているかどうかお悩みの方や、ミラトレのサービスについて知りたい方は、気軽にお問い合わせください。

執筆 : ミラトレノート編集部
パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業ミラトレが運営しています。専門家の方にご協力いただきながら、就労移行支援について役立つ内容を発信しています。
アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3

アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3