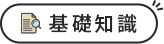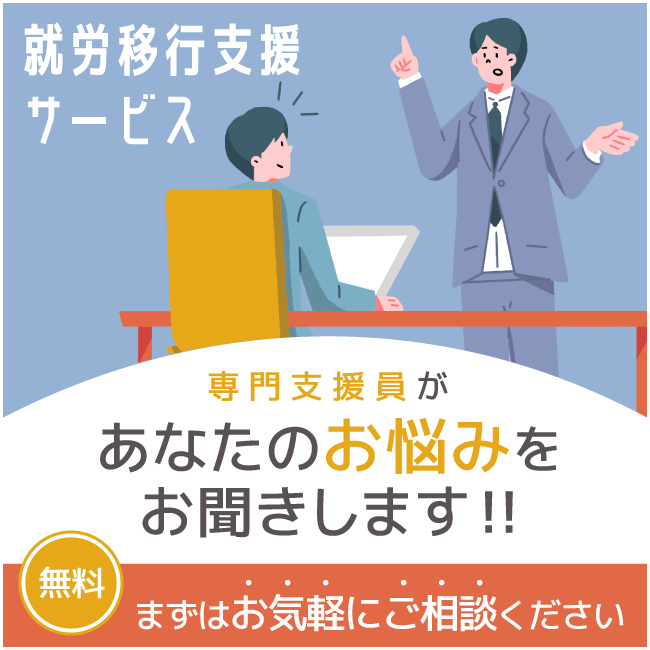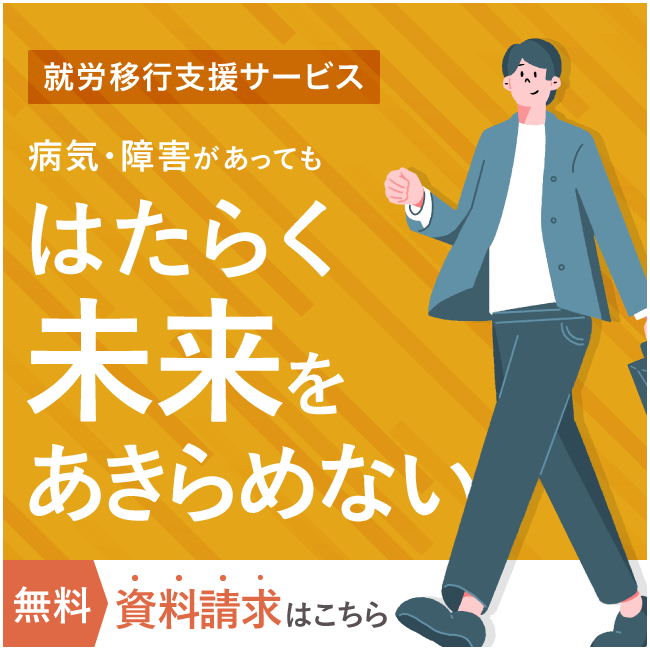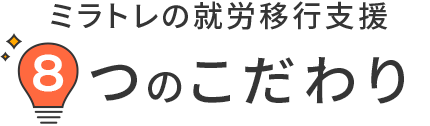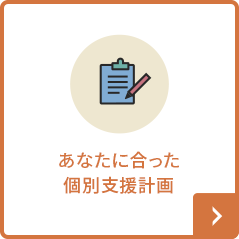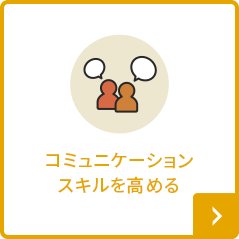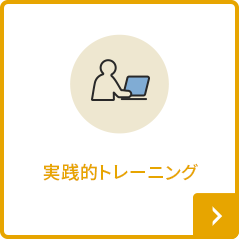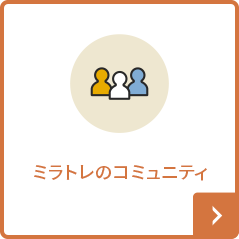ミラトレノート
就労移行支援の
 基礎
基礎 知識
知識



強迫性障害の症状があるために、「仕事をするのが怖い」「記憶に自信がない」など、仕事に対する不安を抱える人もいるでしょう。強迫性障害の方が、就職し長くはたらき続けるためには、どのような工夫が必要なのでしょうか。今回は、産業医科大学教授江口尚先生の解説のもと、強迫性障害の基礎知識や仕事選びのポイント、長くはたらき続けるためのコツを紹介します。
目次
-
1.強迫性障害の基礎知識
-
1-1.強迫性障害の主な症状
-
1-2.強迫性障害の要因
-
1-3.強迫性障害の主な治療方法
-
1-4強迫性障害の生活する上での困りごと
-
2.生活するために活用したいサポート
-
3.強迫性障害のある人に対して周りが理解するべきこと
-
3-1.家族や周りの人ができるサポートについて教えてください
-
3-2.強迫性障害の人に接する際の注意点や接し方のポイントはありますか?
-
4.強迫性障害のある人が仕事を選ぶポイント
-
4-1.強迫性障害の人が就職活動で大切にすべきことは何ですか?
-
4-2.強迫性障害の人が比較的はたらきやすいのはどのような環境ですか?
-
4-3.強迫性障害の人にとって注意が必要な仕事はありますか?
-
5.強迫性障害のある人のはたらく形、仕事を続けるコツなどを解説
-
5-1.強迫性障害の人が、長くはたらき続けるためのコツはありますか?
-
5-2.強迫性障害の人が長くはたらくために、家族や職場の方にはどのようなサポートを求めるとよいでしょう?
-
5-3.強迫性障害の人がはたらきやすい、はたらき方の形はありますか?
-
6.強迫性障害のある人の「仕事」に対するよくある疑問
-
6-1.自分の障害を職場に伝えるべき?
-
6-2.仕事を始めるのが怖い…どうしたらよい?
-
7.強迫性障害に向き合い、仕事ができる環境を見つけよう
強迫性障害の基礎知識
強迫性障害とは、突然ある考えが頭に浮かんで離れなくなり、考えから生まれた不安や苦痛を振り払うために何度も同じ行動を繰り返してしまう障害のことを指します。何度手を洗ってもきれいにならないと感じて手洗いが止まらなくなってしまったり、戸締まりの確認を何度も繰り返し約束の時間に遅れてしまったりなど、日常生活に影響が出てしまう状態です。不安を感じるだけでなく、その不安を振り払うための過度な行動が伴います。
強迫性障害と混同されやすいものに「強迫性パーソナリティ障害」があります。強迫性パーソナリティ障害は、個性や特性として生まれ持ったこだわりが強すぎて、日常生活に支障がある障害です。不安から行動するのではなく、秩序や規則に対する強いこだわりが行動を起こさせるので、強迫性障害とは異なります。
また、強迫性障害の人は不安を取り払うための行動が過度になっていると自分でも分かるため、「何をしているのだろう」「どうして行動を抑えられないのだろう」と悩み、ストレスや生きづらさが繰り返されてしまいます。そうした悩みやストレスから、抑うつ障害や不安障害など、他の障害を併発しやすいのも特徴です。
強迫性障害と混同されやすいものに「強迫性パーソナリティ障害」があります。強迫性パーソナリティ障害は、個性や特性として生まれ持ったこだわりが強すぎて、日常生活に支障がある障害です。不安から行動するのではなく、秩序や規則に対する強いこだわりが行動を起こさせるので、強迫性障害とは異なります。
また、強迫性障害の人は不安を取り払うための行動が過度になっていると自分でも分かるため、「何をしているのだろう」「どうして行動を抑えられないのだろう」と悩み、ストレスや生きづらさが繰り返されてしまいます。そうした悩みやストレスから、抑うつ障害や不安障害など、他の障害を併発しやすいのも特徴です。
強迫性障害の主な症状
強迫性障害の症状としては、「強迫観念」と「強迫行為」があります。「強迫観念」は自分の意思に関係なく突然浮かんで頭から離れない考えのことをいいます。
強迫観念から生まれた不安にかきたてられ、やらずにはいられなくなる行為が「強迫行為」です。自分でもやりすぎている、無意味であるとわかっていても止められない行動を指します。代表的な強迫観念と強迫行為の内容としては、次のようなものが挙げられます。
強迫観念から生まれた不安にかきたてられ、やらずにはいられなくなる行為が「強迫行為」です。自分でもやりすぎている、無意味であるとわかっていても止められない行動を指します。代表的な強迫観念と強迫行為の内容としては、次のようなものが挙げられます。
- 不潔と洗浄
汚れや細菌汚染の恐怖から、過剰な手洗い、入浴、洗濯を繰り返す
ドアノブや手すりが不潔だと感じて触れないなど - 加害恐怖
誰かに危害を加えたかもしれないという不安が心を離れず、新聞やテレビに事件・事故として出ていないか確認したり、警察や周囲の人に確認したりする - 確認行為
戸締まり、ガス栓、電気器具のスイッチを過剰に確認する
(何度も確認する、じっと見張る、指差し確認する、手で触って確認するなど) - 儀式行為
自分の決めた手順でものごとをおこなわないと、恐ろしいことが起きるという不安から、どんなときも同じ方法で仕事や家事をしなくてはならない - 数字へのこだわり
不吉な数字・幸運な数字に、縁起をかつぐというレベルを超えてこだわる - 物の配置、対称性などへのこだわり
物の配置に一定のこだわりがあり、必ずそうなっていないと不安になる
これらの強迫行為は「やってはいけない」と頭ではわかっていても、衝動を抑えられず、我慢できないものです。気持ちが全てその不安や苦痛に向いてしまい、振り払わずにはいられません。これらが度を越し、社会生活に支障がでていると判断された場合は、強迫性障害と診断されます。
強迫性障害の要因
強迫性障害の要因は、よくわからないことが多いようです。幼い頃のトラウマが引き金となることもあります。トラウマもさまざまで、虐待された経験や交通事故、火事や地震、家族の死などが関係すると考えられています。また、強いストレスが原因で発症する場合もあるようです。過重労働が続くことで、知らず知らずにストレスを抱えることもあるかもしれません。これらのことから、医師は診断の際は、病歴や生育歴を丁寧にヒアリングすることが多いです。
強迫性障害は、パニック障害のように突発的に起こるものではなく、あらわれる頻度が徐々に増していくことで、気づいたら強迫行為を止められなくなってしまうというケースが多いようです。自分が困るだけでなく、周りの人にも強迫行為を強制するなどで迷惑がかかってしまい、強迫性障害が判明することもあります。
強迫性障害は、パニック障害のように突発的に起こるものではなく、あらわれる頻度が徐々に増していくことで、気づいたら強迫行為を止められなくなってしまうというケースが多いようです。自分が困るだけでなく、周りの人にも強迫行為を強制するなどで迷惑がかかってしまい、強迫性障害が判明することもあります。
強迫性障害の主な治療方法
強迫性障害の主な治療方法としては、認知行動療法や薬物療法が挙げられます。薬物療法では、脳内のホルモンバランスを整えて、症状を安定させていくSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)などの薬が用いられます。強迫症状が治まる効果が期待されるセロトニンの働きを強める効果のある薬です。
また、認知行動療法の中では、「ばく露反応妨害法」が強迫性障害の代表的な治療方法として挙げられます。不安を感じる状況の中でも強迫行為をしないで我慢するという行動療法です。施錠したか不安になっても確認に戻らず我慢したり、汚いと思うものを触っても手を洗わないで我慢したりを続けることで、不安が次第に弱まり、強迫行為をしなくてもよくなっていくという流れです。
また、認知行動療法の中では、「ばく露反応妨害法」が強迫性障害の代表的な治療方法として挙げられます。不安を感じる状況の中でも強迫行為をしないで我慢するという行動療法です。施錠したか不安になっても確認に戻らず我慢したり、汚いと思うものを触っても手を洗わないで我慢したりを続けることで、不安が次第に弱まり、強迫行為をしなくてもよくなっていくという流れです。
強迫性障害の生活する上での困りごと
強迫性障害の人の多くは、普通の人ならそれほど時間のかからない行為に対して、予定より長く時間を使ってしまうことを困りごととして挙げています。戸締まりの確認や仕事上の書類確認、手洗いにも多くの時間を使ってしまうのです。
約束の時間に遅れる、納期に間に合わないなどの状況であっても強迫行為をし続けてしまうため、時間を上手に使えないことに困る人も多いといいます。
また、周囲の理解を得られないという困りごともあるようです。障害と認識されにくく、「こだわりの強い人」「細かすぎる人」という目で見られることもあるでしょう。自分が困っていて苦しんでいることを理解してもらえない点は、本人にとってもつらいことです。
約束の時間に遅れる、納期に間に合わないなどの状況であっても強迫行為をし続けてしまうため、時間を上手に使えないことに困る人も多いといいます。
また、周囲の理解を得られないという困りごともあるようです。障害と認識されにくく、「こだわりの強い人」「細かすぎる人」という目で見られることもあるでしょう。自分が困っていて苦しんでいることを理解してもらえない点は、本人にとってもつらいことです。
生活するために活用したいサポート
強迫性障害の方の生活を支えるためには、さまざまなサポートがあります。これらを上手に活用し、生活基盤を整えましょう。
職場の産業医や学校の精神科医、スクールカウンセラーに相談できます。勤務先が産業医を選任していない場合は、都道府県に設置されている産業保健総合支援センター(さんぽセンター)に相談するとよいでしょう。
職場の産業医や学校の精神科医、スクールカウンセラーに相談できます。勤務先が産業医を選任していない場合は、都道府県に設置されている産業保健総合支援センター(さんぽセンター)に相談するとよいでしょう。
- 医療費のサポート
・自立支援医療
精神科の治療のため、定期的・継続的に通院している場合、かかった医療費を補助してもらえる制度です - 暮らしと社会生活のサポート
・精神障害者保健福祉手帳
税金の優遇制度や交通機関の割引、公営住宅への優先入居など経済的・福祉的なサービスを利用することができます - 就労のサポート
・就労移行支援事業所
・ハローワーク
・地域障害者職業センター
・障害者就業・生活支援センター(なかぽつ) - さまざまな相談ごとのサポート
・保健所
└都道府県別の保健所一覧
・精神保健福祉センター
└全国精神保健福祉センター一覧
・病院の患者会や家族会
└みんなねっと
強迫性障害のある人に対して周りが理解するべきこと
強迫性障害の方を支える家族や周りの人は、どのように本人に接するとよいのでしょうか。家族ができるサポートや職場の方に理解してほしいことについて、産業医科大学教授 江口尚先生に解説いただきます。

【監修者】
産業医科大学 産業生態科学研究所
産業精神保健学研究室 教授
江口 尚氏
【専門分野】
職場の心理社会的要因、治療と仕事の両立支援、障害者や中小企業の産業保健
家族や周りの人ができるサポートについて教えてください
家族や周りの方は、強迫性障害の方を説得しないでただきたいです。本人は好んで強迫行為をしているわけではなく、不合理であることもよくわかっています。自分の中に巻き起こる不安や衝動を抑えられずに苦しんでいることを理解してください。説得できない状況であることを念頭において、まずは本人のつらい気持ちを聞いてあげてほしいです。
そして、精神科の受診を促すことも大切です。家族や周りの方が本人への接し方に悩む場合は、主治医に相談し、本人に合わせたアドバイスをもらうとよいでしょう。家庭内は、家族が生活を保てる範囲で、なるべく本人が安心して暮らせる環境づくりなど、配慮ができるとさらによいと思います。
そして、精神科の受診を促すことも大切です。家族や周りの方が本人への接し方に悩む場合は、主治医に相談し、本人に合わせたアドバイスをもらうとよいでしょう。家庭内は、家族が生活を保てる範囲で、なるべく本人が安心して暮らせる環境づくりなど、配慮ができるとさらによいと思います。
強迫性障害の人に接する際の注意点や接し方のポイントはありますか?
強迫性障害は、がんばって何とかなるものではありません。病院やカウンセリングに通い、適切な治療を受けることで症状が軽減されます。本人を否定する言葉や、「がんばれ」「我慢しなさい」といった言葉をかけるのはやめましょう。強迫性障害の方は、自分自身で十分に自分を否定しています。つらさを受け止めて、理解できないことがあっても本人に伝えることは避けた方がよいでしょう。
強迫性障害のある人が仕事を選ぶポイント
強迫性障害の方が就職する際、仕事を選ぶときのポイントはあるのでしょうか。就職活動をする上で大切にすべきことなど、江口先生に解説いただきます。
強迫性障害の人が就職活動で大切にすべきことは何ですか?
強迫性障害の方が就職活動の際に大切にした方がよいことは、その職場が強迫性障害に理解があるかどうかという点です。障害があることを理解してくれた上で、仕事の成果や実績が伴っていれば勤務中に離席しても問題視されない職場を選べるとよいと思います。
強迫性障害の人が比較的はたらきやすいのはどのような環境ですか?
強迫性障害の方のはたらきやすさという点では、「在宅勤務」という選択肢が挙げられます。私生活上の困難なことは、自宅にいることである程度はコントロールできるからです。ただし、仕事の確認をする際には課題が生じるかもしれません。出社し、周りに人がいる状態であれば簡単にできる確認作業も、オンライン上では難しさを感じる場合もあります。そういった意味では、ある程度本人の裁量でできる仕事を任せてもらえれば、はたらきやすさにつながるでしょう。
強迫性障害の人にとって注意が必要な仕事はありますか?
一口に強迫性障害と言っても症状に個人差はありますが、通勤距離が長い場合は注意が必要でしょう。自宅から遠い場所へ行くほど、不安や心配事が膨らむケースがあるためです。また、拘束時間が長い仕事の場合は、突然強迫観念に襲われてもすぐに離席や帰宅することが難しく、不安を拭い去れません。自分のペースで仕事するのが難しく、常に締切に余裕がない仕事なども、強迫行為に時間を奪われてしまうと取り戻すことが難しいため注意が必要でしょう。
強迫性障害のある人のはたらく形、仕事を続けるコツなどを解説
就職自体がゴールではありません。本当に重要なのは、就職後に長くはたらき続けることです。強迫性障害の方が仕事を続けるコツについて、江口先生に解説いただきます。
強迫性障害の人が、長くはたらき続けるためのコツはありますか?
長期就労を目指す強迫性障害の方は、まずはしっかりと通院し治療を受けることが大切です。強迫性障害は、精神科医によっては対応できない場合もあるため、信頼できる主治医を選びましょう。その際には、実績や評判などを確認して選ぶことも重要です。
また、障害について上司や同僚の理解を得られないと、長くはたらくことは難しいと思います。自分の言葉で、自分の特性や症状、症状があらわれたときにどうして欲しいのかをあらかじめ伝えましょう。周囲も障害のことを前もって知っているのと知らないのとでは、症状があらわれたときの反応が違います。その際の離席については、あらかじめ職場と相談しておくとよいと思います。「1時間離席するが、業務はリカバーできる」などと伝えられると、企業側も安心です。
合わせて、自分自身でも対処行動をある程度身につけておくことが大切です。強迫観念に襲われたらどう鎮めるか、強迫行為をしたい衝動にかられたらどう対処したらよいかなどを見つけましょう。自身の認知の癖を認知行動療法などを通して把握し、その対処方法を身につけることで長期就労につながりやすくなります。自分なりに障害との付き合い方がわかっていれば、ストレスや忙しさなど症状が出るきっかけも分かるでしょう。
※認知行動療法とは、自分自身の認知に働きかけて気持ちを楽にする精神療法(心理療法)の一つです。
また、障害について上司や同僚の理解を得られないと、長くはたらくことは難しいと思います。自分の言葉で、自分の特性や症状、症状があらわれたときにどうして欲しいのかをあらかじめ伝えましょう。周囲も障害のことを前もって知っているのと知らないのとでは、症状があらわれたときの反応が違います。その際の離席については、あらかじめ職場と相談しておくとよいと思います。「1時間離席するが、業務はリカバーできる」などと伝えられると、企業側も安心です。
合わせて、自分自身でも対処行動をある程度身につけておくことが大切です。強迫観念に襲われたらどう鎮めるか、強迫行為をしたい衝動にかられたらどう対処したらよいかなどを見つけましょう。自身の認知の癖を認知行動療法などを通して把握し、その対処方法を身につけることで長期就労につながりやすくなります。自分なりに障害との付き合い方がわかっていれば、ストレスや忙しさなど症状が出るきっかけも分かるでしょう。
※認知行動療法とは、自分自身の認知に働きかけて気持ちを楽にする精神療法(心理療法)の一つです。
強迫性障害の人が長くはたらくために、家族や職場の方にはどのようなサポートを求めるとよいでしょう?
一番近くにいてくれる家族には、基本的には見守っていてもらうようお願いしています。本人に余裕があるときにはセルフモニタリングできているかと思いますが、余裕がなくなると難しい面もあります。そのようなときには家族から「少し頑張りすぎているのではないか」と率直に伝えてもらうことで、ストレスに気づける場合もあります。
また、症状が安定している方でも、忙しさなどで不安定になってしまうこともあります。不安定なときには、可能であればその不安定さを緩和できるような環境を職場に求めましょう。治療によって強迫性障害による症状が緩和することはありますが、完全に治るわけではありません。周囲の方には「ストレスへの対処が苦手」なことを知っていてもらうことも大切です。症状が安定しているからといって安易に仕事量を増やすのは危険です。仕事量が増えると不安定になってしまう人もいますので、仕事量を増やす場合には本人と職場がきちんと相談し、徐々に増やす方がよいでしょう。
また、症状が安定している方でも、忙しさなどで不安定になってしまうこともあります。不安定なときには、可能であればその不安定さを緩和できるような環境を職場に求めましょう。治療によって強迫性障害による症状が緩和することはありますが、完全に治るわけではありません。周囲の方には「ストレスへの対処が苦手」なことを知っていてもらうことも大切です。症状が安定しているからといって安易に仕事量を増やすのは危険です。仕事量が増えると不安定になってしまう人もいますので、仕事量を増やす場合には本人と職場がきちんと相談し、徐々に増やす方がよいでしょう。
強迫性障害の人がはたらきやすい、はたらき方の形はありますか?
強迫性障害の方がはたらく中でよく聞かれる困りごととして、仕事のペースを自分の裁量で決められないことや、物理的に拘束されてしまうことなどが挙げられます。同じ場所で何時間も作業しなければならない職場環境や、アポイントの時間に拘束される営業の仕事などは、強迫性障害の方のはたらきやすさに矛盾するでしょう。まずは相談先をつくり、自分にあったはたらき方について相談にのってもらいましょう。まずは、しっかりと医療機関にかかり、仕事のことについて主治医に相談しましょう。症状が出たときに周囲への支援を求める際には、職場の産業医や産業保健スタッフに相談をしてみましょう。
もしも確認癖が悪化したり、勤怠が乱れたりした場合は要注意です。迷わず受診し、主治医に相談した上で休職も選択するとよいでしょう。しっかりと休んでリセットすることも、ときには大切です。症状が落ち着くと通院をやめてしまう人もいますが、きちんと通院し、薬の量を調整しながら過ごしましょう。医療機関や職場に相談先をつくっておくことが、はたらきやすさや長期就労につながると考えます。
もしも確認癖が悪化したり、勤怠が乱れたりした場合は要注意です。迷わず受診し、主治医に相談した上で休職も選択するとよいでしょう。しっかりと休んでリセットすることも、ときには大切です。症状が落ち着くと通院をやめてしまう人もいますが、きちんと通院し、薬の量を調整しながら過ごしましょう。医療機関や職場に相談先をつくっておくことが、はたらきやすさや長期就労につながると考えます。
強迫性障害のある人の「仕事」に対するよくある疑問
仕事に対して不安や疑問を抱えることもあるでしょう。ここでは、強迫性障害の人の多くが抱く疑問・不安について解説します。判断に悩むときの参考にしてください。
自分の障害を職場に伝えるべき?
「最近、強迫性障害の症状が頻出している。仕事に遅刻するなど業務に支障が出そうだが、職場に伝えるべきか」といった悩みを持つ人もいるでしょう。強迫性障害が理由で仕事に遅れているとわからない人からすると、「よく遅刻をして、やる気がない」と勘違いされてしまうケースもあります。
企業には、障害のある人が感じるバリアを取り除くために「合理的配慮」を提供する義務があります。事業主や直属の上司にはあらかじめ障害があることを伝えておくことで、適切な配慮が得られるでしょう。
医師による診断書があると会社側の理解も得られやすいです。もし、産業医や人事担当者に伝えることはハードルが高いと感じるならば、家族や友人、同僚など身近に相談できる人がいると安心です。
※関連記事:「合理的配慮とわがままの違いは?10の実例を交えてポイントを解説」
企業には、障害のある人が感じるバリアを取り除くために「合理的配慮」を提供する義務があります。事業主や直属の上司にはあらかじめ障害があることを伝えておくことで、適切な配慮が得られるでしょう。
医師による診断書があると会社側の理解も得られやすいです。もし、産業医や人事担当者に伝えることはハードルが高いと感じるならば、家族や友人、同僚など身近に相談できる人がいると安心です。
※関連記事:「合理的配慮とわがままの違いは?10の実例を交えてポイントを解説」
仕事を始めるのが怖い…どうしたらよい?
「仕事を始めたいが、迷惑をかけてしまうかもしれない。でも仕事をしなければ生活ができない」といった悩みを抱える声も聞きます。まずは専門機関を受診して、治療をおこないましょう。その後、仕事を始めてよいか、医師による判断を得ることが賢明です。
一般企業への就職や復職に不安がある場合は、「就労移行支援」や「就労継続支援」などを利用することもおすすめです。就労移行支援や就労継続支援では、支援員のサポートを受けながら、自分のペースで働くためのスキルを身につけられます。通所することで、実際にはたらくイメージを持つことができ、不安を和らげられるでしょう。
また、医療機関や障害者職業センター、就労移行支援事業所などの就労支援機関では、求職者を対象に「リワーク」(復職支援)もおこなっています。リワークの目的は、復職を支援する専門スタッフに相談しながら、プログラムを通して仕事のスキルや集中力を回復させることです。復職への負担を減らすことで、復帰後も無理なくはたらき続けられるでしょう。
一般企業への就職を考える人は、通院や症状によって業務に遅れが出る可能性もあります。業務量や進度を理解してもらえるか、調整をしてもらえるかなど相談することで、お互いの不安を軽減できるとよいでしょう。
※関連記事:「長期休職中の方に必要なリワークとは?取り組み内容やリワークの効果について解説」
一般企業への就職や復職に不安がある場合は、「就労移行支援」や「就労継続支援」などを利用することもおすすめです。就労移行支援や就労継続支援では、支援員のサポートを受けながら、自分のペースで働くためのスキルを身につけられます。通所することで、実際にはたらくイメージを持つことができ、不安を和らげられるでしょう。
また、医療機関や障害者職業センター、就労移行支援事業所などの就労支援機関では、求職者を対象に「リワーク」(復職支援)もおこなっています。リワークの目的は、復職を支援する専門スタッフに相談しながら、プログラムを通して仕事のスキルや集中力を回復させることです。復職への負担を減らすことで、復帰後も無理なくはたらき続けられるでしょう。
一般企業への就職を考える人は、通院や症状によって業務に遅れが出る可能性もあります。業務量や進度を理解してもらえるか、調整をしてもらえるかなど相談することで、お互いの不安を軽減できるとよいでしょう。
※関連記事:「長期休職中の方に必要なリワークとは?取り組み内容やリワークの効果について解説」
強迫性障害に向き合い、仕事ができる環境を見つけよう
強迫性障害の人が就職し、長くはたらくためのさまざまなコツを紹介しました。仕事を始めたいけれど「再び症状が出るのが怖い」「何度確認しても解決・完了していないと感じてしまう」などの悩みをもつ人もいるでしょう。長くはたらくためには、自己理解や障害受容など、まずは自分を知ることが大切です。一人ではどうしたらよいかわからないときは、精神科や心療内科といった医療機関、就労移行支援事業所などの外部サービスを利用し、サポートを受けるとよいでしょう。治療を重ねて仕事ができるようになったら、自分に合った環境を見つけ、就職に向けて取り組んでみてはいかがでしょうか。

執筆 : ミラトレノート編集部
パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業ミラトレが運営しています。専門家の方にご協力いただきながら、就労移行支援について役立つ内容を発信しています。
アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3

アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3