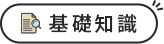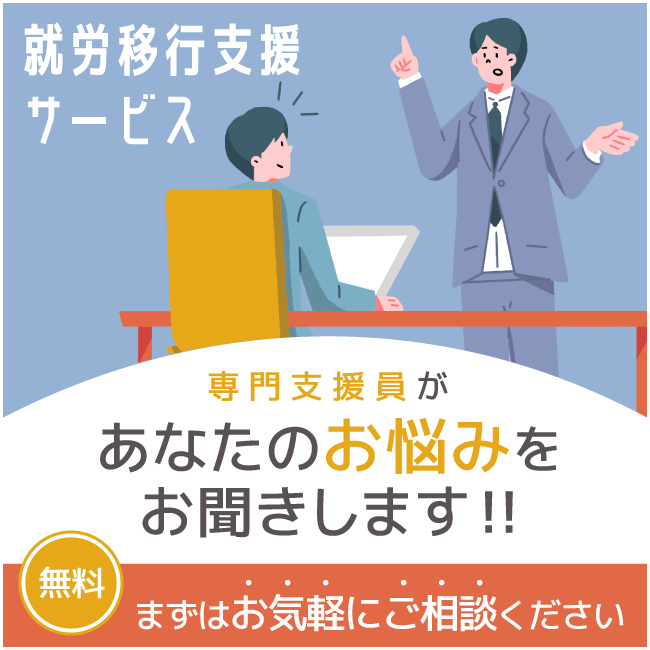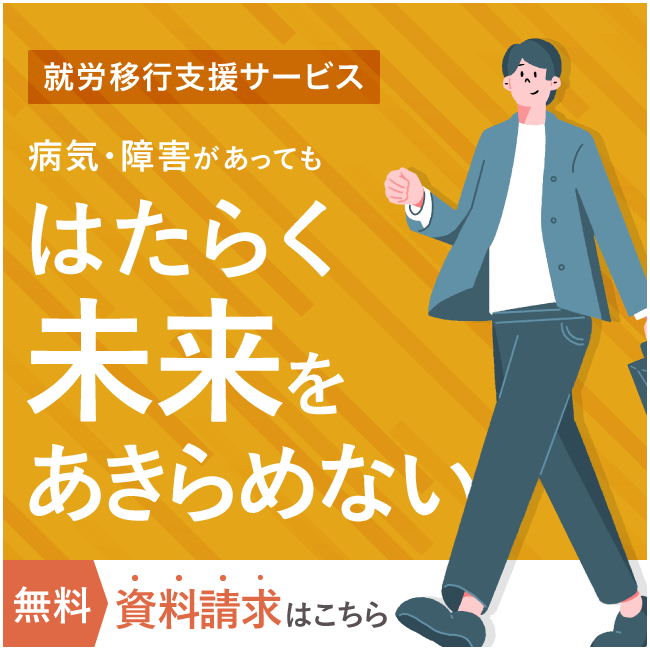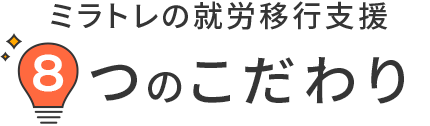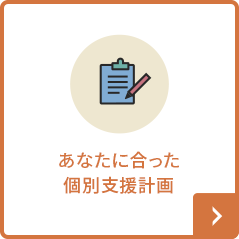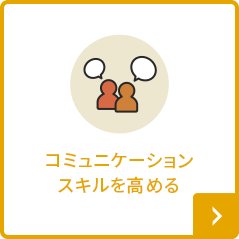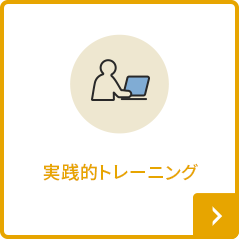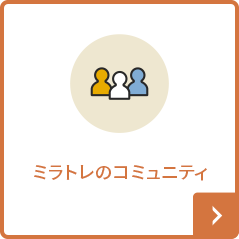ミラトレノート
就労移行支援の
 基礎
基礎 知識
知識



就労移行支援を利用するための手続きのひとつに「認定調査」があります。どのような調査なのか気になる人もいるでしょう。また、認定調査に関連して「障害支援区分認定」という言葉を耳にした人もいるかもしれません。今回は、認定調査や障害支援区分認定の基礎知識について解説します。加えて、就労移行支援を利用するには認定調査のほかにどのような手続きが必要なのか、順を追って説明します。就労移行支援の利用を申請するための予備知識を備えておきたい、という人はぜひご一読ください。
認定調査とは
認定調査とは、障害福祉サービスの利用を申請した人に対して、サービスの必要性を明らかにするためにおこなわれる聞き取り調査です。就労移行支援の認定調査を受ける場合、主にお住まいの市区町村の福祉窓口で、市区町村職員または委託された相談支援専門員から認定調査を受けます。
ただし2024年、厚生労働省は、「障害支援区分の認定を必要としないサービスについては、必ずしも認定調査をおこなう必要はない」という方針を明らかにしました。就労移行支援は障害支援区分の認定を必要としないサービスのため、認定調査を実施しない市区町村もあります。
ただし2024年、厚生労働省は、「障害支援区分の認定を必要としないサービスについては、必ずしも認定調査をおこなう必要はない」という方針を明らかにしました。就労移行支援は障害支援区分の認定を必要としないサービスのため、認定調査を実施しない市区町村もあります。
認定調査のヒアリング内容
認定調査は、原則として1人の調査員が1回でおこない、所要時間はおおむね数十分~2時間ほどです。調査では、主に以下の項目について質問されます。
| 調査項目 | 主な質問内容 |
|---|---|
| ●移動や動作などに関する項目(12項目) | 移動や外出に支援が必要か など |
| ●身の回りの世話や日常生活などに関する項目(16項目) | 健康や栄養の管理、薬の管理、金銭管理に支援が必要か 危険な行為を認識できるか など |
| ●意思疎通などに関する項目(6項目) | コミュニケーション、説明の理解、感覚過敏・感覚鈍麻 などについて |
| ●行動障害に関する項目(34項目) | 感情が不安定、昼夜逆転、こだわり、多動・行動停止、そううつ状態、反復的行動、対人面の不安緊張 などがあるか |
| ●特別な医療に関する項目(12項目) | 過去14日間に特別な医療行為を受けたか |
認定調査では、心身や生活の状態について正確に伝える必要があります。質問内容は簡単ですが、面接の場面において緊張や不安が高まりがちな方は、的確に答えるのは難しいかもしれません。通所を希望している就労移行支援事業所の支援員や家族に同席してもらい、回答を補足してもらうと良いでしょう。また、事前に調査票を確認して、どのように答えるかシミュレーションしておくと安心です。
調査終了後、認定調査の報告書や医師の意見書をもとに、1次判定(コンピュータ判定)と2次判定(市町村審査会)がおこなわれ、結果が通知されます。万一、結果に納得がいかない場合は市区町村に見直しを求めることが可能です。しかし、障害や疾患の診断を受けている人が不支給となるケースは少ないので、あまり心配しなくとも良いでしょう。
調査終了後、認定調査の報告書や医師の意見書をもとに、1次判定(コンピュータ判定)と2次判定(市町村審査会)がおこなわれ、結果が通知されます。万一、結果に納得がいかない場合は市区町村に見直しを求めることが可能です。しかし、障害や疾患の診断を受けている人が不支給となるケースは少ないので、あまり心配しなくとも良いでしょう。
就労移行支援を利用するまでの流れ
就労移行支援を利用するには認定調査のほかにいくつか手続きが必要です。次のような手順で進めましょう。
- 実際の流れ
(1)就労移行支援事業所を探す
↓
(2)就労移行支援事業所へ問い合わせる
↓
(3)見学や体験利用を通じて事業所を決定する
↓
(4)障害福祉サービス受給者証(受給者証)を申請する
↓
(5)認定調査を受ける
↓
(6)サービス等利用計画案を作成・提出する
↓
(7)受給者証が交付される
↓
(8)就労移行支援事業所と利用契約を結ぶ
↓
(9)利用開始
就労移行支援を利用するまでの流れ
(1)就労移行支援事業所を探す
就労移行支援事業所を探す方法として、「インターネットで検索する」「市区町村の障害福祉課に相談する」「障害者就業・生活支援センターなどの専門機関に相談する」という方法があります。自分の障害特性が支援対象となっているか、自分の課題を解決できるトレーニングを実施しているかを確認し、自分に合う事業所を選びましょう。
(2)就労移行支援事業所へ問い合わせる
興味のある事業所が見つかったら、問い合わせや資料請求をおこない、より詳しい情報を集めましょう。
(3)見学や体験利用を通じて事業所を決定する
ほとんどの就労移行支援事業所は見学が可能です。支援員の人柄や事業所の雰囲気、プログラムの進め方など、実際に目で見て確かめましょう。質問や確認しておきたいことを事前にメモにまとめておくとスムーズです。できれば、いくつかの事業所を見学して比較検討し、その中から自分に合っていると感じた事業所で体験利用に参加することをおすすめします。
(4)障害福祉サービス受給者証(受給者証)を申請する
就労移行支援の利用を申請する場合、受給者証を取得する申請が必要となります。この際、障害の状況を証明できる書類があれば障害者手帳は必須ではありません。お住いの地域の市区町村役所福祉窓口に次のものを持参し、申請をおこないます。
就労移行支援事業所を探す方法として、「インターネットで検索する」「市区町村の障害福祉課に相談する」「障害者就業・生活支援センターなどの専門機関に相談する」という方法があります。自分の障害特性が支援対象となっているか、自分の課題を解決できるトレーニングを実施しているかを確認し、自分に合う事業所を選びましょう。
(2)就労移行支援事業所へ問い合わせる
興味のある事業所が見つかったら、問い合わせや資料請求をおこない、より詳しい情報を集めましょう。
(3)見学や体験利用を通じて事業所を決定する
ほとんどの就労移行支援事業所は見学が可能です。支援員の人柄や事業所の雰囲気、プログラムの進め方など、実際に目で見て確かめましょう。質問や確認しておきたいことを事前にメモにまとめておくとスムーズです。できれば、いくつかの事業所を見学して比較検討し、その中から自分に合っていると感じた事業所で体験利用に参加することをおすすめします。
(4)障害福祉サービス受給者証(受給者証)を申請する
就労移行支援の利用を申請する場合、受給者証を取得する申請が必要となります。この際、障害の状況を証明できる書類があれば障害者手帳は必須ではありません。お住いの地域の市区町村役所福祉窓口に次のものを持参し、申請をおこないます。
- 受給者証の申請に必要な持ちもの
●利用申請書
●印かん(認印)
●身分証明書
●障害や疾患を証明できる書類(障害者手帳、自立支援医療受給者証、医師の診断書など)
●マイナンバーカード
※自治体によって、必要な持ちものが異なる場合があります。また、認定調査を予約制にしている自治体もあります。事前に電話などで確認しましょう。
(5)認定調査を受ける
就労移行支援の認定調査の場合は、主に市区町村役所の福祉窓口で認定調査を受けます。介護サービスに関する認定調査の場合は、認定調査員が自宅を訪問しておこなう場合もあります。
(6)サービス等利用計画案を作成・提出する
サービス等利用計画案とは、福祉サービスの利用目的や要望などを書き込む書類です。利用者本人や家族が作成することもできますが、市区町村役所の特定相談支援事業者に依頼することもできます。その場合は、作成に一定の日数がかかる場合がありますので、よく確認しましょう。
(7)受給者証が交付される
申請から1週間~2カ月ほどで受給者証が自宅に届きます。自治体によっては、最長2カ月間の体験利用ができるよう、支給前に暫定支給がおこなわれることもあるので、窓口で確認してください。
(8)就労移行支援事業所と利用契約を結ぶ
事業所で利用契約を結びます。契約書の読み合わせや、書類の記入、押印等の作業があり、1~2時間ほど時間がかかる場合があります。持ち物としては、受給者証や印かんなどが必要になるので、事前に確認しておきましょう。
(9)利用開始
支援員と話し合い、利用開始日を決めましょう。一人ひとりの特性や目標に合わせて、支援員と本人が相談して「個別支援計画」を作成し、その計画にのっとってトレーニングを進めます。
就労移行支援を利用するにはさまざまな手続きが必要ですが、就労移行支援事業所の支援員がサポートしてくれるので、難しく考える必要はありません。不安な点があれば、支援員に相談しましょう。
就労移行支援の認定調査の場合は、主に市区町村役所の福祉窓口で認定調査を受けます。介護サービスに関する認定調査の場合は、認定調査員が自宅を訪問しておこなう場合もあります。
(6)サービス等利用計画案を作成・提出する
サービス等利用計画案とは、福祉サービスの利用目的や要望などを書き込む書類です。利用者本人や家族が作成することもできますが、市区町村役所の特定相談支援事業者に依頼することもできます。その場合は、作成に一定の日数がかかる場合がありますので、よく確認しましょう。
(7)受給者証が交付される
申請から1週間~2カ月ほどで受給者証が自宅に届きます。自治体によっては、最長2カ月間の体験利用ができるよう、支給前に暫定支給がおこなわれることもあるので、窓口で確認してください。
(8)就労移行支援事業所と利用契約を結ぶ
事業所で利用契約を結びます。契約書の読み合わせや、書類の記入、押印等の作業があり、1~2時間ほど時間がかかる場合があります。持ち物としては、受給者証や印かんなどが必要になるので、事前に確認しておきましょう。
(9)利用開始
支援員と話し合い、利用開始日を決めましょう。一人ひとりの特性や目標に合わせて、支援員と本人が相談して「個別支援計画」を作成し、その計画にのっとってトレーニングを進めます。
就労移行支援を利用するにはさまざまな手続きが必要ですが、就労移行支援事業所の支援員がサポートしてくれるので、難しく考える必要はありません。不安な点があれば、支援員に相談しましょう。
就労移行支援の利用に障害支援区分認定は必要?
障害福祉サービスの利用申請者には原則として認定調査がおこなわれますが、「障害支援区分認定」が必要かどうかは障害福祉サービスの種類によって異なります。障害支援区分とは、障害のある人が必要とする支援の度合いを6段階で表すもので、数字が大きいほど必要な支援の度合いも大きくなります。
障害支援区分が必要な障害福祉サービスは介護給付や共同生活援助に限られ、就労移行支援は不要です。障害支援区分の要不要にかかわらず「認定調査」という言葉が使われるため、少し紛らわしいかもしれません。就労移行支援の利用を検討している人は、障害支援区分認定や障害手帳の等級に関係なく申請できることを覚えておくと良いでしょう。
障害支援区分が必要な障害福祉サービスは介護給付や共同生活援助に限られ、就労移行支援は不要です。障害支援区分の要不要にかかわらず「認定調査」という言葉が使われるため、少し紛らわしいかもしれません。就労移行支援の利用を検討している人は、障害支援区分認定や障害手帳の等級に関係なく申請できることを覚えておくと良いでしょう。
就労移行支援事業所「ミラトレ」では一人ひとりの就労をバックアップ
就労移行支援の利用を検討する際は、確かな就職実績がある、自分の障害特性に対応している、就職に向けたトレーニングが充実している、無理なく通える距離である、など自分に合いそうな事業所を選ぶことが大切です。その上で、利用したい事業所が決定したら、支援員に申請方法について相談すると良いでしょう。支援員のサポートを受けながら、スムーズに手続きを進められます。また、支援員と直接コミュニケーションを取ることで、支援員との相性やサポートの質を把握しやすくなるでしょう。
就労移行支援事業所「ミラトレ」では、就労に向けた一歩を安心して踏み出せるよう、さまざまな手続きをサポートしています。ご利用開始後は、自分に合ったはたらき方や障害との向き合い方を見つけられるよう、トレーニングや擬似就労を実施。就職の準備はもちろん、就職後の定着まで総合的に支援しています。
「専門家のサポートを受けながら自分の課題と向き合いたい」「目標に向けて一緒に頑張る仲間がほしい」という方にも、ミラトレの利用をおすすめします。申請方法やプログラム内容など、就労移行支援に関する質問は、気軽にお問い合わせください。
就労移行支援事業所「ミラトレ」では、就労に向けた一歩を安心して踏み出せるよう、さまざまな手続きをサポートしています。ご利用開始後は、自分に合ったはたらき方や障害との向き合い方を見つけられるよう、トレーニングや擬似就労を実施。就職の準備はもちろん、就職後の定着まで総合的に支援しています。
「専門家のサポートを受けながら自分の課題と向き合いたい」「目標に向けて一緒に頑張る仲間がほしい」という方にも、ミラトレの利用をおすすめします。申請方法やプログラム内容など、就労移行支援に関する質問は、気軽にお問い合わせください。

執筆 : ミラトレノート編集部
パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業ミラトレが運営しています。専門家の方にご協力いただきながら、就労移行支援について役立つ内容を発信しています。
アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3

アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3