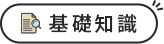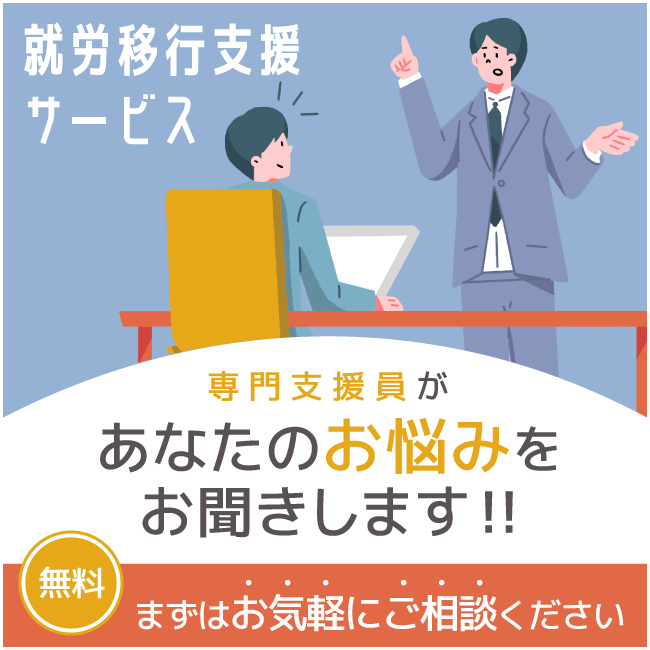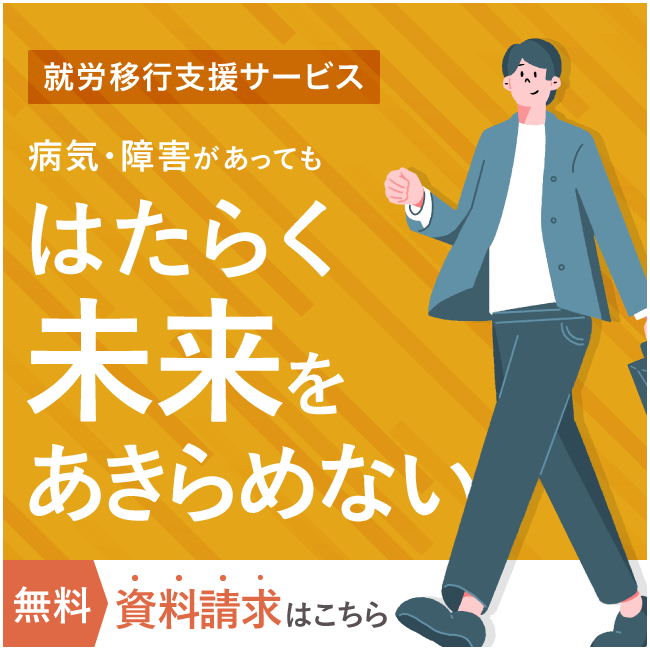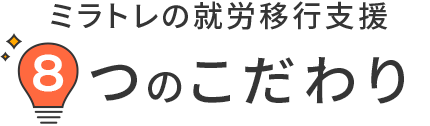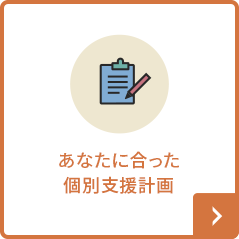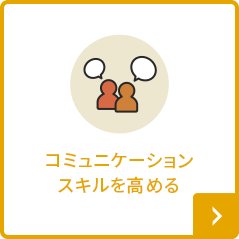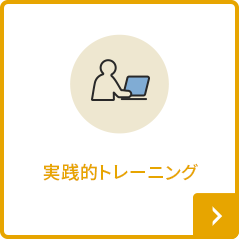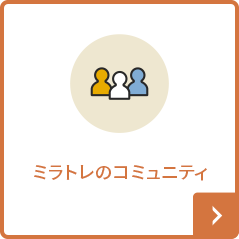ミラトレノート
就労移行支援の
 基礎
基礎 知識
知識



うつ病や適応障害などの精神疾患で休職している人の中には、「リワークはどうすれば利用できるの?」「就労移行支援との違いは?」という疑問を持つ方もいるでしょう。リワークは「復職」、就労移行支援は「就職」を目指して支援を行うサービスです。そのため、対象者・支援内容・利用できる施設・費用などさまざまな点において違いがあります。この記事では、リワークと就労移行支援の違いと、リワークの利用方法についても詳しく解説します。
リワークと就労移行支援の違い
就労移行支援とリワーク(復職支援)は、目的や対象者などが異なる別々のサービスです。
リワークは、「休職中の人」が職場に復帰するためのサポートをおこないます。一方、就労移行支援は、障害や病気のある「求職中の人」を対象に、一般企業の就職に向けたサポートをおこなうサービスです。
ただし、就労移行支援事業所でも、休職中の人を対象としたリワークプログラムを実施している場合があります。
双方の違いをわかりやすく一覧にまとめました。
リワークは、「休職中の人」が職場に復帰するためのサポートをおこないます。一方、就労移行支援は、障害や病気のある「求職中の人」を対象に、一般企業の就職に向けたサポートをおこなうサービスです。
ただし、就労移行支援事業所でも、休職中の人を対象としたリワークプログラムを実施している場合があります。
双方の違いをわかりやすく一覧にまとめました。
| リワーク(復職支援) | 就労移行支援 | |
|---|---|---|
| 目的 | 休職者の復職を支援 | はたらいていない人の就職を支援 |
| 対象 | 精神疾患などで休職中の人 | 障害や難病のある求職中の人(利用開始時に18歳以上65歳未満の人。ただし、18歳未満の場合でも、児童相談所長の意見書があれば利用可能) |
| 料金 | 無料~月額2万円(利用する施設や所得に応じて異なる) | 無料~月額3万7,200円(所得に応じて異なる) |
| 利用期間 | 平均6~7カ月 | 平均1~1年半前後(最長2年) |
| 実施場所 | ・医療機関 ・障害者職業センター ・在籍している企業 ・就労移行支援事業所 |
就労移行支援事業所 |
| 利用条件 | 主治医およびリワーク施設の担当医の許可、雇用元企業の意見書などが必要(※就労移行支援事業所を利用の場合は就労移行支援と同様) | 居住地である市区町村の福祉課に申請が必要 |
目的の違い
リワークと就労移行支援では目的が異なり、リワークは「復職」、就労移行支援は「就職」を目指します。
リワークは、企業に在籍しているものの、精神疾患などで休職中の人が復職できるようサポートするサービスです。そのため、リワークでは、認知行動療法やストレスマネジメントなど心身の回復を目指す、職場復帰に特化したプログラムをおこないます。
会社側に部署異動や業務内容の変更を必要に応じて相談・依頼するなど、休職の原因を取り除くこともリワークの役目です。
就労移行支援は、障害や難病のある求職中の人が一般企業に就職できるようサポートするサービスです。就業に必要な知識やスキルの習得、就職活動支援、職場実習といった一般就労に向けた準備から就職後の職場定着まで幅広いサポートプログラムを提供しています。
リワークは、企業に在籍しているものの、精神疾患などで休職中の人が復職できるようサポートするサービスです。そのため、リワークでは、認知行動療法やストレスマネジメントなど心身の回復を目指す、職場復帰に特化したプログラムをおこないます。
会社側に部署異動や業務内容の変更を必要に応じて相談・依頼するなど、休職の原因を取り除くこともリワークの役目です。
就労移行支援は、障害や難病のある求職中の人が一般企業に就職できるようサポートするサービスです。就業に必要な知識やスキルの習得、就職活動支援、職場実習といった一般就労に向けた準備から就職後の職場定着まで幅広いサポートプログラムを提供しています。
対象者の違い
リワークの対象者は、主にうつ病や不安障害といった精神疾患などにより休職中の会社員です。企業と雇用関係にあり、復職を目指している人が対象となります。
一方、就労移行支援の主な対象者は、一般企業への就労を目指している障害や難病のある人です。はたらいていない、もしくは就労経験がない求職中の人が対象となります。うつ病や統合失調症といった精神障害に限らず、発達障害や知的障害、身体障害がある人も含まれます。
一方、就労移行支援の主な対象者は、一般企業への就労を目指している障害や難病のある人です。はたらいていない、もしくは就労経験がない求職中の人が対象となります。うつ病や統合失調症といった精神障害に限らず、発達障害や知的障害、身体障害がある人も含まれます。
料金の違い
リワークの料金は、利用する施設の種類によって異なります。
以下は、施設の種類別の利用料金です。上限が設定されている医療機関と就労移行支援事業所の場合、収入によって利用料金が異なります。
以下は、施設の種類別の利用料金です。上限が設定されている医療機関と就労移行支援事業所の場合、収入によって利用料金が異なります。
| 施設 | 利用料金 |
|---|---|
| 医療機関(医療リワーク) | 無料~月額2万円 |
| 障害者職業センター(職リハリワーク) | 無料 |
| 企業内(職場リワーク) | 無料 |
| 就労移行支援事業所 | 無料~月額3万7,200円 |
また、医療機関のリワークは、医療保険が適用されるため原則3割負担で利用できます。しかし、自立支援医療制度を利用すれば1割負担となる上、月額の上限額が以下のように設けられているのが特徴です。
| 所得区分(世帯年収) | 一般 | 重度かつ継続 |
|---|---|---|
| 市町村民税所得割 23万5,000円以上(年収約833万円以上) | 対象外 | 2万円 |
| 市町村民税所得割 3万3,000円以上23万5,000円未満(年収約400万~833万円未満) | 総医療費の1割または高額療養費(医療保険)の自己負担限度 内容1 |
1万円 |
| 市町村民税所得割 3万3,000円未満(年収約290万~400万円未満) | 5,000円 | |
| 市町村民税非課税(本人または障害児の保護者の年収80万1円以上) | 5,000円 | |
| 市町村民税非課税(本人または障害児の保護者の年収80万円以下) | 2,500円 | |
| 生活保護世帯 | 0円 | |
※参照:厚生労働省『自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み』
一方、就労移行支援は、障害者総合支援法にもとづく障害福祉サービスのため、原則1割負担です。ただし、所得に応じて月額の限度額が無料~3万7,200円と定められています。就労移行支援の利用料金については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。
※関連記事:『就労移行支援の利用料金』
※関連記事:『就労移行支援の利用料金』
利用期間の違い
リワークと就労移行支援は、その利用期間や頻度にも違いがあります。
以下は、一般的な利用状況です。
以下は、一般的な利用状況です。
| リワーク | 就労移行支援 | |
|---|---|---|
| 利用期間 | 2~6カ月程度 | 最長2年 |
| 利用頻度 | 週2~5日程度 | 週5日 |
| 1日の利用時間 | 4~6時間程度 | 6~7時間程度 |
いずれも、利用者の状況に応じてプログラムを組むため、利用期間や頻度、時間は個人によって異なります。
リワークは、職場復帰を目標としているため、短期間で集中的におこなわれるのが特徴です。
一方、就労移行支援では、就労を目指してスキル習得やトレーニングをおこなうため、リワークよりも利用期間が長くなる傾向にあります。利用頻度や1日の利用時間は、一般企業での就労に慣れるためにも週5日、6~7時間程度の利用が望まれます。しかし、個人の状況や希望に応じて、より短い頻度や時間から利用を開始することも可能です。
リワークは、職場復帰を目標としているため、短期間で集中的におこなわれるのが特徴です。
一方、就労移行支援では、就労を目指してスキル習得やトレーニングをおこなうため、リワークよりも利用期間が長くなる傾向にあります。利用頻度や1日の利用時間は、一般企業での就労に慣れるためにも週5日、6~7時間程度の利用が望まれます。しかし、個人の状況や希望に応じて、より短い頻度や時間から利用を開始することも可能です。
利用できる施設の違い
リワークと就労移行支援では、利用できる施設の種類にも違いがあります。
一般的に、リワークの多くは医療機関でおこなわれます。その他、障害者職業センター、企業、就労移行支援事業所の全4施設で実施されています。
一方、就労移行支援は就労移行支援事業所でのみ利用できるサービスです。
一般的に、リワークの多くは医療機関でおこなわれます。その他、障害者職業センター、企業、就労移行支援事業所の全4施設で実施されています。
一方、就労移行支援は就労移行支援事業所でのみ利用できるサービスです。
利用条件の違い
リワークの利用は、施設の種類ごとに条件が定められています。
医療機関や障害者職業センター、企業でリワークをおこなう場合、主治医の許可が必要となるのが一般的です。支援を受けることが適切と判断されない場合、利用できないケースもあります。そのため、リワークの利用を検討している人は、主治医に相談すると良いでしょう。
一方、就労移行支援を利用するためには、お住まいの市区町村の福祉窓口への申請が必要となります。その際、障害者手帳もしくは医師の診断書、企業の意見書などの提出が必要な場合があります。
いずれも、施設や自治体によって条件が異なる場合があるため、事前に確認をしましょう。
医療機関や障害者職業センター、企業でリワークをおこなう場合、主治医の許可が必要となるのが一般的です。支援を受けることが適切と判断されない場合、利用できないケースもあります。そのため、リワークの利用を検討している人は、主治医に相談すると良いでしょう。
一方、就労移行支援を利用するためには、お住まいの市区町村の福祉窓口への申請が必要となります。その際、障害者手帳もしくは医師の診断書、企業の意見書などの提出が必要な場合があります。
いずれも、施設や自治体によって条件が異なる場合があるため、事前に確認をしましょう。
リワークと就労移行支援の選び方
ここまでリワークと就労移行支援の違いを解説しました。では、リワークと就労移行支援は、それぞれどのような人が適しているのでしょうか。以下で解説します。
リワークに向いている人
リワークは職場復帰を目的とした支援のため、「職場復帰を目指している休職中の人」が向いているといえます。提供されるプログラムも職場復帰に特化しているため、すでに退職した人や、休職中であっても転職を目指している人などは、就労移行支援がおすすめです。
就労移行支援に向いている人
就労移行支援に向いているのは、「はたらいていない求職中の人」や「休職中で転職を考えている人」などが当てはまります。また、自身のもつ障害や難病の特性と折り合いをつけながら、はたらくスキルを身につけたい人にもおすすめです。
※関連記事:『長期休職中の方に必要なリワークとは?取り組み内容やリワークの効果について解説』
※関連記事:『長期休職中の方に必要なリワークとは?取り組み内容やリワークの効果について解説』
リワーク施設の探し方
利用できるリワーク施設を探す手段として、主に次の3つが挙げられます。
- 探し方
●インターネット検索
●主治医・医療機関
●お住まいの市区町村の福祉担当窓口
インターネットで調べる際は、「リワーク施設 〇〇市」などのキーワードで検索します。
また、「日本うつ病リワーク協会」のサイトでは都道府県別に医療リワークの施設を検索できます。
障害者職業センターでのリワークを検討している場合、高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式サイト内「地域障害者職業センター」で全国の施設が確認できます。
主治医や医療機関に相談すると、自身の症状や状況に適したリワーク施設を紹介してもらえる可能性があります。
お住まいの市区町村の福祉担当窓口では、リワーク施設に関する情報を提供してもらえます。
気になる施設が見つかったら、実際に足を運んで雰囲気やプログラム内容、スタッフの対応などを確認することをおすすめします。
また、「日本うつ病リワーク協会」のサイトでは都道府県別に医療リワークの施設を検索できます。
障害者職業センターでのリワークを検討している場合、高齢・障害・求職者雇用支援機構の公式サイト内「地域障害者職業センター」で全国の施設が確認できます。
主治医や医療機関に相談すると、自身の症状や状況に適したリワーク施設を紹介してもらえる可能性があります。
お住まいの市区町村の福祉担当窓口では、リワーク施設に関する情報を提供してもらえます。
気になる施設が見つかったら、実際に足を運んで雰囲気やプログラム内容、スタッフの対応などを確認することをおすすめします。
リワークの利用方法、開始するまでの流れ
リワークを利用するおおまかな流れは、以下の通りです。
- リワーク開始までのステップ
(1)医師に相談し診断を受ける
(2)実施している施設を医師に紹介してもらう、もしくは自分で探す
(3)見学・説明会・体験利用などに参加する
(4)利用申し込み手続きをおこなう
(5)支援計画を作成し利用開始
リワークは、病状が安定期を迎え、復職を見据えられる状態でなければ利用できません。そのため、まずはかかりつけ医や専門医に相談し、リワークを利用できるか健康状態を確認してもらいます。実施施設は医師が紹介してくれる場合もありますが、なるべく見学や体験を利用し、複数の施設を比較検討すると良いでしょう。施設の雰囲気やスタッフの対応などを確認して、自分に合うかどうか確認してから利用手続きをおこないます。
実施しているプログラムや支援内容は、施設によって異なります。事前に支援スタッフと面談をおこない、自身の状況を伝えると同時に、プログラム内容が自分にあっているか確認しましょう。また、疑問や不安があれば積極的に質問し、その場で解消することをおすすめします。復職に向けた課題を整理し、支援計画を作成すれば正式なプログラムのスタートです。
実施しているプログラムや支援内容は、施設によって異なります。事前に支援スタッフと面談をおこない、自身の状況を伝えると同時に、プログラム内容が自分にあっているか確認しましょう。また、疑問や不安があれば積極的に質問し、その場で解消することをおすすめします。復職に向けた課題を整理し、支援計画を作成すれば正式なプログラムのスタートです。
リワークについてよくある質問
- Q1:リワークは強制ですか?
リワークは強制ではありません。職場復帰にあたって、自分に必要だと感じた場合に利用が推奨されます。ただし、リワークへの参加を復職の条件のひとつとしている企業もあるため、確認が必要です。 - Q2:リワークは誰でも利用できますか?
リワークの対象者は、うつ病や適応障害などの精神疾患が原因で休職中の人です。利用するには主治医からの許可が必要な場合がほとんどです。施設によって利用の条件が異なるため、自身が対象かどうかはあらかじめ確認しておきましょう。 - Q3:リワークを途中でやめても大丈夫ですか?
リワークは、利用を中止することもできます。症状が悪化して続けられない場合やプログラムが自分に合わない場合などは、医師やスタッフと相談して中止も検討しましょう。 - Q4:リワークの利用に障害福祉サービス受給者証は必要ですか?
就労移行支援事業所でリワークプログラムを受講する場合は必要となります。医療機関や障害者職業センター、企業でのリワークの場合は必要ありません。
リワークか就労移行支援か、判断に迷ったら「ミラトレ」に相談しよう
リワークと就労移行支援の違いについて解説しました。どちらも就労を支援する点は同じですが、その目的や支援内容、利用できる施設などが異なる別々のサービスです。そのため、どちらのサービスを利用するのが適切かどうかは、2つのサービスについて理解した上で自身の状況を鑑みて判断することが大切です。
就労移行支援事業所「ミラトレ」では、障害の特性と折り合いながら長くはたらくための支援をおこなっています。事業所によっては、就労移行プログラムや定着支援プログラムだけでなく、リワークプログラムも実施しています。就労移行支援とリワークのどちらを利用すべきか判断に迷う場合は、ミラトレにて相談を受け付けています。気軽にお問い合わせください。
就労移行支援事業所「ミラトレ」では、障害の特性と折り合いながら長くはたらくための支援をおこなっています。事業所によっては、就労移行プログラムや定着支援プログラムだけでなく、リワークプログラムも実施しています。就労移行支援とリワークのどちらを利用すべきか判断に迷う場合は、ミラトレにて相談を受け付けています。気軽にお問い合わせください。

執筆 : ミラトレノート編集部
パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業ミラトレが運営しています。専門家の方にご協力いただきながら、就労移行支援について役立つ内容を発信しています。
アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3

アクセスランキングAccess Ranking
-
No.1

-
No.2

-
No.3