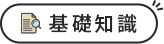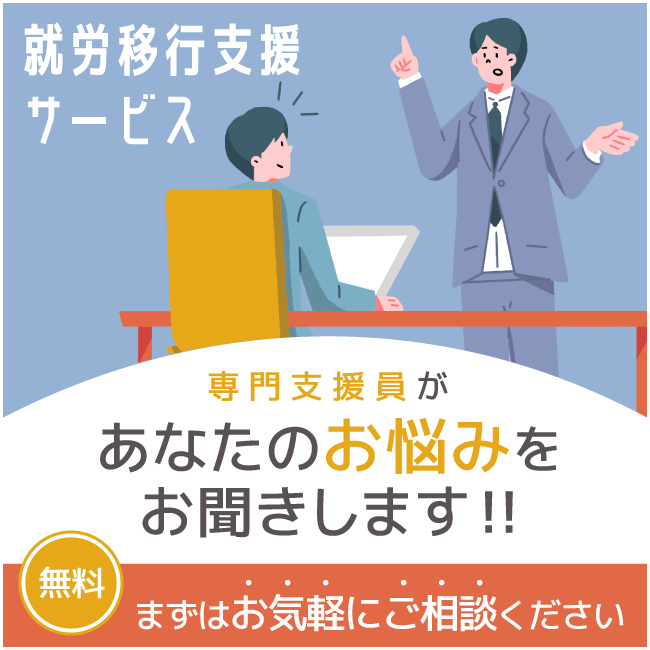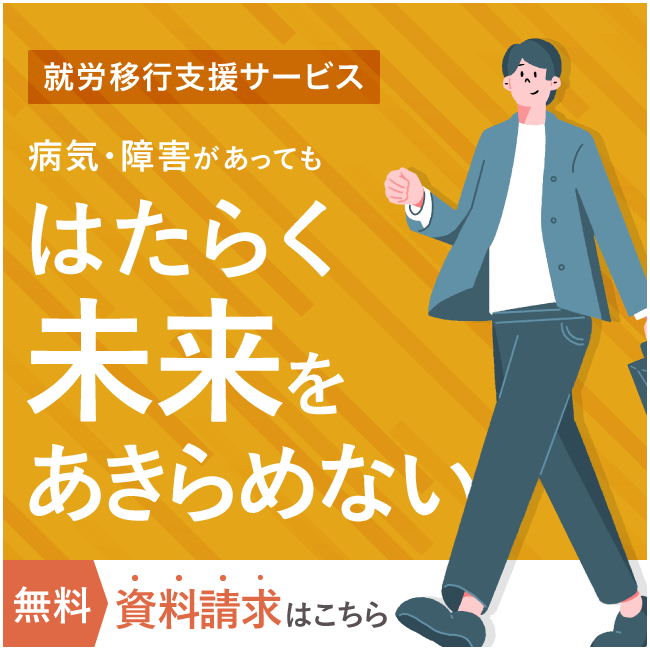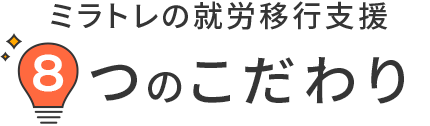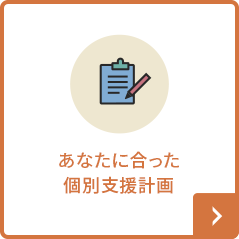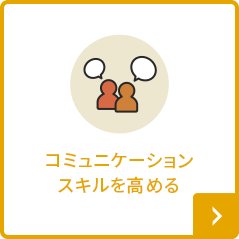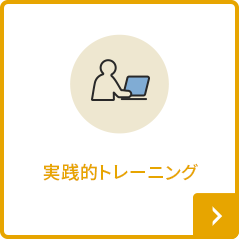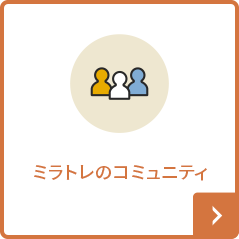ミラトレノート
就労移行支援の
 基礎
基礎 知識
知識


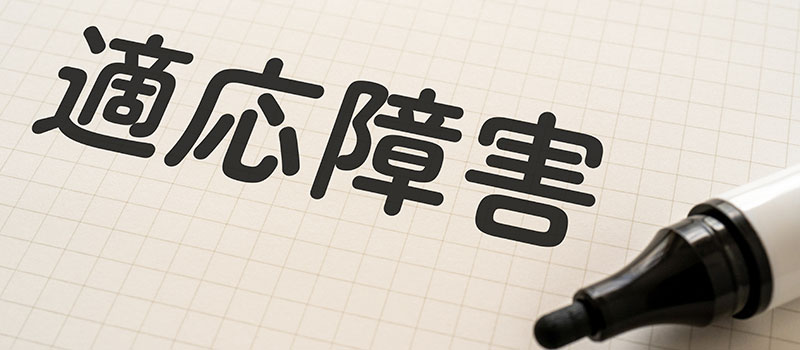
近年、仕事のストレスでメンタルヘルスの不調を訴える人が増えています。厚生労働省の2023年度調査によると、仕事に強い不安やストレスを感じている人の割合は82.7%に上りました。中には、ストレスが原因で適応障害になり、意欲の低下や睡眠障害などさまざまな症状が表れるケースもあります。「どうしても会社に行く意欲がわかない」という人は、適応障害の可能性を疑ってみた方が良いかもしれません。また、すでに適応障害が明らかになったものの、「経済的な不安から退職に踏み切れない」という人もいるでしょう。そのような悩みをもつ人に向けて、退職を検討する前におこなうべきことや、退職を決断した後の流れについて解説します。
※関連記事:『会社が怖いと不安を感じる人は適応障害の可能性も。うつ病との違いや対処法について』
※出典:厚生労働省『令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)の概況』
目次
-
1.適応障害で退職を検討する前にやるべき4つのこと
-
1-1.家族に相談する
-
1-2.医師に相談する
-
1-3.業務の調整について上司に相談する
-
1-4.休職を検討する
-
2.円満退職に向けたステップ
-
2-1.ステップ1:医療機関で診断書の作成を依頼する
-
2-2.ステップ2:退職の意思を家族に伝える
-
2-3.ステップ3:退職の意志を上司に伝える
-
2-4.ステップ4:社会保険の手続きに向けた準備をする
-
3.適応障害で退職する際の伝え方
-
4.適応障害で退職した後に活用したいサポート
-
4-1.雇用保険(失業保険)
-
4-2.自立支援医療制度
-
4-3.傷病手当金
-
4-4.労災保険
-
4-5.障害者手帳
-
4-6.障害年金
-
4-7.生活保護
-
5.適応障害の退職に関する「よくある質問」
-
5-1.Q.1 適応障害を理由に即日退職できますか?
-
5-2.Q.2 適応障害を理由とした退職は自己都合退職になりますか?
-
5-3.Q.3 適応障害で退職しても、雇用保険は給付されますか?
-
6.就労移行支援でストレス対処法を身につけ、自分に合ったはたらき方を
適応障害で退職を検討する前にやるべき4つのこと
家族に相談する
医師に相談する
また、会社に業務調整の相談をする際、診断書があると上司の理解を得やすくなる場合があるため、必要に応じて診断書の作成を依頼しましょう。産業医がいる会社であれば、面談の依頼をおすすめします。産業医からの助言・指導が、業務内容や職場環境の改善につながることがあるでしょう。
業務の調整について上司に相談する
休職を検討する
※関連記事:『適応障害で仕事を続けるメリットデメリット』
※関連記事:『長期休職中の方に必要なリワークとは?取り組み内容やリワークの効果について解説』
円満退職に向けたステップ
ステップ1:医療機関で診断書の作成を依頼する
ステップ2:退職の意思を家族に伝える
ステップ3:退職の意志を上司に伝える
ステップ4:社会保険の手続きに向けた準備をする
| 社会保険の種類 | 必要な手続き |
|---|---|
| 社会保険(健康保険) |
職場の社会保険(健康保険)に加入している場合、退職後の社会保険は下記のいずれかに変更します。保険料などを比較しながら選びましょう。 (1)現在の健康保険を任意継続する (1)「協会けんぽ」の場合は協会けんぽ支部へ、「健康保険組合」の場合は各健康保険組合に相談する |
| 年金 | 会社の厚生年金に加入している場合、国民年金への切り替えが必要です。お住まいの市区町村役所の年金窓口や年金事務所で手続きします。保険料の納付が難しい場合は、免除の申請をおこないましょう。 |
雇用保険(失業保険) |
退職前に最寄りのハローワークへ相談しましょう。 |
※参考:『全国健康保険協会 会社を退職するとき』
※参考:『日本年金機構 会社を退職したときの国民年金の手続き』
適応障害で退職する際の伝え方
会社に退職願の規定がある場合を除き、書き方に定めはありませんが、退職理由と退職日、名前は忘れず記載しましょう。退職理由として適応障害にふれる必要はなく、「一身上の都合」や「健康上の理由」で問題ありません。職場の人に感謝の気持ちを伝えたいときは、挨拶文を作成するのも良いでしょう。
「退職願」と「退職の挨拶」の文例を紹介します。
- 【退職願 文例】
このたび一身上の都合により、〇〇年〇月〇日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。 - 【退職の挨拶 文例】
体調不良により長らく休職させていただき申し訳ありません。体調が思わしくなく復職の見通しが立たないため、誠に勝手ながら〇〇年〇月〇日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
皆様方にご心配とご迷惑をおかけしたまま退職することをお詫び申し上げます。末筆ながら、皆様方のご健勝と◯◯社の益々のご発展を心よりお祈りしております。
適応障害で退職した後に活用したいサポート
雇用保険(失業保険)
※参考:『ハローワーク 基本手当について』
自立支援医療制度
※参考:『厚生労働省 自立支援医療(精神通院医療)の概要』
傷病手当金
労災保険
※参考:『厚生労働省 労災保険相談ダイヤル』
障害者手帳
障害年金
生活保護
※関連記事:『適応障害の人の仕事選びのポイントや長くはたらき続けるコツ』
適応障害の退職に関する「よくある質問」
Q.1 適応障害を理由に即日退職できますか?
Q.2 適応障害を理由とした退職は自己都合退職になりますか?
※参考:『厚生労働省 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準』
Q.3 適応障害で退職しても、雇用保険は給付されますか?
就労移行支援でストレス対処法を身につけ、自分に合ったはたらき方を
就労移行支援事業所「ミラトレ」では、ストレスコントロール法をはじめとする健康管理法や、就職に必要なスキルを身につけるためのトレーニングをおこなっています。職場環境にスムーズに馴染めるよう、擬似就労などの実践的なトレーニングも実施。就職後も、仕事の悩みや不安を解消できるよう支援をおこなっています。事業所によっては、休職中のリハビリテーション「リワークプログラム」を実施し、復職をサポートしています。プログラム内容や支援内容について知りたい方は、気軽にお問い合わせください。

執筆 : ミラトレノート編集部
パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業ミラトレが運営しています。専門家の方にご協力いただきながら、就労移行支援について役立つ内容を発信しています。
-
No.1

-
No.2

-
No.3

-
No.1

-
No.2

-
No.3