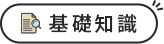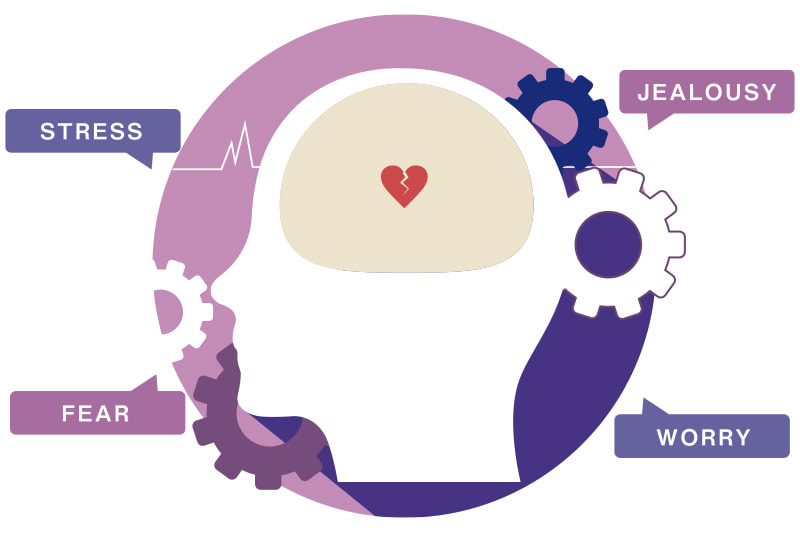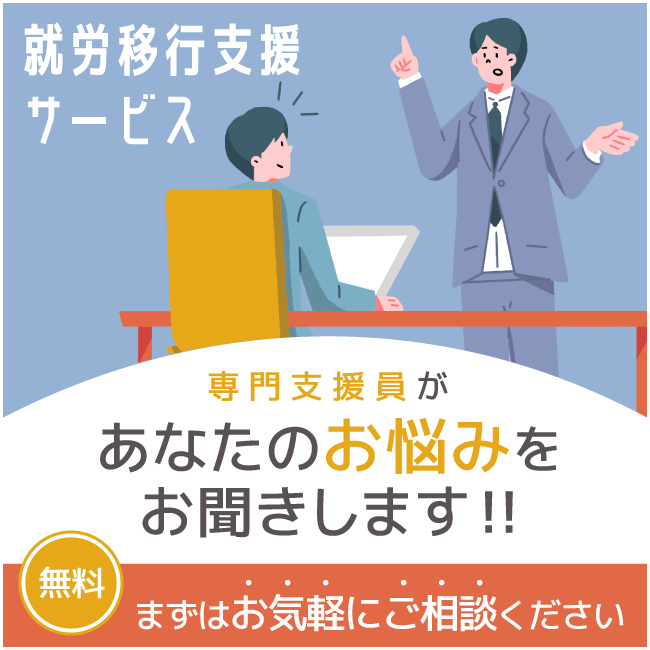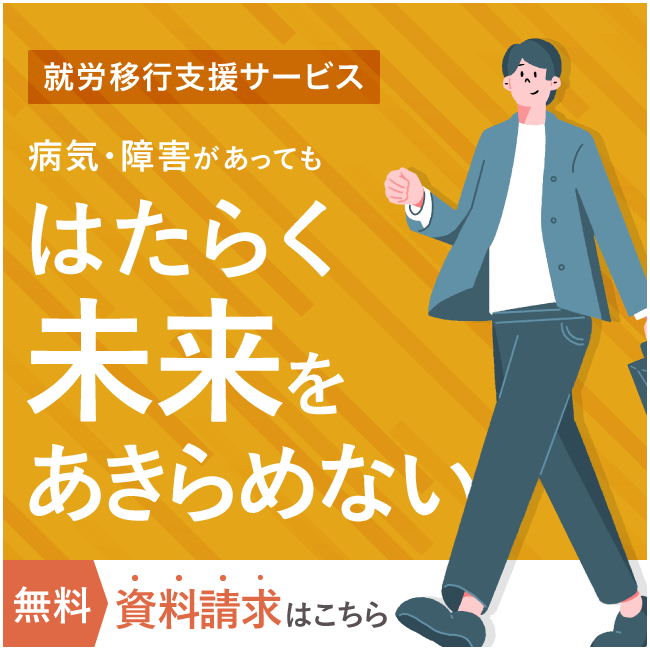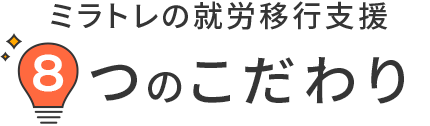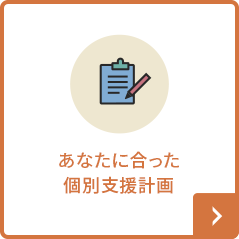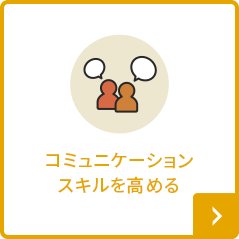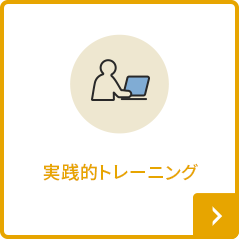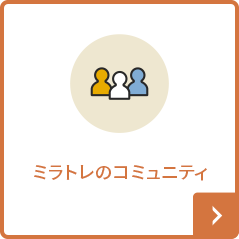ミラトレノート
就労移行支援の
 基礎
基礎 知識
知識



統合失調症とは、認知機能障害や幻覚、妄想などの症状が現れることのある精神疾患です。一生涯で発症する人の割合は約100人に1人といわれており珍しい障害ではありませんが、原因はいまだ明らかになっていません。脳機能の乱れやストレス、遺伝的要因などさまざまな原因が考えられています。
統合失調症を発症すると、思考力や集中力が低下して業務に影響が出たり、周りの目が気になって人間関係が円滑に運ばなくなったりして、はたらきづらさを感じることがあるかもしれません。統合失調症の悩みは一人で抱え込まず、周囲の理解を求めることが大切です。また、退職するかどうかは慎重に考える必要があります。今回は、退職前にできることや、退職しても前向きに次のステップへ進むための準備について解説します。
※関連記事:『会社が怖いと不安を感じる人は適応障害の可能性も。うつ病との違いや対処法について』
※出典:厚生労働省『令和5年 労働安全衛生調査(実態調査)の概況』
目次
-
1.統合失調症で退職を検討する前に実行したい5つのこと
-
1-1.家族に相談する
-
1-2.医師に相談する
-
1-3.退職以外の選択肢も考える
-
1-4.はたらき方を変更する
-
1-5.休職して心身を整える
-
2.統合失調症で会社を退職する際のステップ
-
2-1.ステップ1:医療機関で診断書をもらう
-
2-2.ステップ2:家族に伝える
-
2-3.ステップ3:上司に伝える
-
2-4.ステップ4:社会保険に関わる手続きの準備をする
-
3.統合失調症で退職する際の会社への伝え方
-
4.退職後に活用したいサポート
-
4-1.雇用保険(失業保険)
-
4-2.自立支援医療制度
-
4-3.傷病手当金
-
4-5.障害者手帳
-
4-6.障害年金
-
4-4.労災保険
-
4-7.生活保護
-
5.統合失調症の退職でよくある質問
-
5-1.Q.1 統合失調症で退職をした場合、雇用保険(失業保険)を受けられる?
-
5-2.Q.2 統合失調症での退職は自己都合退職になる?
-
5-3.Q.3 統合失調症で即日退職はできる?
-
6.「ミラトレ」では特性理解と再就職を専門家がサポート
統合失調症で退職を検討する前に実行したい5つのこと
家族に相談する
医師に相談する
退職以外の選択肢も考える
はたらき方を変更する
休職して心身を整える
※関連記事:『長期休職中の方に必要なリワークとは?取り組み内容やリワークの効果について解説』
統合失調症で会社を退職する際のステップ
ステップ1:医療機関で診断書をもらう
ステップ2:退職の意思を家族に伝える
ステップ3:退職の意志を上司に伝える
ステップ4:社会保険に関わる手続きの準備をする
| 社会保険の種類 | 必要な手続き |
|---|---|
| 社会保険(健康保険) |
職場の社会保険(健康保険)に加入している場合、退職後の社会保険は下記のいずれかに変更します。保険料などを比較しながら選びましょう。 (1)現在の健康保険を任意継続する 「協会けんぽ」の場合は協会けんぽ支部へ、「健康保険組合」の場合は各健康保険組合に相談する お住まいの市区町村役所に設置されている国民健康保険の係に相談する 保険に加入している家族の勤務先を通じて加入する |
| 年金 | 会社の厚生年金に加入している場合、資格喪失日から14日以内に国民年金へ切り替える必要があります。お住まいの市区町村役所の年金窓口や年金事務所で手続きします。保険料の納付が難しい場合は、免除の申請をおこないましょう。 |
雇用保険(失業保険) |
退職前に最寄りのハローワークへ相談しましょう。 |
※参考:『全国健康保険協会 会社を退職するとき』
※参考:『日本年金機構 会社を退職したときの国民年金の手続き』
適応障害で退職する際の伝え方
会社に退職願の規定がある場合を除き、書き方に定めはありませんが、退職理由と退職日、名前は忘れず記載しましょう。退職理由として適応障害にふれる必要はなく、「一身上の都合」や「健康上の理由」で問題ありません。職場の人に感謝の気持ちを伝えたいときは、挨拶文を作成するのも良いでしょう。
「退職願」と「退職の挨拶」の文例を紹介します。
- 【退職届 文例】
退職届
✕✕年✕✕月✕✕日
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇殿
△△部 △課
氏名(印)
私儀
このたび一身上の都合により、
勝手ながら、〇〇年〇月〇日をもって退職いたします。
以上
統合失調症で退職した後に活用したいサポート
雇用保険(失業保険)
※参考:『ハローワーク 基本手当について』
自立支援医療制度
※参考:『厚生労働省 自立支援医療(精神通院医療)の概要』
傷病手当金
申請書は、健康保険証に記載されている管轄の協会けんぽ支部に郵送します。受給できる期間は、支給開始日から最長1年6カ月です。
- 条件
(1)退職日までに1年以上継続して健康保険に加入していること
(2)退職日の前日までに、療養のため続けて3日以上休職し、退職日も療養のためにはたらけていないこと
(3)失業保険を受けていないこと
(4)在職中と同じ病気や障害によって、退職後も療養のためにはたらけない状態であること
(5)はたらけない期間が継続していること(断続的な支給は受けられない)
障害者手帳
障害年金
労災保険
※参考:『厚生労働省 労災保険相談ダイヤル』
生活保護
これらの支援制度は必ずしも併用できません。たとえば、障害年金と雇用保険は同時に支給されないケースがあります。詳しくは、障害者相談支援センターなどの相談窓口で確認すると良いでしょう。
統合失調症の退職でよくある質問
Q.1 統合失調症で退職をした場合、雇用保険(失業保険)を受けられる?
Q.2 統合失調症での退職は自己都合退職になる?
Q.3 統合失調症で即日退職はできる?
「ミラトレ」では特性理解と再就職を専門家がサポート
就労移行支援事業所「ミラトレ」では、体調管理法やビジネススキルを身につけながら、「自分に合うはたらき方」を支援員と一緒に見つけていきます。書類作成や面接対策などの就職活動もきめ細やかにサポート。就職後も、日常や仕事での困りごとに寄り添いながら、職場への定着を支援していきます。「支援内容について知りたい」「自分の障害や就職について相談したい」という方は、お気軽にミラトレへご相談ください。

執筆 : ミラトレノート編集部
パーソルダイバースが運営する就労移行支援事業ミラトレが運営しています。専門家の方にご協力いただきながら、就労移行支援について役立つ内容を発信しています。
-
No.1

-
No.2

-
No.3

-
No.1

-
No.2

-
No.3